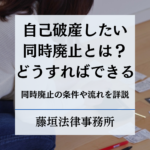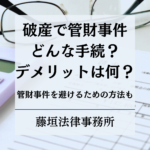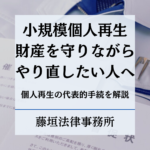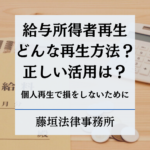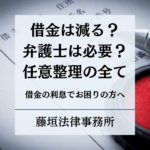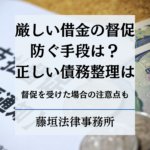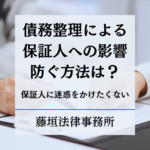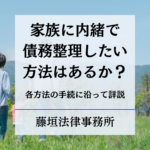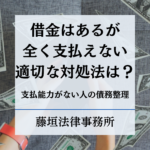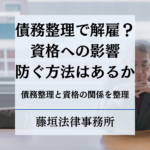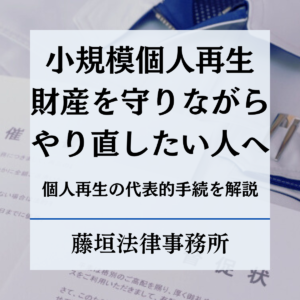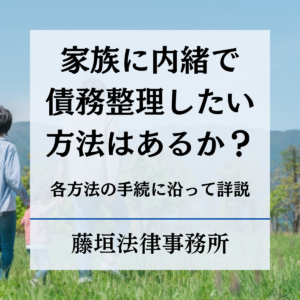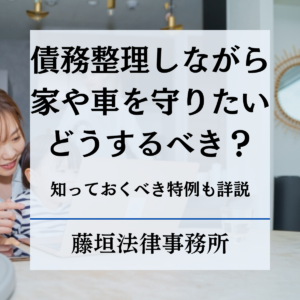公務員であっても自己破産を行うことは可能です。
自己破産は誰にでも認められている法的な債務整理の手段であり、公務員だからといって例外的に制限されることはありません。
国家公務員法や地方公務員法においても、自己破産をしたこと自体を理由に懲戒処分とする規定はなく、自己破産のみを理由に懲戒免職や停職となることは原則としてありません。
ただし、借金の原因が職務上の重大な違法行為である場合には、その違法行為を理由に懲戒処分を受ける可能性はあり得ます。
代表例としては、横領行為や背任行為といった深刻な職務違反が挙げられます。
もっとも、これらはあくまで自己破産を原因とする不利益ではありません。
職務上の信用を損なうような違法行為がなければ、自己破産を選択しても原則としてクビになることは考えにくいでしょう。
公務員が自己破産を理由に懲戒免職になるのは稀なケース
自己破産を理由に公務員が懲戒免職となるケースは、非常にまれです。
国家公務員法および地方公務員法では、懲戒処分の対象となる行為は「信用失墜行為」や「職務上の義務違反」などに限定されており、自己破産そのものは処分理由には該当しないのが通常です。
この点、懲戒免職につながる可能性があるケースとしては、以下のような例が挙げられるでしょう。
- 借金の原因が職務に関連する不正行為(横領した金銭の費消など)である場合
- 債権者からの度重なる督促・訴訟等により、職場に重大な迷惑や信用失墜をもたらした場合
- 秘密保持義務や服務規律に違反する形で債務整理を行った場合
一方、借金の原因が生活費や家族間の事情など、個人的な理由にとどまる場合は、特に不適切な方法で自己破産を進めるのでない限り、自己破産を理由に懲戒免職となることは考えにくいでしょう。
自己破産が昇進や評価に与える直接的な影響は限定的
公務員が自己破産をしたとしても、それだけを理由に昇進が停止されたり、不利益な人事評価を受けたりすることを法的に正当化する根拠はありません。
国家公務員法・地方公務員法においても、自己破産を理由に差別的な扱いをすることを可能とする規定はないため、昇進や評価は、端的に職務遂行能力や勤務実績等に基づいて判断されることになります。
また、破産手続が開始されると、一定の職業や資格には制限が生じますが、公務員としての立場はそのような制限の対象に含まれていません。
そのため、業務の範囲に法的な制限が生じる恐れもないでしょう。
ただし、事実上の間接的な影響が生じる可能性は否定できないところです。
自己破産が昇進や評価に間接的な影響を与えるケースとしては、以下のような場合が考えられます。
- 債務整理の情報が周囲に知られ、職場内の人間関係に悪影響が生じる場合
- 管理職としての信用性や金銭管理の資質が十分でないと判断される場合
- 転居や給与の差し押さえなどが生じ、職場に大きな負担を与えた場合
もっとも、これらの影響はあくまで事実上のものであり、影響の程度も限定的であるのが通常です。
職務を適切に果たしている限り、過度に懸念する必要は大きくないでしょう。
おすすめの記事:債務整理におすすめ法律事務所20選を人気比較!費用が安いのはどこ? | ココモーラ
なぜ「公務員は自己破産できない・クビになる」という誤解が広まっているのか
公務員は自己破産できない、公務員が自己破産するとクビになる、といった誤解をされている場合は少なくありませんが、特に法的な根拠はありません。
これらの誤解が広まる理由としては、以下のような点が考えられます。
- 公務員に高い倫理性や信用性が求められること
-
公務員は、職務の性質上、倫理性や信用性が重視されやすいものです。そのため、金銭面のトラブルがあると、信用を損なうため懲戒処分の対象になる、といったイメージが先行し、誤解につながる可能性があります。
- 過去の不正確な情報が強く影響している
-
公務員が自己破産をすることは望ましくないとのイメージから、公務員と自己破産との関係について、不正確な情報が流通してしまうことも一定数あります。これらの情報が受け手に強く影響し、誤解の原因となる可能性があり得ます。
- 一部の特殊な事例が誤解を生んでいる
-
公務員が懲戒処分を受ける場合、国民にとって必要な情報として公開される場合が少なくありません。そのため、一部の特殊な事例で公務員が懲戒解雇になると、その事実が広く知られるケースもありますが、事例が特殊であることは理解されないまま、誤解の原因となる可能性があり得ます。
現在では、インターネットを通じて様々な情報を入手することができますが、それらがすべて正しい内容であるとは限りません。
根拠のない誤解を防ぐためには、専門家や公的機関など、情報源が信頼できることを重視するのが有益でしょう。
公務員の自己破産、職場や家族にバレる可能性と対策

自己破産を検討する上で、「職場や家族に知られてしまうのではないか」という不安は非常に大きな問題です。
実際、情報が漏れる可能性はゼロではありませんが、事前に仕組みを理解し、適切な対応を取ることで、バレるリスクを最小限に抑えることも可能です。
職場や家族にバレる可能性を把握して対策を講じるためには、まずバレる際の主な経路を把握することが重要です。
あわせて、経路ごとに適した対策を講じることで、個別の状況に合わせた十分なリスク回避が可能になるでしょう。
なお、職場や家族に発覚するリスクの多くは、専門家を通じて手続きを進めることによって、大きく低減させることが可能です。
具体的な対応に悩みが生じる場合は、専門的な知識経験を持つ弁護士や司法書士といった専門家への依頼も有力な手段になります。
「官報」掲載でバレる?公務員への影響と現実的な可能性
自己破産を行うと、裁判所による破産手続開始決定がなされた段階で、その情報が「官報」という国の公報紙に掲載されます。
これは、法令の規定に基づき、公告する必要のある情報については、官報に掲載する方法で周知する必要があるためです。
官報には、破産者の氏名や住所、手続きの内容等が掲載されます。
官報は誰でも閲覧することができますが、一般の人が日常的にチェックする可能性は極めて稀です。
通常、官報をきっかけにバレることはあまりないと言えるでしょう。
ただし、法律関係や金融関係の部門では、経理や人事の関係で官報のチェックが行われ、把握される可能性も否定できません。
官報に近しい立場の場合、可能性は低いながらもゼロではない、と理解するのが適切でしょう。
もっとも、官報経由で職場に自己破産がバレたとしても、自己破産そのものは法律上の正当な手続きであり、不適切な行動ではありません。
そのため、職場にバレたと過敏になる必要はないことを正しく把握しておきましょう。
退職金や共済組合の手続きでバレるケースとその回避策
公務員が自己破産をする際に、退職金や共済組合の関係を処理する必要がある場合、職場にバレる可能性は否定できません。
まず、破産手続では破産者の財産を全て明らかにする必要があり、将来支給される退職金も財産の一部となります。
そのため、退職金制度の対象となる場合には、勤務先(所属庁)に「退職金見込額証明書」の作成を依頼する必要があり、作成依頼を通じて破産手続の情報が職場に伝わる可能性があるでしょう。
また、共済組合から住宅貸付などの借入がある場合、共済組合は破産手続きにおける債権者となるため、弁護士や裁判所などの通知を受けて破産手続きを把握することになります。
共済組合と勤務先が密接な関係にある場合には、共済組合から間接的にバレる可能性も考えられます。
これらのリスクをゼロにすることは困難ですが、弁護士や司法書士といった専門家を通じたやり取りにすれば、リスクを最小限に抑える余地はあります。
専門家が窓口になる場合、退職金見込額証明書の請求に際して破産に関する情報を与えないようにしたり、職場内や共済組合内での情報共有を必要最小限にしてもらったりすることで、破産の事実がバレない可能性もあり得るでしょう。
不安がある場合には、専門家への相談、依頼が有力な回避策になりやすいと言えます。
給与差押えを回避すれば、職場にバレるリスクは大幅減
公務員に限らず、給与が差し押さえられると、職場にバレる可能性が高くなります。
給与の差押えは、裁判所を通じて勤務先に直接通知が届くため、少なくとも差し押さえを受けるような金銭トラブルがあることは明らかになってしまうでしょう。
もっとも、差押えが行われる前に、速やかに適切な行動をすることで、職場にバレるリスクを大きく減少させることも可能です。
具体的には、弁護士に依頼し、早期に弁護士から対応してもらうことが最も適切でしょう。
弁護士が依頼を受けると、債権者に対して「受任通知」を送付します。
そして、貸金業者が受任通知を受領すると、借金の督促をすることが法律上禁じられるため、現実的には債務者や弁護士の動向を待つことになります。
これにより、給与差押えを防げる可能性が非常に高くなるでしょう。
ここで重要なのは、債権者からの給与差押えに至るより前に、督促を受けている段階で早期に行動することです。
債権者は、いきなり差押えをすることは通常なく、段階的に請求方法を強めていくことが一般的です。
そのため、請求方法が給与差押えという強いものになる前に、迅速に対応することで、給与差押えを防ぎやすくなります。
給与が差し押さえられると、精神的にも社会的にも大きな負担や不利益が避けられません。
事前に適切な対応を尽くせば、生活や信用を保ちながら自己破産を行うことが可能になるでしょう。
家族にバレずに自己破産手続きを進めるための注意点
自己破産手続きは、ポイントを正しく押さえておくことで、家族への影響を防ぎながら進められる可能性が非常に高くなります。
家族への心配を避けたい場合には、以下の注意点を踏まえた対応が適切です。
- 弁護士との連絡方法
-
弁護士に手続きを代行してもらうことで、郵便物の宛名や文書の通知先が全て弁護士の事務所になるため、家族に知られることなくやり取りが進められます。
ただし、弁護士と自分との間でやり取りする方法や、弁護士と電話する際の時間帯には、十分な配慮が必要でしょう。家族とともに在宅している時間帯に破産手続きのやり取りが生じると、家族にバレるリスクが飛躍的に高まります。 - 同居家族の財産への影響
-
自己破産の手続きが進んでも、基本的に同居家族の財産には影響がありません。自己破産は、あくまで自分個人の債務と財産を整理する制度であるためです。
もっとも、同居家族の財産に例外的な影響が生じるケースがある点には注意が必要です。代表例としては、同居家族と共同の名義になっている財産や債務が挙げられます。
例えば、自宅を夫婦共同の名義にしており、夫が自己破産をした場合、現実的には自宅を処分せざるを得なくなる場合もあるでしょう。 - 正直に話すことのメリット
-
自己破産を行う際、家族に対して正直に話すことも有力な選択肢の一つです。家族に事情や状況を理解してもらうことができれば、サポートを得られ、手続きを円滑に進めることも可能でしょう。
家族への影響を防ぐ手段は、必ずしも家族にバレないことのみではありません。必要に応じて正直に話すことも検討することをお勧めします。
公務員が自己破産するデメリットと影響
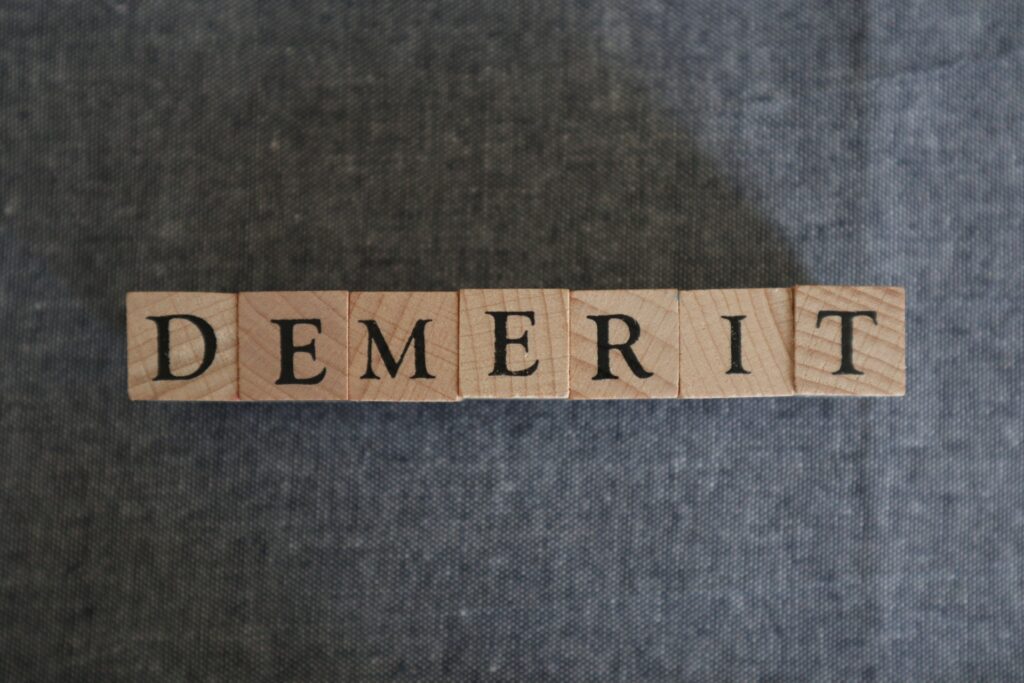
自己破産をすることで、借金の返済義務から解放されるという大きなメリットがある一方で、当然ながらいくつかのデメリットや制限も存在します。
この点、公務員の場合、一般の方にはない公務員ならではの注意点も含まれます。
もっとも、デメリットがあるからといって、自己破産が有効な手段でない、ということにはなりません。
むしろ、デメリットが限定的であり、自己破産をする利点の方がはるかに大きい場合も少なくありません。
デメリットやその影響を適切に理解することができれば、個別のケースで自己破産がどれだけ有効であるか、正しく判断することができるでしょう。
財産はどうなる?差押え対象となるもの・ならないもの
自己破産をすると、すべての財産を失うのではないかと不安に感じる方も多いかもしれません。
しかし、生活に必要な一定範囲の財産は「自由財産」として残すことが認められており、すべてを差し押さえられるわけではありません。
自由財産に該当するものの例としては、以下のようなものがあります。
自由財産の該当例
- 99万円以下の現金や預貯金
- 生活必需品(家具、衣類、寝具、冷蔵庫や洗濯機などの家電)
- 退職金の一部(退職予定がない場合は8分の7、退職予定の場合は4分の3)
- 保険契約の解約返戻金が20万円未満の場合(解約が不要)
一方、以下のような財産は差押え対象になることが見込まれます。
差押え対象の該当例
- 自宅などの不動産
- 高額な自動車
- 高級時計やブランド品、美術品など
- 99万円を超える現金・預貯金
なお、自由財産の扱いについては、個別の判断が必要になりやすいため、自身のケースでどこまでが差押えの対象になるかは専門家への相談をお勧めします。
早期に弁護士へ相談することで、日常生活への支障を最小限に抑える方策を提案してもらえることも少なくありません。
信用情報(ブラックリスト)への登録期間と影響
債務整理を行うと、「ブラックリストに載る」と言われる状態になります。
これは、信用情報機関に「金融事故情報」が登録されることを指します。
信用情報とは、クレジットカードの利用履歴やローンの契約状況、返済の遅れなどを記録した情報のことです。
金融事故情報が登録される主な信用情報機関は、以下の3社です。
- JICC(日本信用情報機構)
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- JBA(全国銀行個人信用情報センター)
金融機関やカード会社は、これらの信用情報機関の情報をもとに、申込み者にお金を貸すかどうか、クレジットカードを発行するかどうかを判断しています。
ブラックリストに登録された場合、その期間中は、新たなローンやクレジットカードの申込みが基本的に通らなくなります。
債務整理の手続きごとに、事故情報が登録される期間は以下のとおりです。
また、現在利用しているカードやローンも途中で利用停止・契約終了となる場合があります。
任意整理:完済から5年間
個人再生:JICC5年間、KSC7年間
自己破産:JICC・CIC5年間、KSC7年間
信用情報への事故登録は一生続くものではありません。
登録期間が終了すれば、事故情報は削除され、再びローンやクレジットカードの申込みができるようになります。
ただし、削除されたからと言って必ずしも直ちに審査に通るわけではなく、一定の悪影響が生じる可能性もあり得ます。
公務員の資格制限はある?該当する職種と期間
自己破産をすると、一定の職業・資格に就けない期間が一時的に発生します。
具体的に資格制限の対象となる職業や資格の例としては、以下のものが挙げられます。
- 弁護士、司法書士、税理士などの士業
- 警備員
- 生命保険募集人
- 一部の会社役員(取締役、監査役など)
なお、この制限は破産手続中(破産手続開始決定から免責許可決定まで)に限られるため、免責許可決定が確定すれば、制限は解除され、もとの職業に戻ることが可能です。
もっとも、公務員の大半の職種(事務職、技術職、教職員、行政職など)は、これらの資格を前提に働いているわけではないため、自己破産をしても日常的な業務や職務の遂行に支障は生じづらいでしょう。
退職金への影響は?差押えの範囲と注意点
将来の退職金は、破産者の財産の一種として扱われます。
しかし、退職金の全額が失われるわけではなく、退職金の扱いには一定の配慮がなされています。
具体的な取り扱いの内容は、以下のとおりです。
- 原則
-
具体的な退職予定はないものの、退職時に退職金の支給が見込まれる状況である場合、支給見込額の8分の1が差押えの対象となります。将来の退職金は、実際に全額支給されるかどうか不明確であるため、低い評価にとどめることで破産者を保護しています。
- 具体的な退職予定がある場合
-
近い時期に退職が予定されていて、退職金予定額が現実に支払われる可能性が高い場合、支給見込額の4分の1が差押えの対象となります。これは、全額支給が見込まれており、8分の1という低い評価をする必要がないと判断されるためです。
- 具体的な取り扱い方法
-
将来の退職金は、その8分の1又は4分の1の価値がある財産として評価されます。例えば、退職予定はないものの、支給見込額が200万円である場合、将来の退職金は200万円×8分の1=25万円分の価値ある財産として扱われ、現金や預貯金と合計して99万円以内であるかを判断されることになります。
共済組合からの借金はどうなる?自己破産時の扱い
公務員の方の中には、共済組合から生活資金や住宅資金などの目的で融資を受けているケースも少なくありませんが、この場合の共済組合は、公務員の債権者に当たります。
そのため、公務員が自己破産する場合、手続き上は金融機関や貸金業者と同様の立場になります。
そのため、共済組合による借金の回収にも一定の制限が生じます。
共済組合からの借金は、給与からの天引きで返済されていることが一般的ですが、公務員が自己破産を弁護士に依頼した後、同じく天引きによる返済を継続してはいけません。
債権者の一部にのみ返済をする結果になってしまい、債権者間で不公平が生じるためです。
そのため、共済組合には、弁護士からの受任通知を受けた段階で給与からの天引きを停止してもらう必要があります。
また、天引きが止まることで、職場への発覚が避けにくい状況にもなるでしょう。
もっとも、弁護士に介入してもらい、早期に適切な手続を進めてもらうことで、影響を最小限に抑えることも可能です。
自己破産がスムーズに進行すれば、職場に広く知られることを防ぎつつ、借金問題の解決を実現することもできるでしょう。
自己破産だけではない!公務員が選べる他の債務整理

公務員でも選べる債務整理の方法は自己破産以外にも複数あります。
たとえば、任意整理や個人再生といった手段は、自己破産に比べて生活や仕事への影響が少なく、財産を手放さずに借金を整理できる余地のある点が大きなメリットです。
特に、公務員の場合、安定収入が見込まれやすいことから、継続返済が必要な任意整理や個人再生も選択できる可能性が高いでしょう。
ここでは、債務整理する手段のうち、どの手続きがどのような状況の人に向いているか、比較解説します。
【任意整理】弁護士が交渉、将来利息カットで返済負担を軽減
任意整理は、弁護士や司法書士を通じて債権者との交渉を行い、将来の利息や遅延損害金をカットした上で返済条件の緩和を目指す手続きです。
裁判所を通さず、債権者と直接交渉する方法であるため、職場や家族には知られにくい点も特徴の一つです。
任意整理は、あくまで合意を目指す手段のため、債権者に応じてもらうことが必要です。
この点、公務員は、比較的安定した収入のある職業と評価されるため、任意整理後の返済も継続が期待されやすく、債権者から交渉に応じてもらえる可能性が高い傾向にあると言えるでしょう。
任意整理が向いているケースとしては、以下の場合が挙げられます。
- 借金元本の返済見込みがある
- 財産を手放さずに債務整理したい
- 周囲に知られたくない
- 安定収入がある
【個人再生】借金を大幅減額、住宅を残せる可能性も
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に(5分の1~10分の1程度)減額し、原則3年(最長5年)で分割返済していくことを目指す手続きです。
自己破産とは異なり、借金を免除されるわけではありませんが、一方で重要な財産を手元に残しながら借金問題を解決できる点に特徴があります。
個人再生の最大の利点の一つが、自宅を手元に残せる可能性がある、という点です。
住宅ローンが残っている場合、債務整理を行うと担保になっている住宅を取り上げられてしまうのが通常ですが、いわゆる住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローン付きの自宅を手放すことなく個人再生を進めることが可能です。
個人再生は、手続後に継続して借金を返済する前提で用いられる制度であるため、利用するためには借金の返済に耐えられる安定収入が必要とされます。
この点、公務員は一般的に安定収入があると評価されるため、個人再生が利用しやすい立場であるということができるでしょう。
個人再生が向いているケースとしては、以下の場合が挙げられます。
- 自己破産は避けたいが、現状では借金の継続返済が困難
- 持ち家を手放したくない
- 安定収入があり、返済計画を立てることができる
【自己破産・任意整理・個人再生】公務員はどれを選ぶべき?
自己破産、任意整理、個人再生の3つは、いずれも借金問題を解決する際に有力な手段ですが、個別のケースでどの手段を選ぶべきであるかは、借金額や収入、財産状況、資格制限の有無、職場への影響が懸念される程度など、様々な事情によって変わります。
複数の事情を総合的に判断して、適切な手段を選択することが必要になるでしょう。
検討するべき項目とそれぞれの手続きとの関係を整理したい場合は、以下を参考にしてみましょう。
比較表
| 検討項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 主な効果 | 将来の利息や遅延損害金のカット、 返済方法の見直し | 借金の大幅な減額(5分の1~10分の1) | 借金の支払義務全額の免除(免責) |
| 対象とする借金 | 選択したもののみ | すべて | すべて |
| 自宅の処分 | 原則として不要 | 住宅ローン特則を利用すれば不要 | 原則として必要 |
| その他財産の処分 | 原則として不要 | 原則として不要 | 必要(必要最低限の財産を除く) |
| 資格制限の有無 | なし | なし | あり |
| 職場に発覚する リスク | 基本的になし | 手続過程で事実上のリスクあり | 手続過程で事実上のリスクあり |
| 利用の条件 | 返済能力 | 返済能力 | 返済が不能 |
| 向いているケース | 借金総額や債権者が比較的少ない | 自宅を守りつつ借金の減額を図りたい | 借金の免除を受けて生活を再建したい |
検討用フローチャート
- 現状で借金の返済は困難か
- いいえ→債務整理はまだ必要なし
はい↓
- 安定した収入があるか(返済原資が確保できるか)
- いいえ(体調不良による収入減少等)→自己破産を検討
はい↓
- 現状で借金の返済は困難か
- いいえ→債務整理はまだ必要なし
はい↓
①借金総額はいくらか
概ね300万円以下→任意整理を検討
概ね300万円超え→個人再生又は自己破産を検討
②資格への影響を防ぎたいか
はい→任意整理or個人再生を検討
いいえ→自己破産も可能
③保証人への影響を防ぎたいか
はい→任意整理を検討
いいえ→個人再生or自己破産も可能
④住宅ローン付きのマイホームに住み続けたいか
いいえ→自己破産を検討
はい↓
- 住宅ローンの負担が重い状況か
- はい→個人再生を検討
いいえ→任意整理(住宅ローン以外)を検討
公務員が自己破産を弁護士に相談するメリットと流れ・費用

公務員の方が自己破産を試みる場合、弁護士への相談や依頼は非常に有力な選択肢です。
特段の事情がない限り、弁護士に依頼することを強くお勧めします。
弁護士に依頼することで、経済的側面と精神的側面の双方で多くのメリットを期待することができます。
また、弁護士費用の負担に不安が残る場合にも、分割払いや法テラスの利用など、負担を軽減するための手段が利用できる場合は少なくありません。
なぜ弁護士?公務員が専門家に依頼すべき5つの理由
自己破産は、自分自身で進めることも手続き上は可能です。
そのため、費用の負担を踏まえ、自分で行うべきか弁護士に依頼する価値があるか、比較検討することも一案でしょう。
この点、基本的には、自己破産を検討する公務員の方は、弁護士への依頼が非常に有益になりやすいと言えます。
その具体的なメリットとしては、以下の5つのポイントが挙げられます。
- 1.職場にバレるリスクを最小限に抑えられる
-
弁護士に依頼した場合、弁護士はまず債権者へ受任通知を送付します。これによって、債務者本人に対する連絡や督促はストップし、債権者からの連絡を通じて職場に発覚する可能性は事実上なくなります。
また、公務員の自己破産では、共済組合や退職金の関係で職場と関係のあるところとのやり取りが発生しますが、弁護士が対応することで適切な配慮を期待でき、職場にバレるリスクを最小限に抑えながら慎重に手続を進められます。
- 2.最適な債務整理の方法が分かる
-
債務整理の方法は自己破産のみでなく、任意整理や個人再生といった手段もあります。公務員の場合、仕事が安定していることから任意整理や個人再生を利用する余地も十分にあるため、方法選択が可能であり、裏を返せば適切な選択を求められることになります。
この点、最適な債務整理の方法を判断するには、専門的な知識経験が不可欠です。債務整理に精通した弁護士に依頼することで、借金額や収入、財産状況等を踏まえて、弁護士が自分に適した債務整理の方法を案内してくれるでしょう。
- 3.複雑な裁判所の手続を一任することができる
-
自己破産を行う場合、裁判所に対して数多くの書面を提出する必要があります。書面作成や提出に関する運用は、事実上の地域差もあるなど、専門家以外が知らないことも少なくないため、裁判所の手続は想像以上に複雑なものとなりやすい面が否めません。
弁護士に依頼した場合、それらの複雑な手続きを弁護士に一任し、裁判所の運用に沿った適切な方法で進めてもらうことが可能になります。弁護士を通じて対応することで、正確かつ円滑な進行が実現できるでしょう。
- 4.債権者とのやり取りや交渉を代行してくれる
-
自己破産に際しては、その準備の過程で複数の債権者とのやり取りが発生します。債権者によっては、時に債務者へ厳しい態度を示されるケースもあり、自身で対応するのは多大な精神的負担が避けられません。
この点、弁護士が間に入り、債権者とのやり取りや交渉を全て代行してもらうことができれば、やり取りの中で生じるストレスを最小限に抑えることができます。対応に必要な時間も割く必要がなくなるため、日常生活への支障も防げるでしょう。
- 5.精神的に安定した状態で進められ、冷静な判断が可能になる
-
借金問題に悩んでいる状況では、精神的に安定するのは困難です。その結果、正しい判断ができなくなり、より深刻な事態を招くケースも一定数見られます。
一方、弁護士に相談や依頼をしている場合には、専門家のサポートで問題解決の見通しが立てられるため、精神的な不安定さを解消しやすくなります。
さらに、冷静で的確な判断も可能になりやすく、借金問題の早期解決につながりやすくなるでしょう。
公務員の自己破産|弁護士に相談する流れ・費用

多くの公務員の方にとって、日頃から弁護士への相談や依頼を行うことはあまりないでしょう。
そのため、相談や依頼の流れ、費用の金額や支払方法などについて、不安が募ることもやむを得ないところです。
もっとも、相談後の見通しが分からないことを理由に、弁護士への相談を控えてしまうのは、解決のチャンスを失うことになりかねません。
相談後の流れを事前に把握することで、積極的に弁護士への相談を行えるようにしましょう。
ここでは、相談から解決までの一般的な流れや、費用相場、支払方法等について解説します。
相談から解決までのステップ|自己破産手続きの一般的な流れ
自己破産を弁護士に相談した後、手続きの完了に至るまでの基本的なステップは、以下のとおりです。
法律事務所に連絡の上、相談予約をします。多くの事務所では無料相談が可能です。相談の際には、借金総額や債権者数、収入や財産の状況、希望する解決方法などを整理し、弁護士の専門的な判断を仰ぎましょう。
弁護士への依頼を決めた場合、正式に委任契約を取り交わします。依頼に際しては、法律事務所との契約書や、弁護士への委任状などを作成することが一般的です。
弁護士が依頼を受けると、まず債権者に対して受任通知を発送します。債権者である貸金業者は、受任通知を受領した後に債務者への督促を行うことが禁じられるため、この段階で取り立てがストップします。
依頼先と協力しながら、債務の状況、収入や支出の状況、保有財産の状況など、必要な情報と根拠資料を準備します。
書類が整った段階で、弁護士が破産手続の申立てを行います。申立てを受けた裁判所では、破産事件を「同時廃止」(目立った財産がない場合)とするか「管財事件」(一定の財産がある場合)とするか判断します。
免責に必要な審尋や、管財事件となった場合に選任される破産管財人との面談を行います。
破産手続が終了し、裁判所から免責が許可されると、借金の返済義務がすべて免除されることになります。
自己破産の弁護士費用相場と支払い方法|分割払いや法テラスも
弁護士への依頼には弁護士費用が発生します。
弁護士というと高額な費用が必要になりそうに思えますが、費用相場や支払方法について正しく理解すれば、無理なく弁護士に依頼することも決して難しくはありません。
自己破産にかかる弁護士費用の一般的な相場は以下のとおりです。
| 着手金 | 20~30万円程度 |
|---|---|
| 成功報酬 | 20~30万円程度(※) |
| 実費 | 数千円~数万円 |
その他、裁判所への予納金として、概ね以下の金額が必要になります。
| 同時廃止事件 | 1~2万円程度 |
|---|---|
| (少額)管財事件 | 20~50万円程度 |
具体的な弁護士費用の金額は、法律事務所によっても異なるため、無料相談を通じて具体的に案内してもらうことが望ましいでしょう。
また、弁護士費用の一括払いが困難なケースに備え、分割払いや後払いに対応している事務所もあります。
弁護士に依頼後、返済がストップした段階で、少しずつ弁護士費用を支払っていくことも可能でしょう。
加えて、収入や資産が一定額を下回る場合、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用することも可能です。
これは、弁護士費用を一時的に立て替えてもらい、長期分割での返済を行っていくものです。
対応している法律事務所の場合、法テラスへの申し込みなどもサポートしてもらえる場合があるため、相談してみるのも一案でしょう。
弁護士費用に関しては、柔軟な支払方法やサポートの制度などが複数あります。
まずは弁護士に相談し、費用の支払いに関するアドバイスを受けてみましょう。
公務員が自己破産を相談する際におすすめの弁護士

自己破産が円滑にできるか、生活の再スタートが適切にできるかは、依頼する弁護士によって結果が大きく変わることも珍しくはありません。
そのため、信頼できる弁護士を選ぶことは、自己破産を成功させるための第一歩と言えるでしょう。
また、公務員の方の場合、公務員特有の問題に対する配慮も不可欠です。
公務員の債務整理に精通しているかどうかも、重要な判断材料とするのが適切です。
ここでは、弁護士の選び方や具体的な相談先について、詳細に解説します。
以下の内容を踏まえて、まず一度弁護士に相談をしてみましょう。
信頼できる弁護士の選び方|公務員の自己破産に強い専門家とは
自己破産の取り扱いや進め方は、弁護士によって様々に異なります。
当然ながら、弁護士の経験やノウハウの有無などによって、手続きの円滑さや安心感は大きく変わってきます。
特に、公務員の自己破産では、職場への配慮などに際して適切な理解が求められるため、公務員の取り扱いに強い弁護士を選ぶことも重要です。
具体的なポイントとしては、以下の点が挙げられます。
- 債務整理(特に自己破産)の実績が豊富であるか
-
弁護士や法律事務所によって専門分野は様々です。そのため、相談先を選ぶ際には、債務整理、特に自己破産に関する解決実績を確認し、専門性があるか把握することが望ましいでしょう。
- 公務員の自己破産に理解があるか
-
公務員の場合、共済制度や退職金の点など、民間とは異なる留意点があります。公務員特有の注意事項を踏まえた弁護士に依頼することで、より的確な対応が期待できるでしょう。
- 丁寧な説明や対応があるか
-
自己破産のためには数か月間のやり取りが必要になります。そのため、弁護士との信頼関係は重要ですが、説明や対応が丁寧な弁護士や法律事務所との間では、信頼関係が築きやすい傾向にあります。
- 費用体系が明確であるか
-
弁護士費用は事務所によって異なります。金額や発生条件も少しずつ異なる場合があるため、費用体系を正しく把握することが重要です。この点、信頼できる弁護士や事務所は、費用の総額や支払方法などを明確に、丁寧に提示してくれます。
公務員の自己破産におすすめの相談先3選
ここでは、自己破産の実績が豊富で、親身に対応してくれる弁護士事務所を厳選してご紹介します。
はたの法務事務所(司法書士法人)
| 対応分野 | 任意整理/自己破産/個人再生/過払い金請求 |
|---|---|
| 費用目安 | 報酬220,000円~ (※但し少額管財事件はプラス220,000円~) |
| 相談料 | 無料 |
| 特徴 | 全国対応/着手金無料/24時間メール受付可 |
はたの法務事務所は、全国対応と豊富な実績を持つ、債務整理に特化した司法書士事務所です。最大の特長は、費用を抑えながら自己破産の準備を進められる点にあります。
司法書士は「申立書類作成の専門家」として、自己破産手続きで最も重要な書類の準備をサポートしてくれます。「着手金無料」で依頼できるため、初期費用をかけずに手続きに着手できるのは大きなメリットです。
「とにかく費用を抑えたい」「手続きは自分自身で主体的に進めたい」という方にとって、非常に有力な選択肢となるでしょう。ただし、司法書士は弁護士と異なり、裁判所での代理人活動(審尋への同席など)は行えません。書類作成のサポートに特化した、費用対効果の高い事務所と言えます。
弁護士法人東京ロータス法律事務所
| 対応分野 | 任意整理/個人再生/自己破産/過払い金請求 |
|---|---|
| 費用目安 | 着手金:¥220,000 報酬金:¥220,000 その他費用 諸費用 ¥55,000 管財の場合 ¥200,000〜 |
| 相談料 | 無料(電話・メール) |
| 特徴 | 着手金無料/分割払い対応/借金減額診断あり |
弁護士法人東京ロータス法律事務所は、借金問題全般、特に自己破産のような複雑な手続きにも豊富な実績を持つ法律事務所です。
自己破産は裁判所を介した法的手続きであり、弁護士に依頼することで全ての窓口対応を任せられます。「着手金無料」で相談できるため、手元に資金がない状態からでも、生活再建に向けた第一歩を踏み出しやすいのが大きな魅力です。
借金の総額が大きく返済の目処が立たない方にとって、費用面の不安を抑えつつ、専門家である弁護士のサポートを受けられる心強い選択肢となるでしょう。
アース法律事務所
| 対応分野 | 任意整理/個人再生/自己破産 |
|---|---|
| 費用目安 | 着手金:220,000円~ |
| 相談料 | 無料(初回) |
| 特徴 | 迅速対応/オンライン面談対応/明確な料金体系 |
アース法律事務所は、債務整理に特化しており、その「迅速な対応」に強みを持つ法律事務所です。
自己破産を決断する方の多くが「一刻も早く取り立てを止めて、平穏な生活を取り戻したい」と願っています。アース法律事務所は、その気持ちに応えるスピード感のあるサポート体制が特徴。弁護士が受任通知を送付することで、債権者からの督促は最短即日でストップします。
初回相談は無料で、費用体系も明確に提示されるため、見通しが立てやすいのも安心材料。精神的な負担を一日でも早く軽減したい方にとって、非常に頼りになる存在です。
まとめ

借金問題に悩む公務員のあなたが、自己破産やその他の債務整理について正しい知識を得て、過度な不安から解放されることが本記事の目的である。
公務員であっても自己破産は可能であり、原則としてそれが理由で職を失うことはない。
職場や家族に知られるリスクも、専門家のサポートを得ることで最小限に抑えることができる。
重要なのは、一人で抱え込まず、できるだけ早く借金問題解決の専門家である弁護士に相談することだ。
無料相談を実施している事務所も多く、あなたにとって最適な解決策を一緒に見つけてくれるはずだ。
この記事が、あなたが勇気を出して第一歩を踏み出すための一助となれば幸いである。
- 公務員も自己破産できることを理解した
- 自己破産で原則クビにはならないことを確認した
- バレるリスクと対策を把握した
- デメリットを理解し、他の債務整理と比較検討した
- 弁護士に相談するメリットと流れを理解した
- 無料相談を利用する準備ができた
FAQ