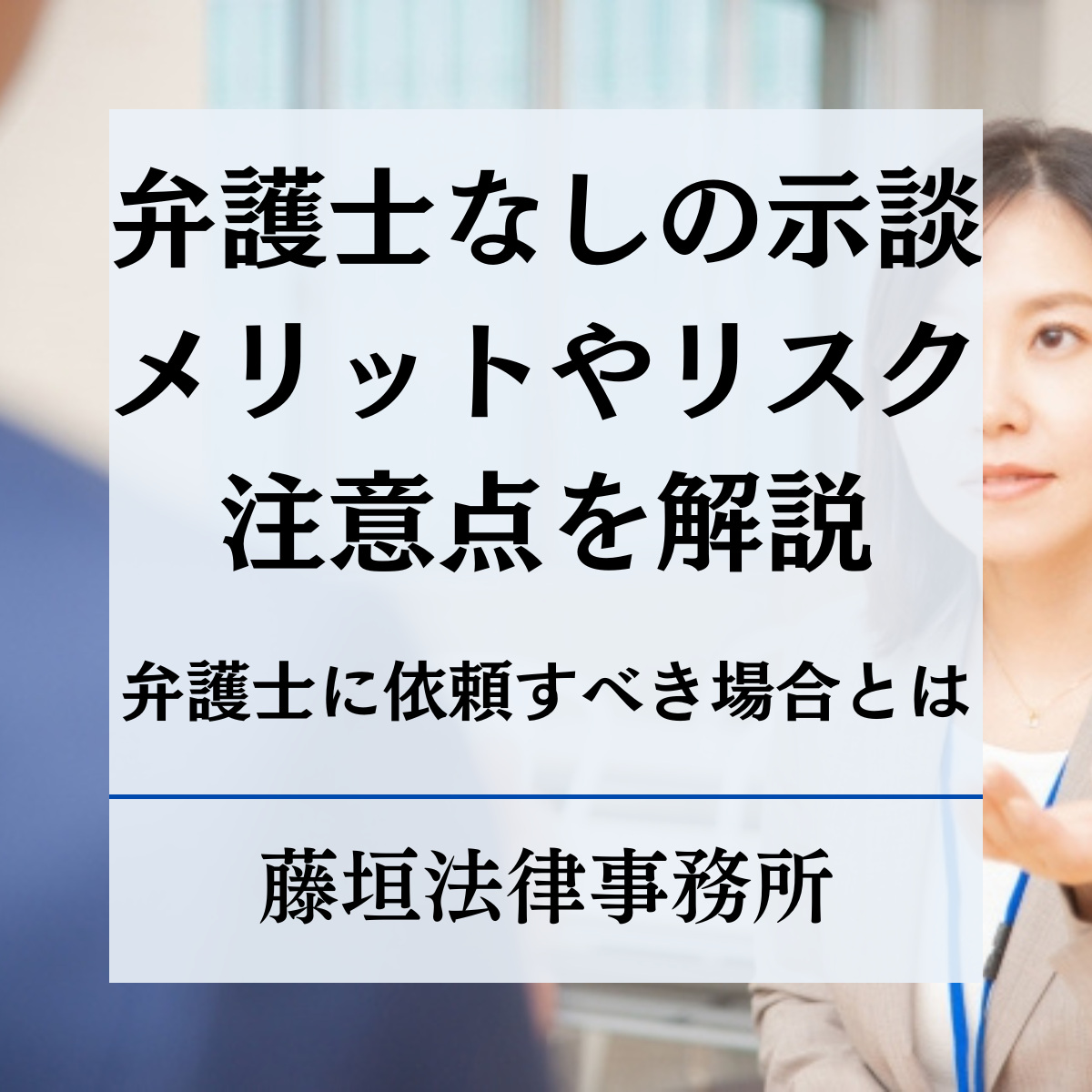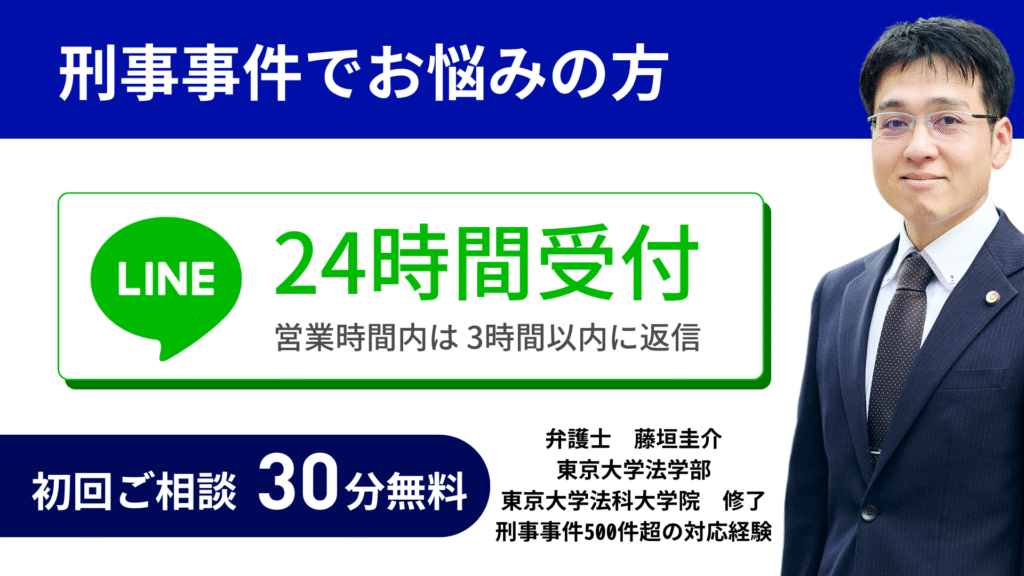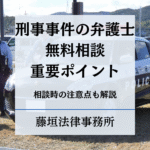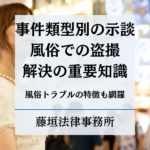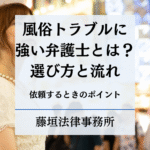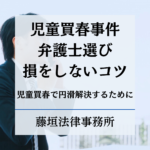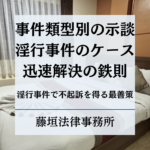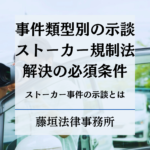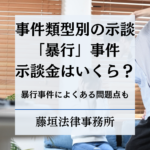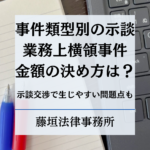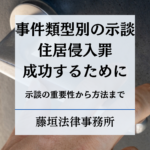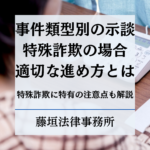刑事事件を起こしてしまった場合、被害者との示談が成立するかどうかは処分の結果を大きく左右します。「弁護士なしでも自分で示談できるのでは?」と考える方もいますが、刑事事件の示談交渉には慎重な対応が求められます。方法を誤ると、かえって被害者の心証を悪化させたり、示談が無効とされるおそれもあります。本記事では、弁護士なしで刑事事件の示談を行うことが可能か、そのメリットとリスク、さらに安全に示談を進めるためのポイントを詳しく解説します。
この記事の監修者

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
弁護士なしでも刑事事件の示談交渉は可能
示談とは,当事者間の話し合いによって合意(=契約)し,トラブルを解決することを言います。
刑事事件の場合,被害者と加害者がお互いの法律関係をどのように決着つけるか,合意することを指すのが通常です。
この刑事事件における示談では,加害者が被害者に金銭(示談金)の賠償を行うことが大多数です。
示談が成立している場合,刑事処分が劇的に軽減し,不起訴となることも数多くあります。前科を避けたい,刑罰を軽くしたい,という場合は,示談の試みが極めて重要になります。
この点、弁護士なしでも刑事事件の示談交渉は可能です。もっとも、その限界や注意点には十分な配慮することを強くお勧めします。

① 弁護士なしであっても法的な効果はある
刑事事件の示談は、弁護士が行わなければ法的な効果が生じないというわけではありません。示談の法的な意味は、民法上の和解契約と位置付けられることが一般的ですが、和解契約をするために弁護士が必要とはされていないためです。
刑事事件における示談は、和解契約の内容として「加害者を許す」という内容(宥恕=ゆうじょ)を盛り込んだものであることが通常です。そのため、宥恕を含む和解契約ができれば、弁護士がいてもいなくても法律的な効力に不足はありません。
示談書の存在も、示談の成立に必要な要件ではありません。そのため、弁護士なしで口約束をするだけでも示談は成立し、法的効果も生じます。もっとも、紛争の蒸し返しを防ぐ手段として、そして捜査機関に示談の事実を示す手段として、示談書を作成することが通常です。
② 限界が生じやすい点には注意が必要
弁護士なしでも示談交渉は法的に可能ですが、実際には多くの限界が生じます。
最も大きな問題は、被害者側が加害者本人との直接的な接触を拒否するケースが非常に多いことです。
感情的なトラブルを伴う暴行・傷害事件や、当事者間の接触が類型的に不適切な性犯罪などでは、特に直接の接触は拒否されることがほとんどでしょう。捜査機関も、当事者同士の示談交渉を促したり当事者間の連絡先交換を仲介したりすることは考え難いところです。
また、加害者が逮捕・勾留という手続で身柄拘束されてしまうと、加害者本人が被害者に直接連絡する手段はなくなってしまい、弁護士なしの示談交渉は非常に難しくなります。
加えて、弁護士のない示談では、内容面にも限界の生じやすい傾向があります。法的知識の不足により適切な示談条件を判断できず、相場よりも高額な示談金を要求されたり、不利な条件を受け入れてしまうリスクも存在します。
示談書の作成においても、記載内容や方法など、適切な文書を作成するためには法的知識が必要となるため、弁護士なしでは難しいケースが多いでしょう。
弁護士なしでの示談交渉は、これらの限界を十分に理解した上で慎重に検討する必要があります。
【弁護士なしの示談交渉における限界】
・被害者側に拒否されやすい
・身柄拘束されると交渉手段がない
・不利益な内容になる可能性
・示談書の作成が難しい可能性
弁護士なしで刑事事件の示談を行う方法

① 被害者への連絡
刑事事件で示談を進める際、まず被害者との連絡を取ることが最初のステップとなります。
被害者への連絡方法は主に以下の手段があります。
・電話による直接連絡
・書面による謝罪と示談の申し入れ
・共通の知人を介した間接的な連絡
・被害者の代理人弁護士を通じた連絡
連絡を取る際は、まず心からの謝罪の気持ちを伝えることが重要です。
その上で示談について話し合いたい旨を丁寧に伝えましょう。
ただし、被害者が連絡を拒否した場合は、無理に連絡を続けることは控える方が賢明です。
直接の連絡は、被害者が了承していることが明確である場合にのみ行うのが望ましいでしょう。被害者が直接の連絡に否定的な心理状態の場合、連絡を試みることが示談に悪影響を及ぼす恐れもあります。
② 示談条件の交渉
示談条件の交渉は、刑事事件の解決において最も重要な段階の一つです。
交渉で話し合うべき主な条件は以下の通りです。
・示談金の金額
・支払い方法(一括払いか分割払いか)
・支払い期限
・謝罪の方法
・今後の接触に関する取り決め
・宥恕条項(処罰を求めない旨の条項)の有無
交渉では感情的にならず、冷静に話し合うことが重要です。
被害者が求める条件を丁寧に聞き取ることから始め、自分が了承できる水準や内容と整合するか、すり合わせていく交渉が円滑になりやすいでしょう。
相手の要求が過度に高額な場合は、客観的な損害額を基準に適正な金額を提案する必要があります。
ただし、法的知識がないと適切な判断が困難な場合も多いため注意が必要です。
③ 示談書の作成、締結
示談を行うにあたっては、示談書の作成と締結により証明手段を確保しておくことが非常に重要となります。
示談書の記載内容に不備があると、後々トラブルの原因となる可能性があるため、記載内容、方法には注意が必要です。
特に注意すべき点は以下の通りです。
・示談金以外の請求を放棄する条項(清算条項)
・示談内容を第三者に口外しない守秘義務条項
・示談書に記載のない事項について今後一切請求しない条項
示談書の署名押印は、双方が内容を十分理解した上で行うことが大切です。
適切な示談書の作成は、将来的な紛争を防ぐ重要な役割を果たします。
示談の基本的な目的は、清算条項を設けて当事者間の法律関係を終了させる点にあります。刑事事件では、これに加えて刑罰を望まないという許し(宥恕)を含めることが一般的です。
④ 示談金の支払い
示談金の支払が生じる場合、支払い方法や時期について、事前にしっかりと取り決めておく必要があります。
一般的な支払い方法として、以下のような選択肢があります。
・一括払い
示談成立と同時に全額を支払う方法で、最も確実性が高い
・分割払い
経済的な事情により一括での支払いが困難な場合に選択される
・振込み
銀行振込による支払いで、記録が残るため証拠として有効
・現金手渡し
直接現金で支払う方法だが、受領証の作成が重要
特に分割払いの場合は、各回の支払い金額、支払い日、振込先などを詳細に記載することが適切です。
また、支払い完了後は受領証を受け取り、示談の履行が完了したことを証明できるようにすることも有益でしょう。
示談金を振込みで支払う場合、示談書の締結より支払う方が後になるため、受領する被害者にとっては不安が残りやすいものです。そのため、支払期限を明確にしたり、支払がなされなかった場合の効果を定めたりするなど、被害者側に配慮することも有力でしょう。
⑤ 捜査機関等への連絡
示談が成立した場合、その事実を適切な機関に報告することが重要です。
まず警察や検察庁など、事件を担当している捜査機関への連絡を行いましょう。
示談成立の報告は、不起訴処分や刑事手続きの軽減に直結する重要な手続きです。
捜査機関は示談の成立を知ることで、事件の処理方針を検討する材料として活用します。
報告する際は以下の書類や情報を準備しましょう。
・示談書の写し
・示談金の支払いを証明する書類(振込明細書など)
・捜査機関が連絡するための被害者側の連絡先情報
示談成立後は、極力速やかに、まずは電話連絡で報告を行うことをお勧めします。その際に、共有が必要な書面もあわせて確認するとスムーズです。
弁護士なしで示談交渉を行うメリット
弁護士なしで刑事事件の示談交渉を行うことには、いくつかのメリットが存在します。
最も大きな利点は、弁護士費用を節約できることでしょう。
弁護士に依頼する場合、着手金や成功報酬として数十万円から数百万円の費用が発生することが一般的です。
軽微な事件や経済的に余裕がない場合、この費用負担は大きな問題となります。
弁護士なしで示談交渉を進めれば、これらの費用を抑えることが可能になるのです。
また、当事者同士で直接話し合うことで、より迅速な解決が期待できる場合もあります。
弁護士を介さないため、連絡や交渉のスピードが早く、お互いの気持ちや事情を直接伝えられるでしょう。
特に知人同士のトラブルや軽微な事件では、率直な謝罪と話し合いが効果的な場合があります。
さらに、プライバシーを保護しやすいという側面もあります。
第三者である弁護士を通さずに解決することで、事件の詳細が外部に漏れるリスクを最小限に抑えられるでしょう。
メリット
・弁護費用の節約
・迅速な解決の可能性
・プライバシーの保護

弁護士なしで示談交渉を行うリスク
① 被害者に拒否される可能性が高い
刑事事件の示談交渉において、加害者本人が被害者に直接連絡を取ろうとしても、拒否される可能性が非常に高いのが現実です。
被害者にとって加害者は「自分に害を与えた相手」であり、心理的な恐怖や不安を抱いているケースがほとんどでしょう。
特に暴行事件や窃盗事件などでは、被害者が加害者との直接的な接触を避けたいと考えるのは自然な反応といえます。
被害者が示談交渉を拒否する主な理由は以下の通りです。
・加害者への恐怖心や不信感
・感情的な対立による冷静な話し合いの困難さ
・加害者本人では誠意が伝わりにくい
・法的知識不足による不安感
また、被害者側も弁護士に相談している場合、「加害者本人とは直接話さないように」とアドバイスを受けていることも多いでしょう。
一方で弁護士が代理人として交渉する場合、第三者的立場から冷静かつ専門的なアプローチが可能となります。
被害者も法的な専門家との交渉であれば、安心して話し合いに応じる傾向があります。
警察や検察の捜査を受けている場合、示談希望の意思を表明すると、捜査担当者から弁護士への依頼を促されることも多いです。
② 逮捕勾留されると示談交渉ができなくなる
逮捕勾留されてしまうと、身体の自由が奪われるため示談交渉が極めて困難になります。
警察署や拘置所に身柄を拘束された状態では、被害者との直接的な連絡や面会は基本的に不可能です。
また、勾留期間は最大20日間と限られており、その間に示談を成立させなければ起訴される可能性が高まります。
時間的な制約がある中で、本人が直接交渉を進めるのは現実的ではありません。
さらに、勾留中に無理な示談交渉を試みると、被害者に不信感を与えかねません。
家族が代理で交渉することも可能ですが、法的な知識が不足していると適切な対応が難しくなります。
逮捕勾留された場合は、示談交渉の機会を逃さないためにも早急に弁護士への依頼を検討することが重要です。
③ 不当に不利な条件を強いられる恐れがある
弁護士なしで示談交渉を進めると、法的知識の不足から不当に不利な条件を受け入れてしまう危険性があります。
被害者側は「示談金をもっと多く支払ってもらいたい」と考え、相場を大幅に上回る金額を要求してくる場合が少なくありません。
また、示談書に「今後一切の請求を行わない」という条項を入れずに、後日追加請求の余地を残すような内容を提案される恐れもあるでしょう。
さらに、示談成立後の守秘義務について過度に厳しい条件を設定されたり、被害者の精神的損害を理由に継続的な金銭支払いを求められたりするケースも存在します。
法的知識のない一般の方では、これらの条件が妥当かどうかを判断することは困難です。
「早く解決したい」という気持ちから、相手の言いなりになってしまう状況に陥りがちでしょう。
適切な示談条件を見極めるためには、類似事件の相場や法的な基準についての専門知識が不可欠といえます。
被害者側の希望する条件が不合理だと思ったとしても、現実的に当事者本人が断ることは非常に難しいものです。内容面で交渉を要する場合は、弁護士を窓口に行うことが現実的には必須でしょう。

④ 適切な示談書の作成が困難
適切な示談書作成には専門的な知識が不可欠となります。
示談書には被害の詳細、示談金額、支払い方法、清算条項、宥恕条項などの必須項目を正確に記載する必要があります。
特に清算条項は今後一切の請求をしないことを明記する重要な条項です。
宥恕条項では被害者が加害者を許し、処罰を求めない意思を表明します。
これらの条項が不適切だと、後日トラブルが再発する恐れがあります。
示談書には双方が署名押印を行うことが一般的ですが、どのように署名するか、どのような印鑑で押印するか、といった点も、示談書作成の際に要する専門的知識の一つです。署名押印にどのような効果を期待するかで、適切な方法が変わってきます。
⑤ 交渉がうまくいかないときの対処法が分からない
弁護士なしで示談交渉を進める場合、交渉が行き詰まった際の対処法を知らないことが大きなリスクとなります。
「相手が話し合いに応じてくれない…」という状況に陥った時、一般の方では適切な解決策を見つけることが困難でしょう。
被害者が感情的になって交渉を拒否したり、提示した示談金額に納得してもらえない場合、素人判断では状況を悪化させる恐れがあります。
弁護士であれば、交渉が難航した際に以下のような対処法を提案できます。
・示談条件の見直しや代替案の提示
・被害者の心情に配慮した適切なアプローチ方法の変更
・法的手続きへの移行タイミングの判断
また、示談交渉の期限が迫っている場合や、検察庁への事件送致が近づいている状況では、迅速かつ的確な判断が求められます。
経験のない方が独力で対応すると、貴重な時間を無駄にしてしまい、最終的に起訴されてしまう可能性が高まるでしょう。
専門知識と豊富な経験を持つ弁護士なら、状況に応じた最適な解決策を提示し、円滑な示談成立へと導いてくれます。
示談交渉がスムーズに進まない場合、長期的な目線で示談を試みる必要がありますが、解決を急ぎたい当事者本人には非常に難しいことです。
⑥ 示談後に紛争を蒸し返される恐れがある
弁護士なしで示談交渉を進めた場合、示談成立後に被害者から紛争を蒸し返される恐れがあります。
弁護士が関与しない示談書では、法的な記載が不完全になりがちです。
特に「清算条項」や「口外禁止条項」などの重要な条項が抜け落ちることで、後日被害者から「示談金が足りない」「追加の損害が発生した」といった主張をされる可能性が高まります。
また、示談書の文言が曖昧だと、被害者が示談の内容を異なって解釈し、新たな要求をしてくる場合もあるでしょう。
「これで終わりだと思っていたのに…」と困惑する加害者も少なくありません。
さらに、弁護士なしの示談では被害者の感情的な部分が十分に解決されず、後から不満が爆発することもあります。
被害者が示談後にSNSで事件について発信したり、職場や近隣に話を広めたりするリスクも考えられます。
専門的な知識を持つ弁護士が作成した示談書であれば、こうした後日の紛争を防ぐための条項が適切に盛り込まれ、真の解決につながりやすくなります。
示談交渉を弁護士に依頼するべき理由
① 刑事事件化を防げる可能性
弁護士に示談交渉を依頼する最大のメリットは、刑事事件化を防げる可能性が高まることです。
警察に被害届が提出される前や、捜査が本格化する前に示談が成立すれば、事件として立件されずに済む場合があります。
特に軽微な事件では、被害者との間で示談が成立していることを理由に、警察が事件として扱わない判断をするケースも少なくありません。
「このまま警察沙汰になってしまうかもしれない…」と不安に感じている方にとって、弁護士による迅速な示談交渉は非常に有効でしょう。
弁護士は法的な観点から適切な示談条件を提示し、被害者の納得を得やすい交渉を行います。
また、示談書の作成においても、将来的な紛争を防ぐための条項を盛り込むなど、専門的な配慮が可能です。
さらに、弁護士が介入することで被害者側も安心感を持ち、示談に応じやすくなる傾向があります。
早期の示談成立により刑事事件化を回避できれば、前科がつくことなく、社会生活への影響を最小限に抑えることが可能になりやすいでしょう。
刑事事件化を防ぐことができれば、即時にトラブルが解決することとなり、加害者本人にとってのメリットが極めて大きな結果となります。目指す余地のある状況であれば、可能な限り目指すことをお勧めします。
② 示談が成立しやすくなる
弁護士が示談交渉に関わることで、被害者との合意に至る可能性が大幅に向上します。
被害者側は、加害者本人からの直接的な接触に対して警戒心や恐怖感を抱くことが多いものです。
「また何かされるかもしれない…」という不安から、話し合いの場を持つこと自体を拒否するケースが非常に多いでしょう。
一方、弁護士が代理人として交渉に当たる場合、被害者の心理的負担は大きく軽減されます。
法律の専門家が間に入ることで、冷静かつ建設的な話し合いが可能となり、感情的な対立を避けながら解決策を模索できるのです。
また、弁護士は示談交渉の経験が豊富なため、被害者の心情に配慮した適切なアプローチを選択できます。
謝罪の仕方から補償内容の提示方法まで、相手が受け入れやすい形で進めることが可能です。
さらに、弁護士が関与することで示談の法的効力や内容について被害者に丁寧に説明でき、安心して合意に至れる環境を整えられます。
このような専門的なサポートにより、示談成立の確率は格段に高くなるでしょう。
③ 法的な手続が不利になることを防げる
弁護士に示談交渉を依頼することで、刑事手続きにおいて不利な状況に陥ることを防げます。
刑事事件では、捜査段階から起訴、裁判まで複雑な法的手続きが存在しており、一般の方が全てを把握するのは困難でしょう。
弁護士は刑事手続きの専門知識を持っているため、各段階で適切な対応を取ることができます。
特に重要なのは、捜査機関との対応です。
取り調べでの発言や証拠の取り扱いについて、弁護士がいることで適切なアドバイスを受けられ、不利な供述を避けることが可能になります。
また、示談成立後の手続きも重要なポイント。
示談書の内容や示談成立の事実を適切に捜査機関に伝えることで、不起訴処分や起訴猶予の可能性を高められます。
法的手続きでの失敗は取り返しがつかない結果を招く可能性があるため、専門家のサポートが不可欠といえるでしょう。
④ 示談金額や示談条件が適切にできる
弁護士に示談交渉を依頼する大きなメリットは、示談金額や示談条件を適切に設定できることです。
法的知識のない個人が示談交渉を行うと、「相場がわからず高額すぎる示談金を要求されるかもしれない…」という不安を抱えがちでしょう。
実際に、被害者側から過大な要求をされても、それが妥当かどうか判断できません。
弁護士は過去の類似事例や刑罰の見込みを基に、事件の内容に応じた適正な示談金額を算定します。
暴行事件なら治療費や慰謝料、窃盗事件なら被害額や迷惑料など、事件類型ごとの相場を熟知しているためです。
また、示談条件についても法的リスクを考慮した適切な内容を提案してくれます。
・宥恕条項(許しの意思表示)の明記
・清算条項(追加請求の禁止)の設定
・口外禁止条項の適切な範囲設定
これらの条項により、示談成立後のトラブルを未然に防げるでしょう。
弁護士の専門知識により、法的効果を最大限に活かした示談が実現できます。
⑤ 釈放や不起訴の可能性が高くなる
弁護士に示談交渉を依頼することで、釈放や不起訴処分を得られる可能性が大幅に向上します。
刑事事件では、示談の成立が処分決定に与える影響は極めて大きいものです。
検察官は起訴・不起訴を判断する際、被害者との示談成立を重要な情状として考慮するでしょう。
特に初犯や軽微な事件では、示談成立により不起訴処分となるケースが多く見られます。
弁護士が関与することで示談成立の確率が高まり、結果として以下のような効果が期待できます。
・身柄拘束中の場合は早期釈放の可能性
・在宅事件では不起訴処分の可能性向上
・起訴されても略式起訴や執行猶予付き判決の可能性
釈放や不起訴を目指すためには、刑事手続の流れや期間制限に配慮することが不可欠です。時期が遅れてしまうと、せっかく示談が成立しても釈放や不起訴に十分な効果が得られません。
刑事事件の示談交渉を依頼する弁護士の選び方
① 刑事事件や示談交渉の経験、専門性
刑事事件の示談交渉は民事訴訟とは全く異なる特殊な分野です。
被害者心理の理解、捜査機関との連携、適切なタイミングでの交渉など、専門的な知識と経験が不可欠となります。
経験豊富な弁護士なら以下の点で優れた対応が期待できます。
・事件の性質に応じた最適な示談戦略の立案
・被害者の感情に配慮した適切なアプローチ
・示談金額の相場や交渉のタイミングの判断
・検察官や警察との効果的な連携
インターネットで検索している場合は、弁護士のホームページで刑事事件の取扱実績や解決事例を確認することも有力です。
事前のリサーチを踏まえて、初回相談では具体的な対応方針を聞いてみましょう。
また、示談交渉だけでなく、その後の刑事手続きまで見据えた総合的なサポートができる弁護士を選ぶことが重要です。
専門性の高い弁護士なら、示談成立後の不起訴処分や執行猶予獲得まで含めた戦略的な対応が可能となります。
② 口コミなどの評価
弁護士選びにおいて口コミや評価は重要な判断材料となります。
しかし「評判が良いから安心できるかもしれない…」と思う一方で、情報の見極めが必要でしょう。
まず、複数の情報源から評価を収集することが大切です。
事務所ホームページ、法律相談サイト、Google口コミなど様々な媒体をチェックしましょう。
特に刑事事件や示談交渉に関する具体的な評価があるかを確認してください。
評価を見る際は以下のポイントに注目すべきです。
・刑事事件での実際の解決事例や成果
・依頼者とのコミュニケーション能力
・費用の透明性や説明の分かりやすさ
・迅速な対応や連絡の取りやすさ
ただし、極端に良い評価や悪い評価だけでなく、バランスの取れた意見を参考にすることが重要です。
また、口コミの内容が具体的で信憑性があるかも判断材料となります。
③ 説明や案内の明快さ、分かりやすさ
弁護士選びでは、説明の分かりやすさが極めて重要です。
刑事事件の示談交渉は複雑な手続きが多いため、弁護士が丁寧に説明してくれるかどうかで、依頼者側の理解度や安心感が大きく変わります。
説明や案内が明快な弁護士の場合、法律用語を使わずに現状を説明し、今後の流れを具体的に示してくれることも期待できます。
弁護士の説明力を判断する際には、以下の各点を意識することが有力です。
・法律用語を一般的な言葉に言い換えて説明する
・質問に対して具体例を交えて回答する
・手続きの流れを時系列で整理して伝える
・費用や期間について明確に提示する
・リスクやデメリットも隠さず説明する
分かりやすい説明ができる弁護士は、示談交渉でも相手方に対して適切なコミュニケーションを取れる可能性が高いと推測できます。説明の明快さを意識することで、その弁護士が適切な示談交渉をしてくれるか、という点にも自然に配慮することができるでしょう。
④ 弁護士の信頼感
示談交渉を依頼する弁護士選びにおいて、信頼感は最も重要な判断基準の一つです。
刑事事件という人生に大きく関わる問題だからこそ、「この弁護士に任せて本当に大丈夫だろうか…」と不安に感じる方も多いでしょう。
信頼できる弁護士を見極めるポイントは以下の通りです。
・初回相談時の対応が丁寧で親身になって話を聞いてくれる
・質問に対して曖昧な回答ではなく、明確で具体的な説明をしてくれる
・費用や手続きについて透明性があり、隠し事がない
・連絡が取りやすく、レスポンスが早い
・事件の見通しについて楽観的すぎず、現実的な見解を示してくれる
また、弁護士会への所属確認や懲戒処分歴の有無も重要な判断材料となります。
面談時の印象や話しやすさも大切な要素です。
信頼関係が築けない弁護士では、重要な情報を正確に伝えられず、結果的に示談交渉にも悪影響を及ぼしかねません。
その弁護士の判断であれば、仮に結果が奏功しなくても納得できるという信頼感があることは非常に重要です。刑事事件の示談においては、具体的な動き方はある程度弁護士の裁量に委ねざるを得ないためです。

示談交渉を弁護士に依頼する場合の弁護士費用
① 逮捕されていない事件(在宅事件)
逮捕されていない在宅事件では、弁護士費用は比較的抑えられる傾向にあります。
身柄拘束されていないため、弁護士との面談や打ち合わせが柔軟に行えること、身柄拘束への対応を要しないことなどが費用を抑える要因となっています。
具体的な費用の金額や内訳は以下の通りです。
・着手金:30万円から50万円程度
・成功報酬:30万円から50万円程度
・示談交渉費用:別途20万円から30万円程度
・その他に実費が発生
弁護士費用が心配で依頼を躊躇してしまう場合は、複数の弁護士事務所で見積もりを取ることも有力です。
在宅事件では時間的余裕があるため、事務所間の比較が比較的容易にできるでしょう。
② 逮捕されている事件(身柄事件)
逮捕されている身柄事件では、弁護士費用が在宅事件よりも高額になります。
具体的な費用水準は以下のとおりです。
・着手金:50万円から80万円程度
・成功報酬:50万円から80万円程度
・示談交渉費用:別途30万円程度
・その他に実費が発生
身柄事件の場合、示談交渉のみでなく刑事手続に対する全般的な対応が不可欠になります。
これらの負担が費用に反映されるため、在宅事件に比して高額になりやすい傾向にあります。
③ 示談後にトラブルが発生した場合の弁護士費用
示談後に発生するトラブルは、刑事手続外の内容であり、いわゆる民事事件であることが一般的です。
金銭の追加請求や、示談の有効性が争われるといった内容が代表的でしょう。
民事トラブルにおける弁護士費用は、交渉段階か訴訟段階かによって異なりやすいところです。
一般的な費用の水準は、以下が一例です。
【交渉段階の場合】
・着手金:20万円から30万円程度
・成功報酬:20万円~(経済的利益の大きさにより異なる)
・その他に実費等が発生
【訴訟段階の場合】
・着手金:40万円から60万円程度
・成功報酬:40万円~(経済的利益の大きさにより異なる)
・その他に実費等が発生
示談後のトラブルは、経緯や内容が様々であり、適切な方針は個別に検討することが適切です。そのため、まずは一度法律相談を行い、取るべき対応や方針を決定していくことが望ましいでしょう。
刑事事件の示談に強い弁護士をお探しの方へ
被害者のいる事件では,示談ができるかできないかで処分が決まると言ってよいケースが少なくありません。
そのため,示談は,刑事処罰がどうなるか,前科が付いてしまうかを左右する非常に重要なものです。
しかし,示談の試み方を誤ってしまうと,示談が成立せず,取り返しのつかない不利益が生じかねません。
刑事事件で前科を防ぐためには,示談に強い弁護士への依頼が欠かせません。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
刑事事件は少しでも早い対応が大事になりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
特設サイト:藤垣法律事務所