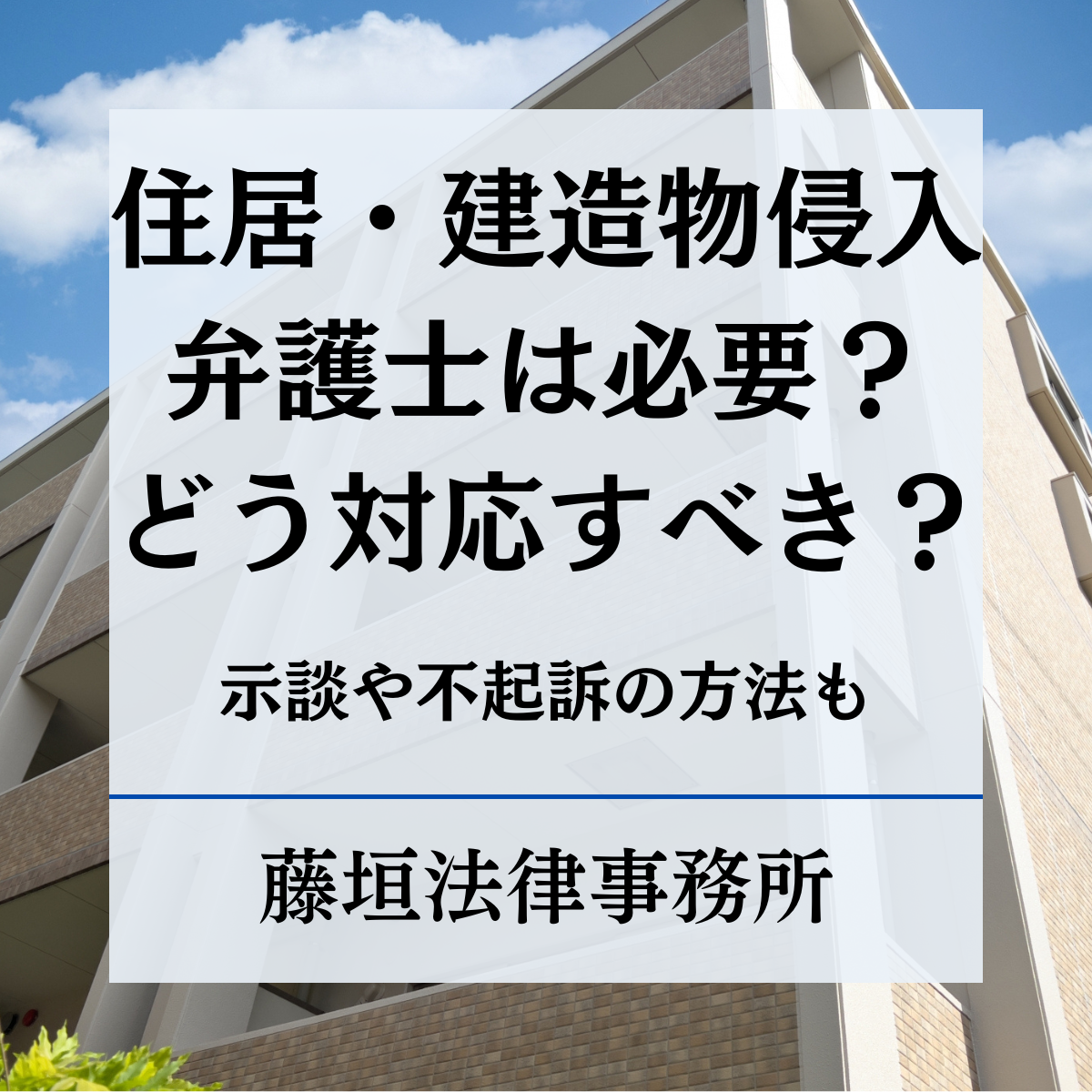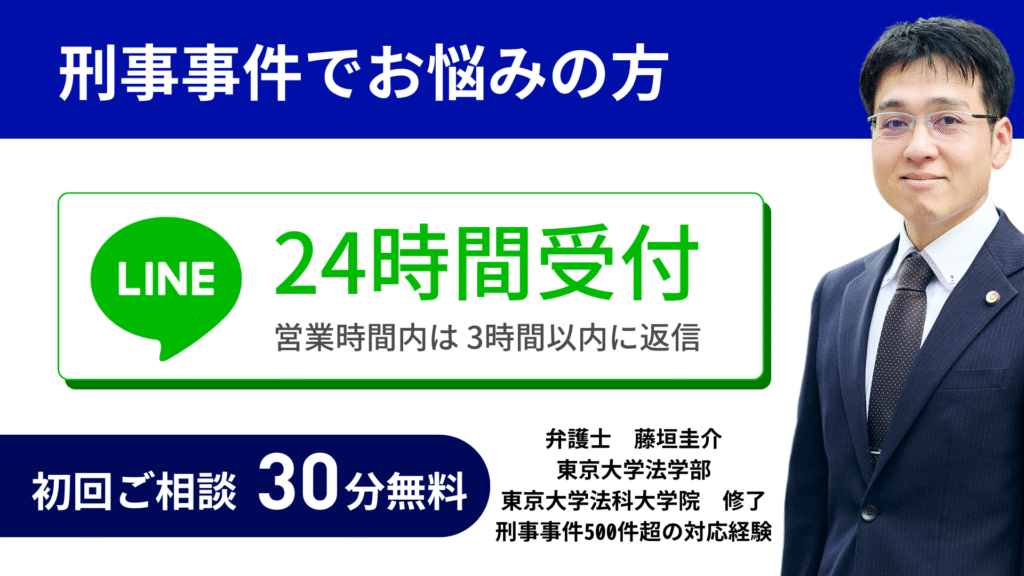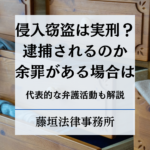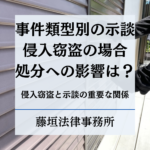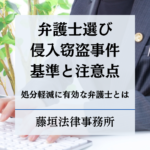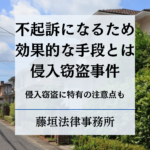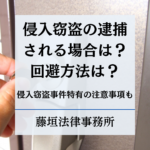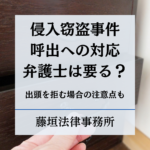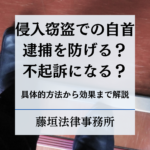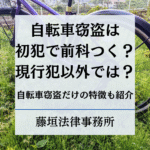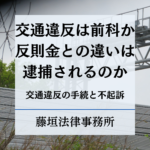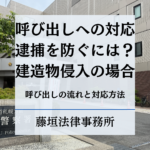「不法侵入って現行犯じゃないと逮捕されないの?」
「後から侵入がバレた場合でも罪に問われるの?」
上記のようなことを感じている方もいるのではないでしょうか。
不法侵入は現行犯でなくても、状況次第では後日逮捕や書類送検される可能性があります。警察が証拠を集め、住居侵入罪として立件できれば法的措置が取られることもあるのです。
本記事では、不法侵入の正しい定義や、現行犯でなくても処罰対象となる具体的なケース、後から逮捕されるまでの流れについて、わかりやすく解説していきます。
この記事の監修者

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
不法侵入とは
不法侵入とは、他人の敷地や建物などに無断で立ち入る行為です。刑法上では「住居侵入罪」として規定されています。
刑法130条では、「正当な理由なく人の住居、建造物若しくは艦船に侵入した者」は、三年以下の懲役または十万円以下の罰金に処せられるとされています。
つまり、単に「入っただけ」であっても、相手の承諾がなければ罪に問われる可能性があるのです。
住居侵入罪が成立する要件
住居侵入罪が成立するためには、まず「他人が占有する住居等であること」が前提です。
ここでいう「住居」には、人が居住している住宅だけでなく、事務所や店舗、場合によっては空き家も含まれます。
次に、「正当な理由がなく侵入したこと」が必要です。
たとえば、郵便配達員や修理業者など、社会的に認められた職務で立ち入る場合は正当な理由があるとされますが、それ以外で黙って入れば違法です。
また、「侵入の意思」が問われるため、間違って入っただけでは故意がないとみなされ、罪に問われないこともあります。
ただし、立ち入りの意図や態度から、明らかに不法だと判断されれば処罰の対象です。これらの要件がそろったときに、住居侵入罪として成立します。
住居侵入罪として問題になる行為には例として以下のようなものが挙げられるので、ぜひ参考にしてください。
住居侵入罪に該当する行為
①窃盗目的で住宅に侵入する行為
いわゆる空き巣などが該当します。窃盗行為が行われた場合,あわせて窃盗罪又は窃盗未遂罪が成立します。
もっとも,窃盗行為を実行せずに立ち去ったとしても,住居侵入罪は変わらず成立します。
②わいせつ行為目的で帰路の後をつけ,住宅に侵入する行為
路上で目撃した被害者へのわいせつ行為を企図した人が,その場ではわいせつ行為を行わず,自宅に入る被害者の後をつけて住宅に侵入した場合です。
わいせつ行為がなされた場合,内容等に応じて不同意わいせつ罪などの性犯罪が別途成立します。また,わいせつ行為がなされなかった場合でも住居侵入罪は変わらず成立します。
③知人の自宅の合鍵を作り,それを用いて居宅に侵入する行為
加害者と被害者が勤務先の同僚等の関係にある場合に,加害者が被害者の所持品から鍵を持ち出して合鍵を作製し,その合鍵を用いて被害者方に侵入するケースです。
合鍵を持ち出した段階で,その行為について窃盗罪の成立することが一般的です。
④更衣室や浴室を覗く目的で住宅の敷地内に侵入する行為
庭などの敷地から,住宅の更衣室や浴室を覗くことができる状況にある場合,その敷地に入る行為は住居侵入罪に該当するのが通常です。
住居侵入罪は,住居のみでなく,その住居に付属して一体となった場所に侵入する行為も対象とするものと理解されます。そのため,庭や駐車場,塀と玄関の間のスペースなど,住居に付属した私有地への侵入行為は,住居侵入罪に該当するところです。
なお,覗き行為が行われた場合,軽犯罪法違反などの犯罪があわせて成立するでしょう。
⑤下着窃盗のためベランダに侵入する行為
ベランダに洗濯物が干してある場合に,これを盗むためベランダに立ち入ったり手を伸ばしたりする行為にも住居侵入罪が成立します。
ベランダも,居室そのものではありませんが住居の一部に含まれるとの理解が一般的です。そのため,正当な理由なくベランダに侵入すれば,住居侵入罪の対象となります。
住居侵入と建造物侵入の区別
住居侵入罪と類似する犯罪に,建造物侵入罪があります。建造物侵入罪は,文字通り建造物に正当な理由なく侵入する犯罪です。
ここで,建造物とは,人が出入りする構造物のうち,住居以外の建物を指すのが通常です。そのため,住居侵入罪は人が日常的に生活する場所への侵入を,建造物侵入罪は住居でないが人が出入りする建物への侵入を,それぞれ対象としていると言えるでしょう。
建造物の具体例としては,商業施設やオフィスビル,学校,工場,倉庫などが挙げられます。
なお,住居侵入罪と建造物侵入罪は,守ろうとする権利や利益(保護法益)にも相違があるとされます。
具体的には以下の通りです。
| 住居侵入罪 | 個人の生活の平穏 プライバシーの保護 |
| 建造物侵入罪 | 建物の安全性 公共の秩序の保護 |
不法侵入は現行犯逮捕以外で逮捕される?
不法侵入は、現行犯で逮捕されるケースが多いですが、実は後日逮捕されることもあります。
防犯カメラの映像や目撃証言などによって、後日特定された場合、警察が逮捕状を取って身柄を拘束することが可能です。
後日逮捕される可能性
現行犯でその場で逮捕されなかったからといって、不法侵入が無罪になるわけではありません。警察は証拠や情報をもとに、後から侵入者を特定し、逮捕できます。
たとえば、防犯カメラの映像や近隣住民の証言、侵入者が残した指紋などが重要な手がかりになります。
現行犯逮捕が優先されるのは証拠隠滅や逃走を防ぐためであり、後日逮捕も法的には十分可能です。
特に悪質なケースや、再犯の恐れがある場合は、警察も積極的に後日逮捕を検討します。現行犯でないからと安心するのは危険です。
不法侵入の事件では、後日逮捕される場合も十分にあり得ます。5割程度は逮捕される印象です。侵入後に別の犯罪行為をしてしまっている場合、特に後日逮捕の可能性が上がりやすいでしょう。
後日逮捕されるには証拠が必要
後日逮捕の場合には、現行犯逮捕以上に「確実な証拠」が求められます。裁判所に逮捕状を請求するには、「罪を犯した相当な理由」があると警察が立証しなければなりません。
たとえば、防犯カメラの映像に顔が鮮明に映っていたり、住人の証言と侵入時の服装や特徴が一致していたりすれば、証拠として採用されやすくなります。
また、物的証拠として指紋や足跡、遺留品が見つかった場合も後日逮捕の根拠になります。
逆に証拠が曖昧だったり、特定できなかったりすると、逮捕に至らないこともあります。つまり、証拠の有無が後日逮捕の可否を大きく左右するのです。
後日逮捕されるまでにかかる期間
後日逮捕までの期間は、事件の内容や証拠の集まり具合によって異なります。早ければ数日以内に逮捕されることもあれば、数週間から数ヶ月かかることもあるでしょう。
警察はまず、関係者からの聞き取りや現場の捜査、証拠の分析を進めます。そのうえで逮捕に足る証拠がそろったと判断されれば、検察と連携して逮捕状を請求し、執行に移ります。
場合によっては、「在宅捜査」として任意で呼び出しを受け、取り調べの末に書類送検されるケースもあります。
逮捕までの期間は見えにくいものですが、「もう大丈夫だろう」と油断するのは禁物です。
不法侵入が発覚するまでの期間、その後に加害者が特定されるまでの期間によって異なりますが、3~6か月程度の期間がかかることは決して珍しくないでしょう。
不法侵入で後日逮捕された際の流れ
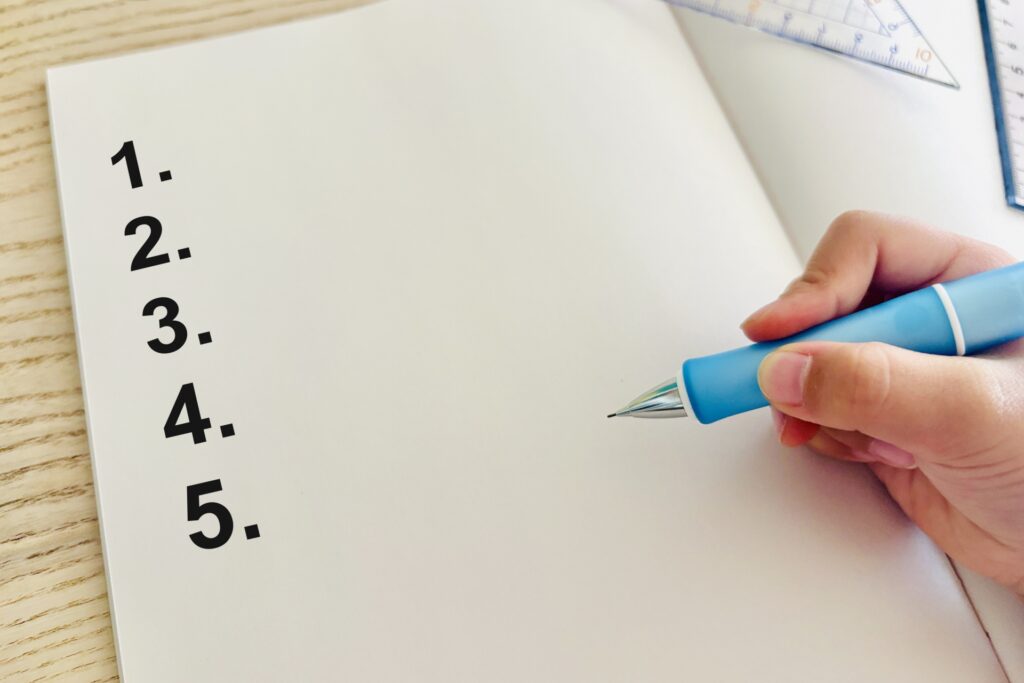
不法侵入で後日逮捕された場合、まず警察は逮捕状を取得して本人を拘束します。逮捕後は警察署に連行され、48時間以内に検察に送致されます。
検察はさらに24時間以内に勾留の要否を判断し、必要があれば裁判所に勾留請求を行います。
勾留が認められれば最大10日間(延長含め最大20日間)拘束され、その間に取り調べや証拠収集が行われます。勾留後、検察は起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴された場合は刑事裁判へと進み、有罪となれば罰金刑や懲役刑が科される可能性があります。
このように、後日逮捕であっても法的手続きは厳格に進められるため、油断は禁物です。
不法侵入で後日逮捕されるのを防ぐために必要なこと
不法侵入をしてしまったが、現時点で逮捕されていない場合、今後の対応によっては処分が軽くなる可能性もあります。
この章では、逮捕を避けたり、刑を軽くしたりするために取れる行動について解説します。
自首する
自ら警察に出頭して罪を認める行為、つまり自首は、刑法上も情状酌量の対象です。
自首には「発覚前」と「発覚後」の区別がありますが、事件がまだ警察に知られていない段階での自首であれば、刑の減免の可能性が高くなります。
発覚後でも、自ら進んで警察に説明し、協力的な姿勢を示すことで、裁判官や検察官の心証を良くし、処分が軽くなるケースがあります。
自首には精神的なハードルがあるものの、逃げ続けるよりも早期の決断が重要です。
示談を交渉する
被害者との間で示談を成立させることも、刑事処分に大きな影響を及ぼします。
住居侵入罪のような被害者が明確な事件では、示談が成立している場合、検察が不起訴にすることもあるでしょう。
示談では謝罪と損害賠償が一般的ですが、内容によっては訴えを取り下げてもらえることもあります。
ただし、無理に示談を進めようとしたり、相手の同意なしに接触したりすると、逆効果になる場合もあるため、弁護士を通じて慎重に交渉することが大切です。
示談は、処分を軽くするための現実的な選択肢の1つです。
住居侵入・建造物侵入事件で弁護士に依頼するメリット
依頼を検討するべきケース
弁護士への依頼を検討すべき場合には,以下のようなケースが挙げられます。
①逮捕の回避を目指す場合
まだ捜査されていないが,今後の逮捕が懸念されるという場合,弁護士に依頼の上で自首を行うことが非常に有力です。
自首を行うと,自ら犯罪捜査のきっかけを作ることにはなりますが,自分から出頭している以上,逮捕が必要だと判断される可能性は大きく低下するのが通常です。
放置していては逮捕が危ぶまれるという状況では,自首による逮捕回避を検討するのが適切でしょう。
もっとも,その手順や方法を誤ると,せっかく自首をしても望んだ効果が得られない可能性も高くなってしまいます。自首を検討する場合は,弁護士との同行など,弁護士への依頼をお勧めいたします。
②早期釈放を目指す場合
逮捕されたケースで早期釈放を目指す場合も,弁護士への依頼が適切と言えます。
住居侵入(建造物侵入)事件では,内容により早期釈放が実現できるかどうかの見込みが大きく異なりやすく,正確な見込みに沿った弁護活動が必要です。現実的に成功する可能性がない方法を取った場合,かえって捜査の長期化を招き,釈放時期を遅らせることにもなりかねません。
釈放を目指す場合,弁護士へ依頼の上,具体的な見込みと釈放に向けた弁護活動の案内を受けることをお勧めいたします。
③刑罰の軽減を目指す場合
刑罰の軽減を目指すためには,被害者との示談が必要不可欠です。
もっとも,当事者間での示談交渉は困難であるため,示談を試みる場合には弁護士への委任が必須となります。
示談に強い弁護士に依頼の上,弁護士を通じて示談交渉を試みることで,刑罰の軽減が実現しやすくなるでしょう。
④接見禁止処分のある場合
証拠隠滅などを防ぐため,弁護士以外との面会を禁じられることがあります。これを「接見禁止」処分と言います。
接見禁止の場合,弁護士しか被疑者の方と会えず,捜査への適切な対応は困難になります。弁護士に委任の上,弁護士とご本人との接見を実施し,早期に適切な対応方針を立てるのが適切でしょう。
⑤否認事件の場合
否認事件では,犯罪事実の立証ができるか,という点が最大の問題になりますが,その判断は非常に専門的な内容となり,弁護士への依頼なく検察と協議をすることは困難です。
事件の内容や否認のポイント,争点の判断基準などについて,弁護士に相談・依頼の上,法的に適切な主張を行うことで,不起訴処分を引き出すことが可能になり得るでしょう。
住居侵入・建造物侵入の刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
住居侵入・建造物侵入の事件は,個別の内容によってその後の流れや処分の見通しに幅の生じやすい事件類型です。正しい見通しを持つことができれば,できる限り有益な結果に向けて最善の対応を尽くすことが可能になります。
一方で,見通しを誤り,有効とは言えない対応に終始した場合,取り返しのつかない不利益が生じる可能性も否定できません。
そのため,個別の内容を踏まえて刑事事件に強い弁護士の意見をお聞きになることをお勧めします。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
特設サイト:藤垣法律事務所