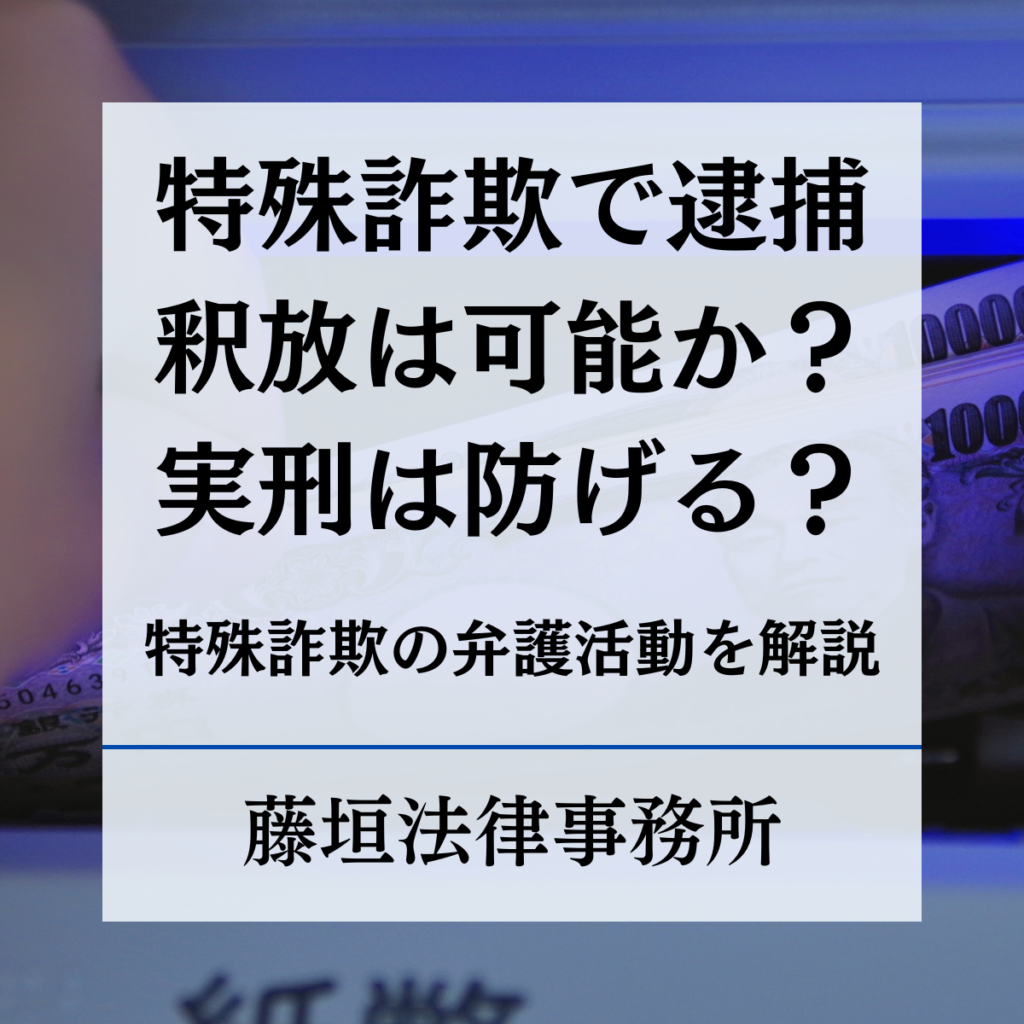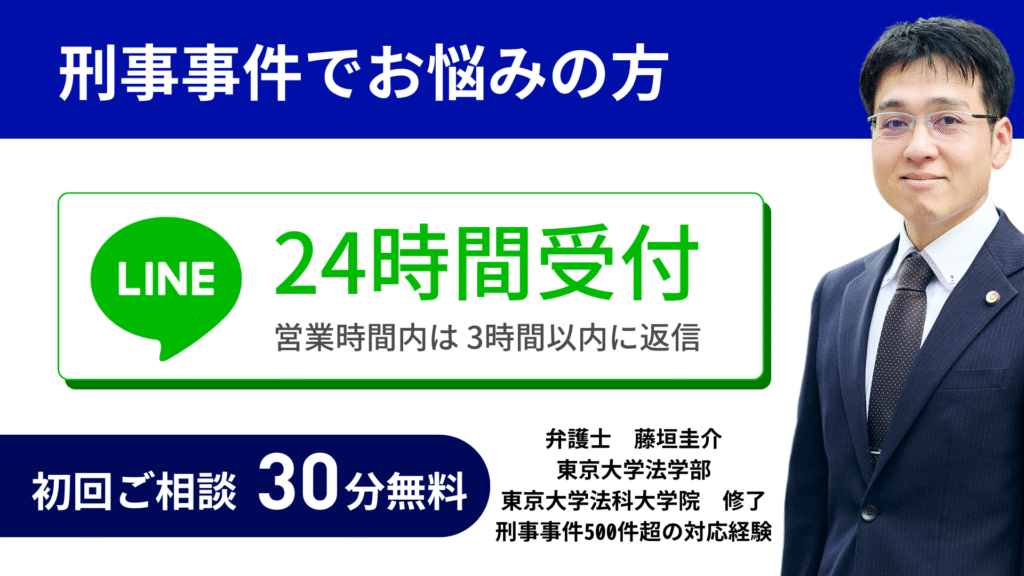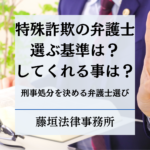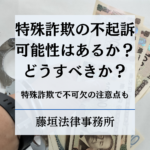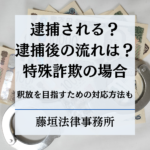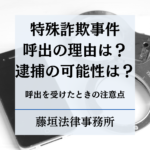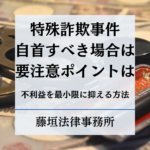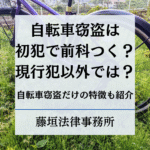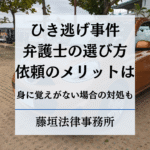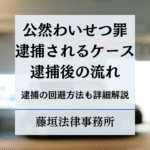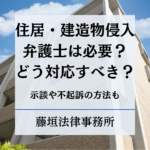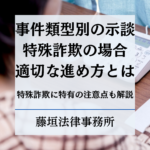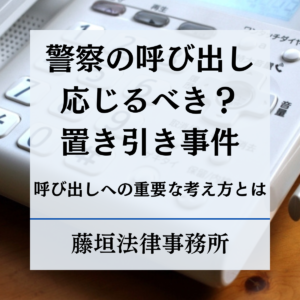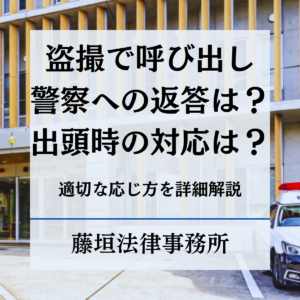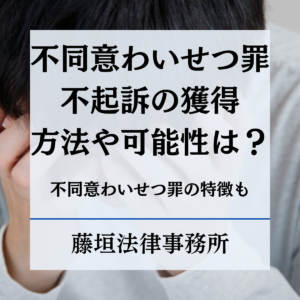「家族が特殊詐欺に関わってしまったかもしれない…どうすればいい?」
「もしかして自分がやっていることって特殊詐欺かもしれない…」
そんな不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。
特殊詐欺のトラブルは、早い段階で弁護士に相談することが何よりも重要です。
弁護士が介入することで、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まり、被害者の場合も返金交渉や損害賠償請求をスムーズに進められます。
本記事では、特殊詐欺の種類を踏まえた上で、関与してしまった場合の対応や弁護士に相談する際のポイントなどを詳しく解説します。
この記事の監修者

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
特殊詐欺とは
特殊詐欺とは,電話やインターネットを利用して他人を騙し,金銭を詐取する詐欺の総称です。具体的な手口としては,オレオレ詐欺,振り込め詐欺,還付金詐欺などが含まれます。これらの詐欺は,高度に計画されたものであり,しばしば組織的に行われます。
特殊詐欺の主な種類と内容は,以下の通りです。
| オレオレ詐欺 | 犯人が被害者に電話をかけ、自分を家族(息子、孫など)と偽り、事故や借金のトラブルを装って金銭を要求します。 |
| 振り込め詐欺 | 犯人が公的機関や金融機関の職員を装い、被害者に架空の未払い金や架空の投資話を持ちかけ、金銭を振り込ませる手口です。 |
| 還付金詐欺 | 犯人が市役所や税務署の職員を装い、還付金があると偽って被害者にATMで操作を指示し、逆に犯人の口座に金銭を振り込ませます。 |
| 架空請求詐欺 | 犯人が電話やメールで架空の請求書や督促状を送り、未払い料金の支払いを要求します。 |
| 金融商品詐欺 | 犯人が高利回りの投資話や安全な投資商品を持ちかけ、被害者から金銭を集めますが、実際にはそのような商品や投資先は存在しません。 |
特殊詐欺の用語や基礎知識
①受け子
受け子とは、特殊詐欺の一環として、詐欺グループの指示を受けて被害者から現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う人物を指します。受け子は詐欺行為の現場に直接関与し、金銭を詐取するための重要な役割を果たします。
受け子になる人々は、報酬を得ることを目的に参加することが多いです。特に学生や失業者、借金を抱えた人々が狙われやすいです。
また,そのきっかけとしては,インターネットの求人広告やSNS、掲示板などで「簡単に稼げる仕事」などの甘い言葉で勧誘されることが多いです。受け子になる人々は、最初は仕事の詳細を知らされず、実際の詐欺行為に関与する段階でその違法性に気づくことが多いです。
②出し子
出し子とは、特殊詐欺において詐欺グループの指示を受け、被害者から詐取した現金を銀行口座から引き出す役割を担う人物を指します。出し子は詐欺の後半のプロセスに関与し、詐取した資金を実際に現金化する重要な役割を果たします。
出し子になる人の特徴や出し子になる経緯は,受け子とほぼ同様です。すなわち,経済的に困窮した人が,SNSなどで簡単に稼げる仕事として見つけ,仕事をするうちに犯罪行為に巻き込まれていくケースが非常に多く見られます。
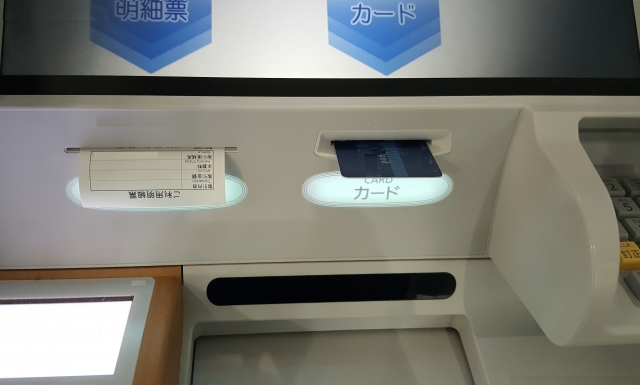
③飛ばし
特殊詐欺における「飛ばし」とは、詐欺グループが自分たちの追跡を困難にするために使用する手法の一つで、携帯電話や銀行口座などの名義を他人名義(第三者名義)にすることをいいます。犯人をたどるきっかけになりやすい物的証拠を他人名義にすることで,警察や被害者からの追跡を避けることを目的としています。
飛ばしの例としては,携帯電話や銀行口座,キャッシュカードなどが挙げられます。
携帯電話の飛ばし
他人名義の携帯電話を使用して詐欺の連絡を行います。
偽名や他人の個人情報を使って契約された携帯電話を利用するため、追跡が難しくなります。
これにより、詐欺の発覚時に実際の詐欺師の身元が特定されにくくなります。
銀行口座の飛ばし
他人名義の銀行口座を使って被害者から金銭を振り込ませます。
このような口座は「口座売買」によって取得されることが多く、不正に他人の情報を使って開設されたものが多いです。
被害者が金銭を振り込んでも、実際の詐欺グループの身元にたどり着くのが難しくなります。
クレジットカードの飛ばし
他人名義のクレジットカードを使用して、詐欺に関連する支払いを行います。
④キャッシュカードすり替え詐欺(窃盗)
近年急増した事件類型に,「キャッシュカードすり替え詐欺」があります。これは、被害者のキャッシュカードを巧妙にすり替え、被害者の銀行口座から不正に現金を引き出す手口です。この詐欺は、詐欺師が被害者の信頼を得て、キャッシュカードとその暗証番号を入手するために様々な手段を用いるため、特に高齢者を狙うケースが多く見られます。
手口の一例としては,以下のような流れで行われます。
| 接触と信頼獲得 | 金融機関の職員や警察官を装い、電話や直接訪問で被害者に接触します。「カードが不正に使用されている」などの理由を告げ、信頼を得ます。 |
| 暗証番号の取得 | キャッシュカードの確認などと称して,キャッシュカードと暗証番号のメモを一緒に封筒に入れるよう指示することなどが多く見られます。 |
| すり替え | キャッシュカードを一度被害者の見えないところに持ち出し,あらかじめ用意した他のカード(ショッピング施設のポイントカードなど)とすり替えます。被害者には封筒をそのまま返却したように装い,さらに安全のため決して封筒を開けないように,などと告げることで,すり替えの発覚を防ぎます。 |
| 不正引き出し | 本物のキャッシュカードと暗証番号を入手した後、すぐにATMや銀行窓口で被害者の口座から現金を引き出します。 |
なお,この類型は,被害者側が騙されてキャッシュカードを譲渡したわけでなく,返却を前提にただ預けただけなので,法的には詐欺罪ではなく窃盗罪と分類されることも一つの特徴です。
ポイント
特殊詐欺は,受け子や出し子といった人物に実動させ,飛ばしの携帯電話や口座を用いることで犯人特定を防ごうとする
キャッシュカードすり替えの手口にも注意。法的には詐欺罪でなく窃盗罪となる。
特殊詐欺の逮捕・勾留
特殊詐欺の事件で捜査の対象となる場合,逮捕されることが非常に多く見られます。
逮捕するかどうかは,逃亡の恐れと証拠隠滅の恐れを基準に判断しますが,特殊詐欺の場合にはいずれの恐れも大きいと考えられるためです。
特殊詐欺の場合,犯罪そのものが重大な内容であるため,重い刑罰を逃れる目的で逃亡する可能性が強く懸念されます。また,詐欺行為によって経済的利益を受けている可能性や関係者に身元の不安定な者が多い可能性を考慮すると,逃亡が比較的容易な立場にある可能性もうかがわれます。
加えて,事件の性質上,複数名の関与がほぼ確実に存在するため,共犯者間の口裏合わせや証拠隠滅(連絡内容・物証等)がなされやすく,証拠隠滅を防ぐためにも逮捕が必要と判断されやすいです。
逮捕された後は,引き続いて勾留もなされることが一般的です。
逮捕時のみならず,捜査中は常に逃亡や証拠隠滅の恐れが大きい状況にあるため,逮捕だけをして勾留せず釈放するというのは,かなり少数ということができるでしょう。
また,勾留の際には,接見禁止の対象となることも多いです。接見禁止とは,勾留中,弁護士以外との面会を禁止する内容の処分をいいます。共犯者間での証拠隠滅を防ぐ目的で,勾留の決定に際して行われることがあります。
特殊詐欺事件の場合,被疑者となった人は逮捕及び勾留が非常になされやすい立場にあると考えるのが適切でしょう。
特殊詐欺の刑罰
特殊詐欺で起訴された場合の刑罰は,実刑判決となることが少なくありません。
組織の中では末端とされる受け子や出し子といった立場であっても,事件の内容や規模,件数などによっては初犯で実刑判決の対象となることも決して珍しくはないでしょう。
そのため,特殊詐欺の事件では,実刑判決を回避するための試みをどうするか,十分に検討されることをお勧めします。
具体的には弁護士へのご相談やご依頼が適切ですが,一般論としては,やはり経済的な被害の補填をすることが最も重要な動きであると言って差し支えないところです。
特殊詐欺の事件は,詐欺罪等のいわゆる財産犯(財産を対象とした犯罪)であるため,財産の被害に対して刑罰が科されることになります。そのとき,財産への被害が埋め合わせられていれば,刑罰の判断基準となる被害の大きさも減少していることになり,刑罰は軽減するのが通常です。
特殊詐欺で起訴されるケースにおいては,被害の一部であったとしても,できる限りの金銭賠償を行い,被害者の財産的な損害を補填することが非常に重要となります。
ポイント
特殊詐欺事件は,犯罪事実が明らかであれば起訴されるのが通常
示談ができれば不起訴が見込まれるが,起訴前に全件の示談を行うのは非常に困難
刑罰は実刑判決も十分に考えられる。軽減のためには被害弁償を行うのが適切
特殊詐欺に関与してしまった場合の対応
特殊詐欺の場合,高額なアルバイトと称して募集するところに応募し,実際に働いてみたら詐欺事件だった,ということが少なくありません。受け子など末端の関係者だと,最初は詐欺だと知らなかったというケースの方が多いかもしれません。
そのため,万一特殊詐欺事件に関与してしまった場合の対応を整理しておくことは有用でしょう。
①直ちに関与をやめる
特殊詐欺の事件は,関与した件数が増えることによって,勾留期間が長く,最終的な処罰が重くなりやすいものです。そのため,直ちに詐欺行為への関与をやめ,自ら傷口を広げないようにしましょう。
②警察への連絡・出頭を試みる
被害者が警察に相談をするより前に,自ら警察に出頭し,自首を行うことで,逮捕の可能性は大きく下がります。また,事件への関与がさほどでもなければ,自首を踏まえて不起訴処分の対象となることも考えられます。
そのため,自身が詐欺事件に関与したと思われる場合には,できるだけ早く警察への連絡や出頭を試みるようにしましょう。
③被害弁償を試みる
自ら被害者に金銭賠償を申し入れることは,処分の軽減を目指すため非常に有力です。
この場合,決して被害全額が賠償できる必要はありません。被害者としても,自ら支払いを申し入れた人がいて,その人が組織の末端の立場でしかないことが分かれば,全額の賠償がなくてもその人だけを許すことは十分に考えられます。
特殊詐欺の共犯の種類
特殊詐欺の共犯には、主に以下3つの種類があります。
- 共同正犯
- 共謀共同正犯
- 幇助犯
詳しく解説します。
共同正犯
共同正犯とは、複数人が協力して同じ犯罪を実行した場合に適用される共犯形態です。
刑法第60条では「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と定められています。
つまり、誰が実際に手を下したかにかかわらず、犯行全体に関与した者全員が正犯と同等の刑事責任を負うことになるのです。
特殊詐欺の場合、電話をかけてだます役、現金を受け取る役、口座を管理する役などがそれぞれの役割を果たしていても、組織全体で1つの犯罪を実行したとみなされれば、全員が共同正犯とされます。
共謀共同正犯
共謀共同正犯とは、実際に犯罪行為を行わなくても、他者と「犯行の意思を共有し、実行を合意した」段階で成立する共犯形態です。
刑法上の明文規定はありませんが、判例によって確立された概念で、特殊詐欺事件では非常に多く適用されています。
たとえば、自分は現場にいなくても、仲間内のグループチャットや口頭で「こうやってだまそう」と話し合い、その内容を了承した場合、すでに共謀共同正犯として責任を問われる可能性があります。
特殊詐欺においては、上位の指示役やリクルーターが実行グループに犯行を指示しただけでも、共謀共同正犯に該当するケースが少なくありません。
実際に被害者と接触していない人物でも、犯罪計画を共有していれば同等の責任を負うため、共謀の有無が捜査や裁判の大きな争点となります。
幇助犯
幇助犯とは、犯罪の実行を手助けした場合に成立する共犯です。刑法第62条に「正犯を幇助した者は従犯とする」と規定されています。
幇助とは、直接的に実行行為を行わなくても、犯行が容易になるよう支援した行為です。
特殊詐欺事件では、犯罪に使う口座を提供したり、被害者をだますための電話をかける道具を貸したりする行為が幇助に該当する可能性があります。
つまり、「自分はだますつもりがなかった」「お金をもらっただけ」といった場合でも、結果的に詐欺の実行を助けたと認定されれば、刑事責任を負うことになるのです。
特殊詐欺で弁護士に依頼するときのポイント

特殊詐欺事件で弁護士を選ぶタイミング
①逮捕されたとき
特殊詐欺事件は,逮捕される可能性の非常に高い事件類型です。その理由としては,事件が重大で悪質と評価されやすいこと,組織的犯罪のため,共犯者間での証拠隠滅がなされやすいことなどが挙げられます。
基本的に,特殊詐欺事件に関わる犯罪行為があったとみなされた場合,逮捕を想定する方が望ましいと言ってもよいでしょう。
もっとも,逮捕は被疑者に対する捜査の初期段階です。逮捕後,取り調べなどの捜査を尽くすことで,被疑者の処分を判断する材料を獲得していくことになります。被疑者の立場としては,逮捕後の対応によって,その後の処分が大きく変わりやすいということでもあります。
そのため,特殊詐欺事件では,逮捕を想定した上で,逮捕されたときにはその後の捜査への対応のために弁護士選びを適切に行いたいところです。円滑な弁護士選びができれば,その後の流れが大きく変わりやすいでしょう。
ポイント
特殊詐欺事件は逮捕の可能性が高い事件類型
逮捕後の対応によって,最終的な処分が変わりやすい
②起訴されたとき
重大事件である特殊詐欺事件では,犯罪事実が明らかであれば起訴することが通常です。反省を深めているという理由で不起訴になることは,基本的にはないでしょう。
そのため,特殊詐欺事件の捜査を受けている場合には,否認事件でない限り,起訴されることを想定し,起訴後の方針も考えておくことが不可欠です。
この点,起訴された際には,保釈を請求したり,刑事裁判(公判)の対応方針を検討したりする必要がありますが,これらは弁護士なしでは困難な動きです。逆に,適切な弁護士に依頼できていれば,速やかな保釈の手続で釈放してもらうことができ,その後の公判でも不利益を最小限に抑えるような対応を取ることができるでしょう。
特に,特殊詐欺事件の場合,初犯でも実刑判決となることが決して珍しくないため,事件の重大性を踏まえると,公判でどのような対応ができるかは非常に重要な問題と言えます。
特殊詐欺事件で起訴された場合には,その後の動きを円滑で適切なものとするため,弁護士選びを十分に行うべきでしょう。
ポイント
特殊詐欺事件は,その重大性のため起訴されやすい
公判での対応次第で,実刑判決の回避も可能になり得る
③示談したいとき
特殊詐欺事件では,詐欺被害者の意向が刑事処分に大きく反映されやすい傾向にあります。被害者が起訴を望まなければ不起訴処分に,被害者が実刑判決を望まなければ執行猶予判決に,というように,被害者が重い処分を希望しない場合には,相応に軽微な処分が期待できる可能性も高くなります。
そのため,被害者と示談を行い,被害者から許しを得ることは,非常に優先順位の高い試みと言えるでしょう。
もっとも,示談の試みは弁護士に依頼する形で行うほかないのが実情です。通常,当事者間に連絡を取り合う手段がないため,捜査機関を通じて被害者に連絡を取ってもらうことになりますが,捜査機関が被害者に連絡を入れてくれるのは,弁護士が窓口に入っている場合に限られます。当事者同士の直接の連絡は,トラブルの原因になりやすいため認めてもらえないのです。
そのため,特殊詐欺事件で示談をしたい場合には,示談の試みに適した弁護士選びを行い,弁護士を通じて進めるのが適切でしょう。
ポイント
詐欺被害者の意向が刑事処分に大きく反映されやすい
特殊詐欺事件の示談は,弁護士が窓口に入ることが必要
④自首したいとき
自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。自首の大きなメリットは,逮捕を回避しやすくなることや刑事処分が軽減されやすいことですが,特殊詐欺事件の場合,逮捕の恐れが大きく,実刑判決等の思い処分も懸念されやすいため,自首が大きな効果を発揮する場合は少なくないでしょう。
もっとも,自首は,犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。捜査が進んでしまった後では自首が成立せず,メリットが十分に生まれない恐れもあり得るところです。
そのため,本当に自首をすべきかどうか,自首をする場合にどのような手順・方法で行うか,という点を十分に検討する手段として,適切な弁護士選びが非常に重要となるでしょう。
また,自首を実際に行う場合にも,弁護士とともに進めることで,円滑な自首が容易になります。
ポイント
自首により,逮捕回避や処分軽減の効果が期待できる
自首すべきか,方法をどうするかは,弁護士による検討が適切
特殊詐欺事件の弁護士を選ぶ基準
①迅速な接見が可能か
逮捕勾留がなされやすい特殊詐欺事件では,弁護士による接見が不可欠です。勾留中に「接見等禁止」の処分がなされると,弁護士以外は面会すらできなくなってしまうため,弁護士が唯一の相談相手となることも珍しくありません。
特に,逮捕直後の初回の接見は,できる限り迅速に行うことが望ましいものです。刑事事件の処分結果は,逮捕直後の初期対応によって大きく左右されやすく,初期対応を誤った後に弁護士が接見を行っても,手遅れになりかねないためです。
そのため,弁護士を選ぶ際には,弁護士が速やかに接見を行い,初期対応に関する打ち合わせやアドバイスを十分にしてくれるか,という点を重要な判断基準とするのが適切でしょう。
迅速な接見ができるかどうかは,弁護士のスケジュールだけでなく,弁護士の活動方針にも影響を受けることがあるため,弁護方針として速やかな接見を予定してくれているかは確認したいところです。
②具体的な弁護方針があるか
特殊詐欺事件の場合,弁護方針に複数の選択肢があり得ます。特に,事件が一つだけでなく複数の余罪を含めた対応を要する場合や,犯罪を立証できるかどうか不明確であると思われる場合には,個別の内容・状況を踏まえた慎重な判断が求められます。
例えば,示談一つを取っても,一般的な刑事事件ではすぐに示談交渉を試みて示談の成立を目指すのが基本ですが,余罪の複数ある特殊詐欺事件では,1件だけ示談が成立してもそれ以上に示談金の負担ができなくなってしまうと,トータルとしてはメリットに乏しい結果となる恐れもあります。そのため,即時に示談を試みるかは難しい問題になり得ます。
また,取り調べへの対応に関しても,どのような内容を話すべきか,認否の方針をどうすべきかは,共犯者の状況,余罪の有無,証拠関係などを推測しながら検討しなければならず,判断は容易ではありません。
そのため,特殊詐欺事件の弁護方針をどうするべきかは,弁護士によっても見解の分かれる可能性がある点と言えるでしょう。どの方針が正解であったかは結果が出なければ分かりませんが,少なくとも,弁護士の方針が具体的・合理的なものと言えるかは,弁護士選びに際して注意するべき基準と言えるでしょう。
③弁護士との連絡が滞らないか
特殊詐欺事件では,弁護士から連絡を受ける以外に状況を把握する手段のない場合が非常に多く見られます。そのため,依頼者側にとって,弁護士との連絡が滞りなくできるかどうかはとても重要なポイントとなります。
もっとも,弁護士の連絡方法や頻度は,個々の弁護士の判断に委ねられます。依頼者目線では連絡が少ないと思っても,弁護士がそのやり方を変えようとしなければ,円滑な連絡は実現できません。
そのため,弁護士とはどのような方法で連絡が取れるか,どのような頻度で連絡が取れるか,という点は,弁護士選びの重要な基準とするのが良いでしょう。なお,法律事務所によっては,事務職員が窓口になって弁護士が直接には対応しない運用であるケースも考えられます。そのような運用が希望に合わない場合は,依頼後の連絡方法を具体的に確認することも有益です。
④事務所が遠すぎないか
特殊詐欺事件の場合,弁護士が警察署や拘置所へ足を運び,複数回の接見を行うことが必要になりやすいです。そのため,弁護士の事務所が接見場所とあまりに遠い場合には,弁護活動に限界の生じる可能性があり得ます。
また,事件を捜査する警察署は,被害者の生活圏に近いことが多く見られます。そのため,被害者への接触を試みる場合にも,やはり弁護士が足を運ぶ必要があるため,同様の問題が生じるでしょう。
そのため,特に身柄事件の場合には,弁護士の事務所があまりに遠方でないか,という点を判断基準の一つとすることをお勧めします。なお,遠方である場合にどのような影響があるかは,弁護士に直接確認の上,弁護士の案内を求めるのが望ましいでしょう。
特殊詐欺事件で弁護士を選ぶ必要
①実刑判決を防ぐため
特殊詐欺事件は,起訴され刑罰を受けることが避けられない場合も少なくありません。そして,刑罰を受ける場合,実刑判決(=直ちに刑務所へ収容することを命じる判決)の対象となることも十分に考えられますが,実刑判決は社会生活を続けられないことを意味するため,不利益が非常に大きく,何としても避けたい場合がほとんどでしょう。
そのため,特殊詐欺事件の多くでは刑罰の軽減に向けた動きが必要となりますが,具体的な方法や内容は個別の事情を踏まえて決定する必要があるため,弁護士の専門的な判断が不可欠です。実刑判決を避けられる見込みがどのくらいか,手段を尽くすとそれがどの程度変わるのか,尽くすべき手段は何か,といった点については,弁護士の判断を仰ぐことが適切でしょう。
②早期釈放のため
特殊詐欺事件の場合,逮捕後にすぐ釈放されるということはあまり期待できません。身柄拘束を続ける必要性が非常に高い事件類型のため,安易に釈放を期待することは適切とは言い難いです。
もっとも,特殊詐欺事件でも釈放を目指すことのできるタイミングは存在します。代表的なものが起訴後の保釈でしょう。起訴後は,起訴前とは異なり捜査が終了しているため,捜査の妨害を防ぐために身柄拘束を続ける必要が小さくなります。そのため,認め事件であれば,起訴後に保釈してもらえることは特に珍しくありません。
この点,保釈による釈放が早期にできるかどうかは,早期に弁護士が動いているかによって大きく変わります。弁護士選びに手間取っていると,それだけ釈放時期が遅れてしまうことになりかねないため,早期釈放に向けて弁護士を速やかに選ぶことが適切です。
③適切な取り調べ対応のため
余罪を含む複数の事件が捜査される特殊詐欺事件では,慎重な取り調べ対応が必要です。取調べに対してどこまでの話をするのかは,事件ごと,状況ごとの検討が不可欠ですが,余罪が絡みやすい特殊詐欺事件では,事件間の関係や想定される証拠なども踏まえて判断する必要があるため,対応方針を決めるのも容易なことではありません。
特殊詐欺事件で最も有益な取調べ対応を行うためには,やはり専門的な知識・経験を持つ弁護士に依頼し,弁護士から適宜助言を得つつ進めることが望ましいでしょう。
弁護活動の一般的な方針
①認め事件の場合
認め事件での弁護活動は,被害者への金銭賠償や示談の試みに尽きるでしょう。
被害者に対するアクションは,弁護士を挟む方法でしか行うことができないため,弁護士に依頼し,弁護士限りで被害者と接触することを目指す必要があります。
弁護士からは,加害者の汲むべき事情なども踏まえ,可能な限り被害者側のお許しを獲得するための試みを行います。
②余罪の発覚を防ぐ場合
自分の関与した事件の一部のみ発覚しており,余罪が発覚していない場合,余罪の発覚を防ぐことが有益になりやすいです。このときは,取調べに対する対応をどうするかが非常に重要となり,その点を弁護士に判断してもらうのが適切です。
一般的には,発覚していない余罪についてのみ黙秘をし,自分からは情報提供しない対応が有力です。もっとも,むやみに黙秘をし過ぎるのは,捜査の長期化につながりやすく,発覚した事件の情状面にも影響することがありますので,具体的な方針は弁護士と十分に協議をしましょう。
③否認事件の場合
身に覚えがない場合には,弁護士を通じて犯罪事実が存在しないことを強く主張してもらうようにしましょう。
特殊詐欺のように複数名が関与する事件の場合,関係者間で足の引っ張り合いが生じるケースもあります。自分の処分を軽くするために他の関係者にとって不利益な供述をすることを,引っ張り込みなどと言います。
また,否認事件の場合も,取り調べへの対応方針は非常に重要です。話すのか話さないのか,話すとしてどこまでのことを話すのかは,個別の事件に応じて弁護士の専門的な判断を仰ぐのが適切でしょう。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
特殊詐欺の事件は,漫然と対応していると実刑判決を受けて刑務所に入ることも珍しくない重大な事件類型です。
また,組織的な事件であることから,弁護士がいなければ状況を把握することの難しい場合も多く,弁護士を通じて対処すべきことも多いため,弁護士に依頼する必要が生じやすいと言えるでしょう。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
特設サイト:藤垣法律事務所