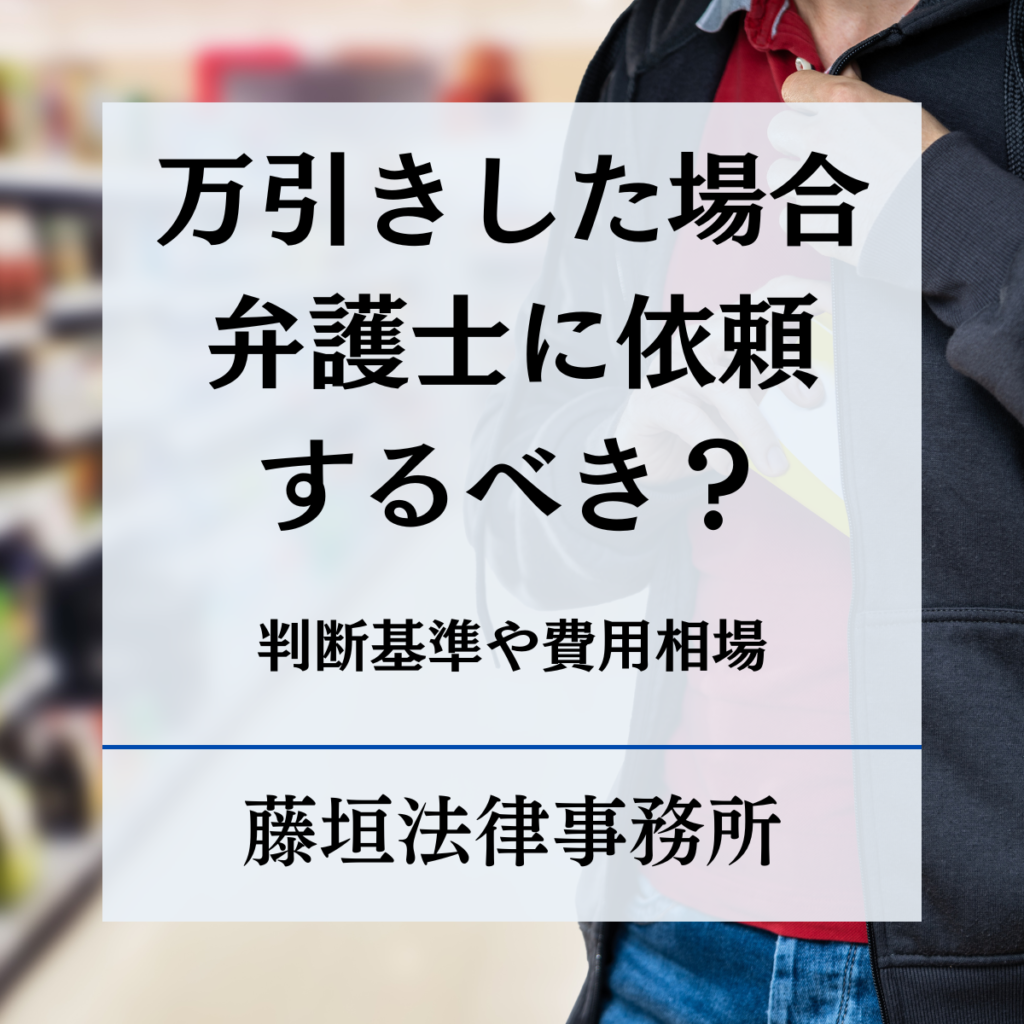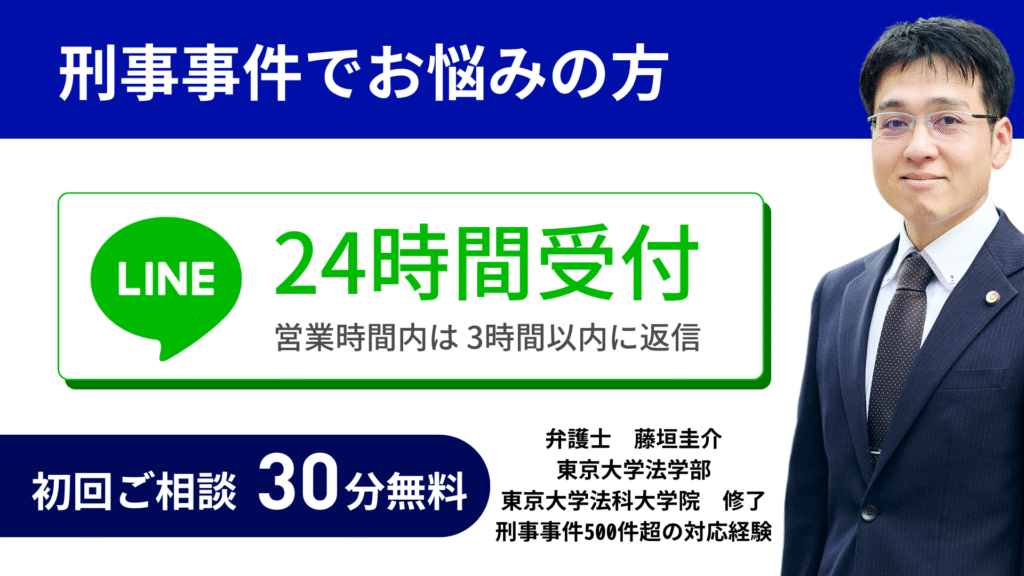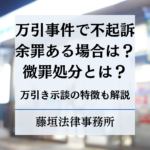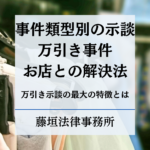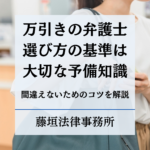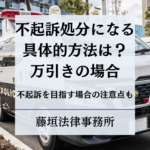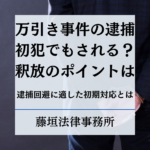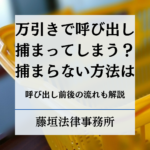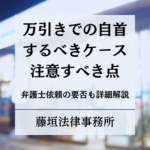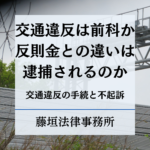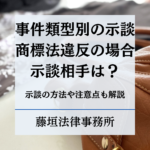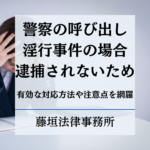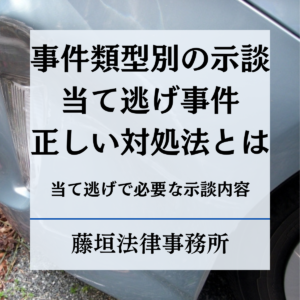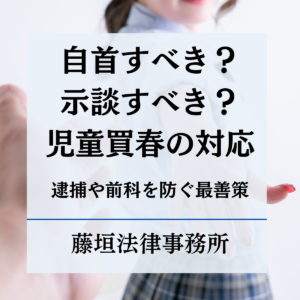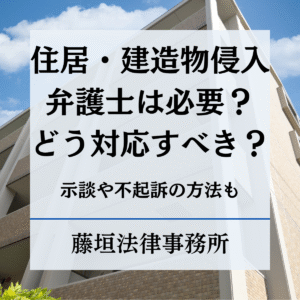万引きをしてしまったものの、今後どうするべきか、法律の専門家である弁護士に相談するべきか悩んでいる方もいるでしょう。
万引きは軽い気持ちで犯してしまうことも多いものの、その影響は意外にも大きく、放置すると刑罰が重くなってしまう恐れがあります。
本記事では、万引きした場合は弁護士に依頼するべきかどうかをご紹介し、費用相場も詳しく解説します。
藤垣法律事務所は、万引き事件を含む、500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、スピーディな対応を行っております。
特に万引き事件は、少しでも早い対応が必要になるため、お困りごとがあればぜひ下記からお問い合わせください。
この記事の監修者

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
万引きの刑罰内容

万引きという行為自体が軽犯罪法や刑法に基づく違反とされるため、法律で厳しく定められています。
万引きは窃盗罪に該当し、その刑罰は懲役刑や罰金刑が課されることがあります。
具体的にいうと、刑法第235条により、窃盗罪として扱われると「10年以下の懲役または50万円以下の罰金(参考:e-Gov法令検索)」が科される恐れがあるのです。
窃盗罪に該当する行為は、以下の通りです。
- 他人の占有する財物
- 窃取
- 不法領得の意思
これらの行為を行うと、刑罰の対象となるため、逮捕されてしまう可能性があります。
万引きしてしまった際に弁護士に依頼するケース

万引きしてしまった際、自分が逮捕されてしまうのかどうか不安になることもあるでしょう。
そんな時、弁護士に相談するのがおすすめですが、必ずしも弁護士を活用するのがいいとは言い切れません。
万引きしてしまった際に弁護士に依頼するケースは、主に以下の通りです。
- 過去に万引きや窃盗など前科があるケース
- 万引きで逮捕されたケース
- 万引きで後日逮捕の可能性があるケース
- 営利目的で万引きをしたケース
- 依頼している弁護士の対応に不満があるケース
詳しく解説します。
過去に万引きや窃盗など前科があるケース
過去に万引きや窃盗で前科がある場合、再度万引きをしてしまうと、初犯とは異なる厳しい法的な処分が予想されるため、弁護士への依頼が強く推奨されます。
前科がある場合、裁判所や検察が再犯を重く見て処罰を厳格化する傾向が強くなり、執行猶予が認められにくくなる可能性が高まります。
そのため、状況に応じては懲役刑が科されるリスクが高くなり、刑事手続きの早い段階で弁護士が介入し、可能な限りの弁護活動を行うことが重要です。
「過去に万引きや窃盗など前科がある」場合、常習性があるとみなされ、前科のときよりも重い罪になる可能性が高いです。ただし、手段を尽くすことで処分を軽くするなどを図ることはできます。
万引きで逮捕されたケース
逮捕後は警察署での取り調べや勾留が続き、その間の行動や対応が今後の処分に大きく影響を与えます。
ここで避けなければいけないのが、最大20日間の勾留期間です。仮に20日間拘束された場合、会社をクビになったり、学生の場合は学校生活に支障をきたしたりなどのリスクがあります。
弁護士に依頼すれば、取り調べにおける適切な対応についてアドバイスを受けられるほか、不利な証言を防ぐための指導が得られます。
処分を少しでも軽減するための重要なサポートを受けられるでしょう。
後日逮捕の可能性がある状況で弁護士への相談をしないでいるとある日突然に逮捕され、警察の留置施設に収容されてしまう恐れがあります。万引き事件に心当たりがあり、警察の捜査や逮捕が懸念される場合にはできるだけ早く弁護士への相談・依頼を行うことをおすすめします。
万引きで後日逮捕の可能性があるケース
万引きをした後、その場で発覚しなかった場合でも、後日逮捕される可能性があります。
店側が防犯カメラの映像などを通じて不審な行動を確認し、被害届を出すことで捜査が開始されるケースが多いため、安心できる状況ではありません。
防犯カメラの映像が決定的な証拠となって逮捕に繋がる場合、被疑者は突然の逮捕に備える準備が整っていないことが多く、慌ててしまうでしょう。
こうしたケースでは、早い段階で弁護士に依頼することで、適切な対応や対策を取るための支援が得られます。
罪が重くなるのはケースバイケースですが、万引きしているのに相談もせず黙っている場合は繰り返して万引きしているケースが多いと考えられます。回数を重ねている方が処分として重くなる傾向があるので、速やかに弁護士に相談しましょう。
営利目的で万引きをしたケース
営利目的とは、盗んだ物を転売して利益を得る意図がある場合であり、「偶発的な犯行」と異なり、計画性や悪質性が高いとみなされます。
このようなケースでは、逮捕や勾留、さらに起訴に至るリスクが大きいため、早急に弁護士に依頼し、適切な対応を取ることが重要です。
弁護士に依頼するメリットとしては、まず刑事処分の軽減に向けた効果的な弁護活動を受けられることが挙げられます。
営利目的の犯行は検察官や裁判所から重い評価を受けやすいため、通常よりも厳しい起訴や刑罰が予想されるでしょう。
弁護士が早い段階から介入し、被疑者の背景や動機を詳しく説明し、情状酌量の余地を示すことで、量刑の軽減を目指すことが可能です。
実際に売ってしまったかどうかが刑の重さに直結するわけではなく、営利目的で万引きをする行為自体が営利目的がない場合よりも重い罪の対象になりやすいです。
依頼している弁護士の対応に不満があるケース
弁護士との関係が円滑でなければ、不安が増したり、最善の結果を得ることが難しくなる可能性があります。
不満の理由は多岐にわたり、進捗報告が遅い、対応が不十分、説明が曖昧など、依頼者の要望や疑問にしっかりと向き合っていないと感じることが多いです。
万引きのケースで特に重要なのは、取り調べでの適切な対応や、起訴回避に向けた交渉、示談成立のための迅速な行動です。
しかし、こうした基本的な対応が不十分だと、依頼者は精神的に追い詰められ、信頼関係が損なわれてしまうでしょう。
もし依頼している弁護士の対応に不満があるケースは、万引き事件に強く、かつ迅速対応してくれる弁護士に乗り換えを検討しましょう。
当事務所では、迅速対応に強みがあり、スピーディーな弁護活動で事件解決のお力添えをしております。実際に不起訴に繋げたり、逮捕されたけど速やかに釈放されたりなど、同種事件の解決実績も複数ありますので、ぜひご相談していただければと思います。
万引きした際に弁護士に依頼しない方がいいケース

万引きした際、弁護士に依頼しない方がいいケースとして挙げられるのは、初犯であり、被害店舗が明らかに許している場合です。
多くの初犯者の場合、逮捕されることなく警察での事情聴取や簡単な取り調べのみで処理され、起訴されずに警告や指導で終わる可能性が高いからです。
特に万引きの規模が小さく、故意性や計画性が低いと判断されると、社会的な更生が期待できるとして厳重な処分を避けられることもあります。
また、被害店舗が許している場合は、店舗側が被害届を取り下げたり、そもそも提出しなかったりする可能性が高いため、刑事事件として進行しないでしょう。
逆に初犯だったとしても店舗側が許してくれていなければ弁護士に依頼する必要があります。
万引きの初犯ケースについては、下記の記事で詳しく解説しているので、合わせてご確認ください。
関連記事:万引き事件は初犯だとどうなる?前科や余罪の影響も解説
万引き事件で弁護士に依頼するメリット
早期釈放
万引き事件の場合,逮捕後の早期釈放を目指すべきケースが非常に多い傾向にあります。逮捕直後から適切な対応を尽くした場合とそうでない場合とでは,釈放されるタイミングに大きな差が生じることも珍しくありません。早期釈放の可能性があり得るからこそ,早期釈放に向けた動きは十分に取るべきです。
具体的には,やはり弁護士に依頼し,法的手続に沿って釈放に向けた弁護活動を尽くしてもらうことが最も有益です。弁護士であれば,被疑者本人と十分にコミュニケーションを取ることができる上,検察官や裁判官に対して適切な情報提供や申立てを行いながら,早期釈放のために可能な手段を尽くすことが可能です。
処分軽減
万引き事件は,内容次第では不起訴処分が十分に目指せる事件類型です。不起訴処分となれば,前科が付かずに手続が終了し,事件の悪影響は最小限に抑えられるでしょう。
もっとも,処分の軽減を目指すための具体的な行動は,自分で判断して行うことが困難なものと言わざるを得ません。何をするべきか,という選択が困難であるのみならず,そもそも弁護士を間に挟まなければできないことも少なくないためです。
そのため,万引き事件で処分の軽減を目指す動きを尽くし,不起訴処分の獲得を希望したい場合には,対応に適した弁護士を選ぶ必要があるでしょう。
前科前歴がある場合の対処
万引き事件の場合,1回だけ行った,というケースが非常に少なく,前科前歴のある場合も多く見られます。一般的に,同種の事件を繰り返してしまうと,繰り返すごとに刑事処分は重くなっていくことになります。
そのため,前科前歴がある場合には,それだけ重い刑事処分が科せられる可能性を考慮する必要がある,ということになるでしょう。
前科前歴があり,より十分な対応を尽くさないと重い刑罰が懸念されるという場合には,弁護士に依頼をして適切な弁護活動を行ってもらう必要が大きいと言えます。結果が出た段階で後悔することを防ぐため,事前に弁護士選びを行うべきでしょう。
更生や治療
万引き事件の加害者となってしまう原因には,病的なものが影響しているケースもあります。「クレプトマニア」(窃盗症)と呼ばれるものが代表例です。
事件の原因が病的なものである場合,刑事処分の軽減を目指すと同時に再発防止のための医学的なアプローチが必要となります。通院治療などを通じて,万引き行為への病気の影響を防げなければ,事件の十分な解決とは言えません。
自分の万引き事件が病的な原因で起きていると考える場合には,弁護士に依頼し,原因の解決についても相談を試みることが有益です。また,実際に通院治療などを行い,これを弁護士に主張などしてもらうことで,治療の努力をしたことが刑事処分の軽減につながる効果も期待できます。
万引き事件で弁護士に依頼するタイミング
逮捕されたとき
万引き事件での逮捕は,現行犯であることが非常に多いです。逮捕される事件では,現場で店員等に発覚し,警察に引き渡される流れが大多数でしょう。
一方,万引き事件は,類型的に重大犯罪との理解はされづらいため,逮捕されたとしてもその後に早期釈放が期待できる場合も少なくありません。早ければ,逮捕の翌日や翌々日に釈放となり,社会生活に復帰できる可能性もあり得るところです。そうなれば,逮捕による生活への影響は最小限に抑えることができるでしょう。
そのため,万引き事件で逮捕されたときは,早期釈放を目指すために弁護士を選ぶべき重要なタイミングということができます。適切な弁護士選びをし,弁護士に十分な弁護活動を尽くしてもらうことで,早期釈放の可能性はより高くなるでしょう。
また,逮捕やその後の早期釈放は,あくまで捜査の初期段階に過ぎないため,最終的な処分を軽減するための対応も必要不可欠です。この点,逮捕などの早い段階で弁護士に依頼し,適切な方針を立てることができれば,最終的な刑事処分にとっても有益な効果が期待できるでしょう。不起訴処分を目指す対応は,逮捕段階から始まっていると言っても過言ではありません。
呼び出しを受けたとき
万引き事件では,後日になって被疑者が特定でき,警察が被疑者を呼び出す流れも非常に多く見られます。警察の呼び出しを受けた場合は,警察署での取り調べが行われることを想定するのが適切です。
もっとも,取調べでどのような対応をするべきか,何が聞かれ,何を回答すべきかという点は,万引き事件の取り扱いに精通していないと判断は困難です。対応時の注意点なども,個別の事件によって異なる可能性があるため,一概には指摘できないところがあります。
この点,万引き事件の弁護活動に適した弁護士を選ぶことができれば,呼び出しに対する適切な対応や供述の方針などを事前に確認することが可能です。事前に適切な方針を立てることができれば,呼び出しへの対応は格段に容易なものになるでしょう。
自首をしたいとき
万引き事件では,被害者であるお店側が損害の内容を特定できていなかったり,そもそも被害の事実を把握していなかったりと,具体的な刑事事件の捜査に至るまでに時間のかかるケースが少なくありません。万引き事件の捜査は,お店側が警察に被害申告することで開始する場合がほとんどであるため,お店側が十分に事件を把握するまでは捜査が開始しない,という流れになりやすいのです。
そのため,万引き事件は,捜査が開始される前に自ら警察に出頭(自首)することが可能になりやすい事件類型であると言えます。自首が成立する場合には,警察の取り扱いとして逮捕がされにくくなったり,最終的な刑事処分も不起訴処分などの軽微なものになりやすかったりと,有益な効果が期待できる場合も多いでしょう。
この点,自首を試みる場合には,弁護士選びの上,弁護士と一緒に適切な方法で行うことが望ましいでしょう。手続に精通した弁護士が主導して自首することで,自首のメリットがより大きくなる効果も期待できます。
裁判を控えているとき
万引き事件で起訴され,公開の裁判(公判)を控える状況になった場合には,適切な弁護士選びが非常に重要となります。
万引き事件で公判を控えるケースというのは,前科や余罪が多数あったり,事件の内容や規模が悪質と理解されるものであったりと,実刑判決などの重大な刑事罰が懸念される場合が少なくありません。軽微な処分で済むのであれば,公判を行う必要はないため,公判に至った場合には万全の対応をすべき必要が非常に大きいと考えるのが適切でしょう。
そのため,公判を控える状況にある場合には,公判対応に適した弁護士を選び,実刑判決などの重大な刑事処罰を避けるための十分な準備と対応を尽くすことを強くお勧めします。また,刑事弁護に長けた弁護士に依頼すれば,結果の具体的な見通しが分かり,処分軽減のためにすべきこともより明確にすることができるでしょう。
万引きした際の弁護士に依頼する費用相場と内訳

弁護士に依頼する際、気になるのは費用でしょう。着手金や成果報酬などは、弁護士事務所によって異なりますが、大体全て含めると90万円〜100万円が一般的です。
かかる費用の内訳は主に以下の通りです。
- 法律相談料
- 着手金
- 接見費用
- 成功報酬
- 日当
- 実費
詳しく解説します。
法律相談料
万引きの問題で弁護士に依頼する際にかかる費用のうち、最初に発生するのが法律相談料です。
法律相談料は、弁護士と面談して状況を相談し、事件の概要や解決の方針についてアドバイスを受けるための費用です。
一般的には、30分から1時間の面談で5,000円から1万円ほどが相場とされていますが、弁護士によっては初回の相談を無料で提供している場合もあります。
当事務所では、初回無料相談を設けております。 2回目以降の場合は、30分ごと5,500円となります。
着手金
万引き事件で弁護士に依頼する場合、着手金は依頼を正式に受けた際に支払う初期費用として重要です。
この着手金は、弁護士が事件の処理を開始するための費用となります。着手金の相場はおおむね30万円以上かかるのが一般的です。
万引きで逮捕された場合や、被害者との示談が求められる場合など、弁護士の関与が深まるほど、その着手金の額も高くなる傾向にあります。
当事務所では、着手金は33万円からとさせていただいております。
接見費用
万引きで逮捕された場合、弁護士が依頼者と直接会って事情を聴取したり、法的アドバイスを行ったりするために発生する費用が接見費用です。
拘置所や警察署に足を運んで行うため、時間と手間がかかることから発生する費用となります。
接見費用の相場は、1回あたり1万円から3万円程度が一般的ですが、距離や面会の内容によって変動することもあります。
当事務所では、接見費用は日当という項目に該当し、大宮駅からの移動時間30分ごと5,500円からとさせていただいております。
成功報酬
弁護士に依頼する際、成功報酬は依頼の成果に応じて支払われる費用です。
成功報酬は、弁護士が依頼者のために有利な結果を得た場合に支払われるもので、特に示談交渉や不起訴処分を目指す場合などに発生することが一般的です。
成功報酬の額は、事件の難易度や弁護士の報酬体系によって異なるものの、成功報酬として設定される額は通常、数十万円に及ぶことがあります。
当事務所では、成果報酬は着手金にプラスする形をとらせていただいております。不起訴であれば着手金にプラス33万円、示談成立の場合は着手金に22万円などといった感じです。
日当
日当は、弁護士が依頼者のために行う活動の一部に対して、一定の日数にもとづいて支払われるものです。
特に裁判所への出廷や長時間にわたる交渉、調査活動などが関わる場合に発生します。
例えば、万引き事件において裁判が長引く可能性がある場合、弁護士は出廷や法廷での弁護活動を行うため、1日単位で日当が設定されることがあります。
日当の相場は、弁護士の経験や事務所の方針、事件の規模により異なりますが、一般的には1日あたり3万円から10万円程度が相場です。
当事務所では、日当は大宮駅からの移動時間30分ごと5,500円からとさせていただいております。
実費
実費とは、弁護士が事件を進めるために実際に支出した費用を指し、依頼者がその費用を負担することになります。
具体的には、交通費や郵送費、証拠収集にかかる費用、鑑定料、裁判所への申立てに必要な手数料などが含まれます。
実費が発生しないプランもありますが、特に遠距離移動がある場合だと、発生してしまうでしょう。
当事務所では、実費は発生した実額でご請求いたします。
万引きしてしまい弁護士に依頼する際の事務所の選び方

万引きをしてしまい、弁護士に相談したい場合、どの事務所を選べばいいか迷うでしょう。
主な選び方は、以下の通りです。
- 解決実績があるか
- 迅速に対応してくれるか
- 再犯防止のために協力してくれるか
詳しく解説します。
解決実績があるか
万引きは、一般的な民事訴訟とは異なり刑事事件として扱われることが多いため、弁護士が過去にどのような実績を持っているかが重要です。
刑事事件全体を対応しており、数多くの実績を持っている弁護士もいれば、万引きや窃盗事件に特化した弁護士も存在します。
万引きに関して過去に多くの成功事例を持つ弁護士であれば、その実績をもとに効果的な戦略を立てることができ、依頼者にとって安心感が得られます。
ホームページや口コミなどを確認した上で、依頼するか検討しましょう。
迅速に対応してくれるか
万引きが発覚した直後は、店内の防犯カメラによって捜査が進むため、状況が急速に進展する可能性があります。
そのため、対応が遅れると、被害者や警察からの対応が不利な方向に進むでしょう。
弁護士が迅速に対応できるかどうかは、その後の法的な進展を大きく左右する要素です。
例えば、万引きが発覚した後に警察の取り調べや事情聴取が行われる前に、弁護士が迅速に関与することで、逮捕や勾留を避けたり、逮捕後に早期に釈放を実現したりする可能性が高まります。
こうした迅速な対応が、後々の刑事手続きにおいても有利に働くことが多いため、依頼者にとって重要なポイントです。
再犯防止のために協力してくれるか
万引きで弁護士に依頼する際、単に事件の法的な解決を求めるだけでなく、その後の再犯防止のためにどのように協力してくれるかを確認することは、長期的に見て有益です。
再犯防止への協力とは、弁護士が事件を通じて依頼者に対して犯罪の重大さをしっかりと伝え、反省を促すためのサポートをしてくれるかどうかです。
例えば、依頼者が参加できる更生プログラムやカウンセリング機関を紹介してくれるかどうかなどが該当します。
依頼者が再び社会の一員としての自信を取り戻し、犯罪に手を染めることなく生きていけるようなサポートをしてくれるでしょう。
万引き事件における弁護士選びの準備
包み隠さず説明する準備
弁護士選びのためには,弁護士に十分な情報を提供することが必要です。弁護士の案内が不十分だと感じた場合,その原因が情報不足だと,適切な弁護士選びのチャンスを逃す結果にもつながりかねません。
万引き事件の場合,対象となった商品の内容はもちろん,余罪や前科前歴など,自分にとって不利益で言いづらいことも,包み隠さず弁護士に説明できるように準備することをお勧めします。言いづらく隠しておきたくなることほど,弁護士にとって重要な情報であることが少なくありません。
弁護士に求めたい要望の整理
弁護士選びに際しては,弁護士に何を実現してほしいのか,という要望を整理し,弁護士に伝えられるよう備えておくことをお勧めします。
万引き事件の場合,釈放を求めたい,不起訴を獲得したい,示談をしたい,自首をしたい,周囲に発覚したくないなど,要望のメインになり得る点は多数あります。もっとも,ケースによってはそのどれかは実現不可能であったり,弁護士の見通し次第で案内の内容が変わってきたりと,事前に聞いておかなければトラブルの原因になるものもあります。例えば,不起訴を希望したいと思って依頼したものの,弁護士側は不起訴が不可能だという前提で考えていると,そのミスマッチは致命的です。
弁護士への依頼には一定の費用が発生するため,相応の成果を求めたいというのは自然な発想です。弁護士選びが無駄にならないよう,要望は何かを明確に整理し,弁護士への依頼によって実現可能かどうかを十分に確認するようにしましょう。
予算の決定
万引き事件は,高額の商品を対象とするケースが少ないため,事件規模は金額にするとそれほど大きくないことが通常です。もっとも,その事件に対応するための弁護士費用は,着手金のみでも数十万円という規模になることが一般的です。
そのため,特に経済的に余裕がない場合には,あらかじめ予算を決定し,その範囲内での弁護士探しを行うことをお勧めします。
弁護士費用は,活動の結果によっても左右されるため,着手金だけでギリギリ,とならないよう,可能な限り余裕を持った検討が望ましいところです。また,事前に予算を明確にしている場合には,その予算の範囲内でできる活動内容を弁護士側から案内してもらえる可能性もあるでしょう。
万引き事件で弁護士に依頼する場合の注意点
弁護士との相性
依頼者も弁護士も人である以上,相性の問題を避けて通ることはできません。依頼者目線では,相性が良くないと感じながら弁護士に依頼するメリットはないと考えるべきでしょう。
この点は,最善の解決に至ればそれほど大きな問題にはなりません。しかしながら,弁護活動は事前に最善の結果になるとお約束することが不可能であり,どうしても結果が伴わない場合があります。特に,万引き事件ではお店側と示談をしたり,お店から許してもらったりすることが現実的に難しいため,希望する最善の解決は困難な方が多いでしょう。
そして,弁護士との相性を軽視することは,最善の結果でなかった場合に大きな問題となります。弁護士が最善の活動をしてくれたのか,結果はやむを得ないものだったのか,という点について疑念が生じやすくなるためです。
弁護士との相性が良く,弁護士の活動を心底信頼できれば,心から「やむを得なかった」と納得しやすいですが,相性が悪いと感じている場合にはそうもいかないことが多くなりがちです。
弁護士との相性を率直にどう感じるか,という点は,弁護士選びに際して軽視しないことが適切でしょう。
弁護士相談の時間的制限
弁護士への法律相談は,30分以内,又は1時間以内といった形で時間を区切って行われるのが通常です。その時間内で,必要な情報を伝え,弁護士から案内を受け,弁護士選びの検討を行う必要があります。
もっとも,その時間は決して長くはありません。無意識に相談時間を浪費してしまうと,肝心の弁護士選びに必要な話が聞けないまま相談が終了してしまう可能性もあるでしょう。
そのため,弁護士選びに際しては,弁護士への法律相談に時間的な制限があることを踏まえ,弁護士選びの基準や聞きたいことなどを可能な限り整理して法律相談に臨むことをお勧めします。そのようなスタンスは,法律相談をより有益な内容とする結果にもつながるでしょう。
万引きに強い弁護士へご相談を!
万引きをしてしまった場合、初犯であれば不起訴になる場合もありますが、再犯の場合だと悪質性があり、刑罰に該当してしまいます。
刑罰を少しでも軽くするのであれば、弁護士に依頼することがおすすめです。
特に刑事事件に精通した弁護士へ依頼すれば、これまでの実績や知見などをいかした上で、迅速に適切な対応を行ってくれます。
藤垣法律事務所は、万引き事件を含む、500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が在籍しており、スピーディな対応を行っております。
特に万引き事件は、少しでも早い対応が必要になるため、お困りごとがあればぜひ下記からお問い合わせください。
特設サイト:藤垣法律事務所