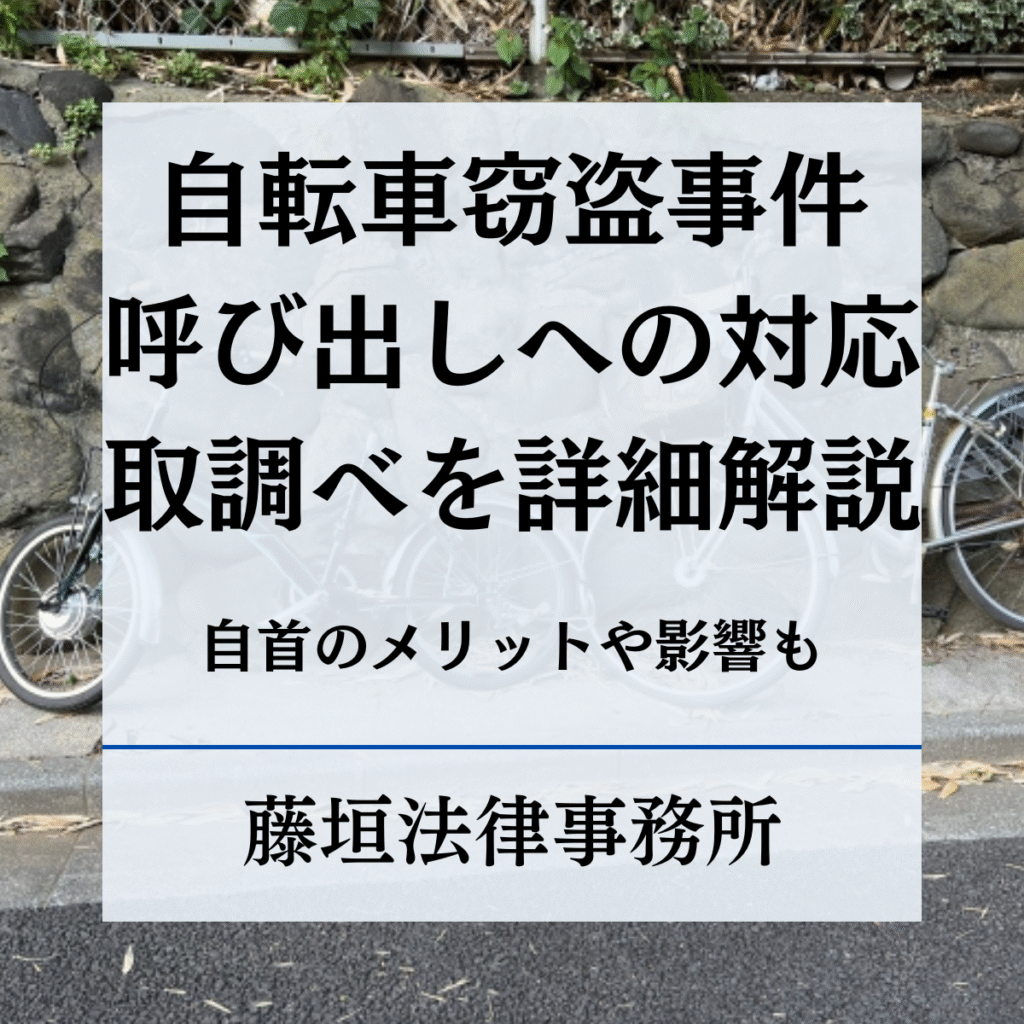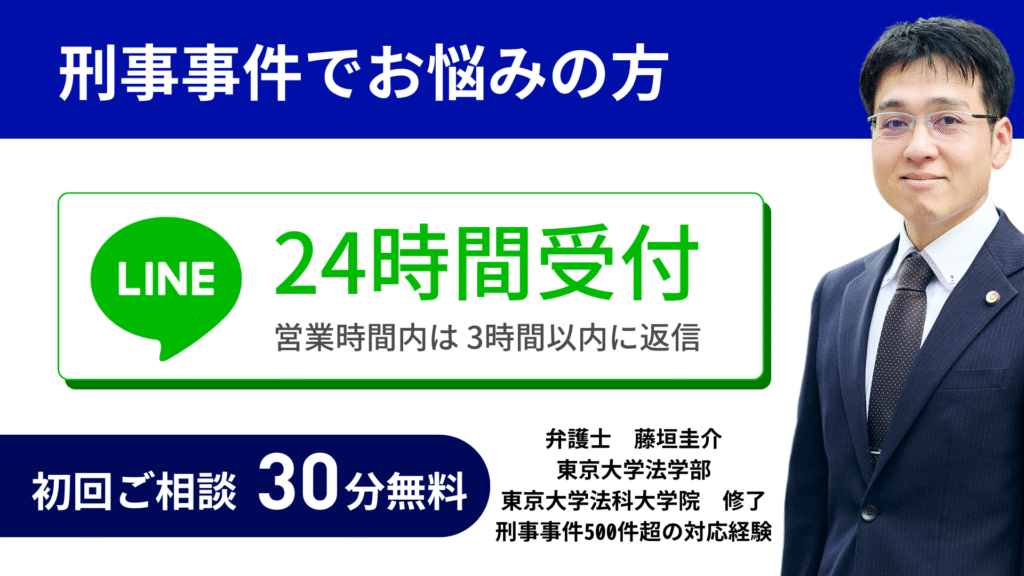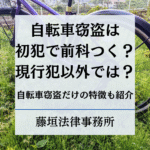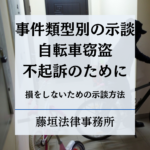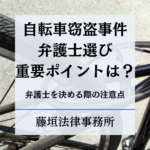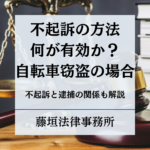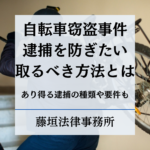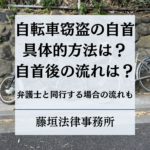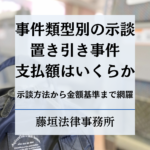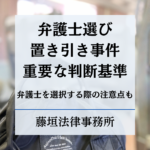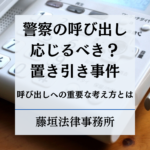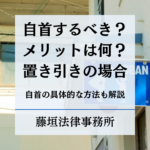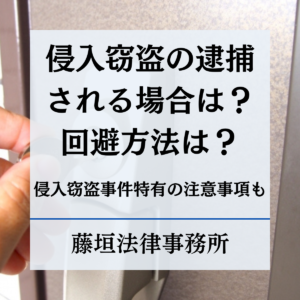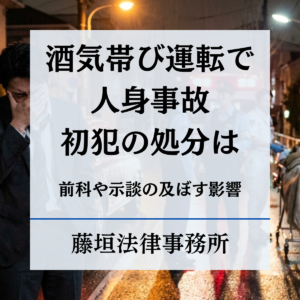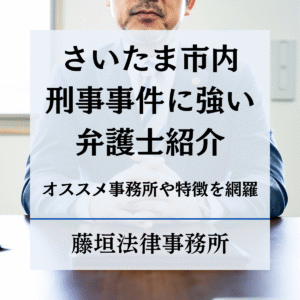このページでは,自転車窃盗事件で警察や検察の取調べを受ける場合について,適切な対応方法などを弁護士が解説します。
自転車窃盗の呼び出しへの対応や今後の見込みを検討するときの参考にご活用ください。
この記事の監修者

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
自転車窃盗事件における取調べの対応法
①認め事件の初回呼び出し
事件の内容に争いがなく認めるケースでは,初回の呼び出しに際して認める方針であることを極力速やかに示すのが賢明です。
初回呼び出し前の段階では,捜査機関にとって被疑者のスタンスが分かりません。認めるか否認するか,どのような言い分を述べてくるのか,予想に限界があるため,最も対応に気を付けるべき否認や証拠隠滅の可能性を踏まえて望むことになるでしょう。
この点,できるだけ速やかに認めて争わないことを示せば,呼び出し後の手続は円滑になり,不要な負担を減少させることにもつながります。反省の態度を明らかにする趣旨でも,非常に有効な動きと言えます。
ポイント
認める方針であることをできるだけ早期に示す
②認め事件の2回目以降
認め事件における2回目以降の呼び出しに際しては,1回目の呼び出しで述べた内容を踏まえ,供述調書の作成などを行うことが想定されます。そして,捜査機関としては,1回目の呼び出しでなされた話を前提に,全ての段取りを想定していることが通常です。
そのため,呼び出された場合の対応としては,確実に出頭の上で,1回目と矛盾のない供述や対応に努めることが適切です。話すたびに内容が二転三転するのは,手続の停滞や長期化を招くのみでなく,自分の供述が信用できない,との評価につながりやすいため,避けることが賢明でしょう。
なお,1回目の呼び出しで事実でないことを話してしまった,という場合には,2回目の出頭より前の段階で訂正を申し出るのが円滑でしょう。多くの場合,1回目の呼び出しから日を空けて2回目の出頭日時を調整することになりやすいですが,2回目の出頭日時を相談する際にあわせて訂正を申し出るのは有力な手段です。
ポイント
1回目の供述内容を踏まえた供述調書の作成などが見込まれる
話が矛盾しないよう一貫した内容とすることが適切
③否認事件
否認事件の場合には,まず自分が何を疑われているのか,という被疑事件の具体的内容を把握するように努めましょう。疑われている内容を正確に理解することが,否認の第一歩となります。
また,被疑事件の内容を把握することで,その証拠関係を推測できるケースもあります。現場を録画した防犯映像はあるのか,目撃者はいるのかなど,証拠の有無や内容が分かれば,あらぬ疑いが生じている原因を突き止めるきっかけにもなります。
なお,これらの前提として,呼び出しに応じて出頭することは重要な対応です。呼び出しに対応させられることへの不満は募るものですが,かえって情報を得るチャンスと理解すれば,有益な機会とすることも可能になるでしょう。
ポイント
疑いの内容や証拠関係を把握する
呼び出しに応じることは非常に重要
自転車窃盗事件の取調べに応じたときの注意点
①記憶に乏しい場合
自転車窃盗事件でよく見られるのが,飲酒をした日の帰り道,というケースです。終電を逃した後,最寄り駅まで電車に乗った後など,徒歩が必要なタイミングで,目についた自転車を乗り捨ててしまう,というものです。
このような事件では,往々にして事件当時の記憶が乏しく,十分な供述ができないことも考えられます。それでも,呼び出しを受けて話を求められることは避け難いため,対応の仕方は十分に知っておくことが必要です。
この点,記憶に乏しい場合には,以下の点に注意することが適切でしょう。
記憶に乏しいときの対応
1.記憶がある部分とない部分を具体的に区別する
→漫然と「覚えていない」と供述するのは,手続の停滞や長期化を招く原因となるため,できるだけ避けるべき
2.記憶がない部分の認否を明確にする
→「覚えていない」との返答は基本的に「認めていない」という意味であるため,その認否が自分の真意と合致しているかは注意すべき
②単独での事件でない場合
自転車窃盗事件では,窃盗した自転車に二人乗りで移動したなど,単独の事件でない場合も少なくありません。このような場合には,自分以外の人物について何と話すのか,という点も検討する必要があります。
また,単独の事件でないことが明らかとなった場合には,他の関係者も呼び出され,話を聞かれることが見込まれます。そのため,他の人がどんな話をするのか,という点も自分の手続や処分に影響を及ぼす可能性があります。
この点,犯人隠避罪や証拠隠滅罪に該当する行為をしないことには,十分に注意をする必要があります。他人に自分の犯罪の証拠を隠滅させたり,自分が他人の犯罪の証拠を隠滅したりする行為は,証拠隠滅罪に該当し,別途刑事処罰を受ける可能性が生じます。なお,ここでの証拠には,物的なものだけでなく,人(人の話=供述)も含まれます。口裏合わせを試みることも含まれることになるため,注意すべきでしょう。
証拠隠滅行為が犯罪とならない場合
・自分の犯罪の証拠を自分で隠滅する
証拠隠滅行為が犯罪となる場合
・自分の犯罪の証拠を他人に隠滅させる
・他人の犯罪の証拠を自分が隠滅する
③自転車を処分するべきか
窃盗した自転車を所持している場合,これを手元に置いておくべきか処分すべきか,という点は悩みが生じやすいポイントです。
この点,少なくとも捜査を受けた後に処分することは,メリットに乏しく基本的に不合理と考えるのが適切でしょう。既に被疑者が特定されており,自転車が手元にあってもなくてもその責任が増減することは考えにくいためです。
一方,まだ捜査を受けていない場合については,自転車を処分することで自分が被疑者と特定されなくなるケースがあるかもしれません。もっとも,発覚した場合には悪質であると判断される原因になり得るので,非常に大きなリスクが伴うことは注意しておくべきでしょう。
また,証拠隠滅行為となり,他者を巻き込むと犯罪に該当するため,他者に相談したり他者と一緒になって行ったりすることは厳禁です。
自転車窃盗事件の呼び出しに応じると逮捕されるか
自転車窃盗事件の場合,呼び出しに応じたことで逮捕される,という経過をたどることはほとんどないと考えられます。むしろ,逮捕を防ぐ意味では,呼び出しに応じることが最善の手段と言っても過言ではありません。
逮捕は,逃亡や証拠隠滅を防ぐために行われるものですが,呼び出しに応じる場合と応じない場合を比較すると,応じない場合の方が逃亡や証拠隠滅の危険は高いと理解されるのが通常です。そのため,呼び出しに応じることは,それだけで逮捕の必要が低いと理解してもらえる有益な行動と言えるでしょう。
なお,自転車窃盗事件では,以下のような場合に逮捕される可能性が高い傾向にあります。
例外的ではありますが,呼び出して話を聞いた段階で初めてこれらのケースに該当すると分かった場合には,逮捕リスクが高くなることも考えられます。もっとも,それは呼び出しに応じたことが原因ではなく,そもそもの事件の内容が原因ではあるため,やはり呼び出しに応じるべきであることに変わりはないでしょう。
自転車窃盗事件で警察が呼び出すタイミングや方法
①被疑者特定後の取調べ目的
自転車窃盗事件では,盗難が発覚した段階では被疑者が分からず,その後の捜査で被疑者を特定できるに至る場合が多く見られます。そして,捜査機関が被疑者を特定した場合には,取調べのためにその被疑者を呼び出すことが一般的です。
この呼び出しは,被疑者が捜査機関を特定した後,あまり期間を空けずに行うことが通常です。具体的な時期は捜査に着手した時期等にもよりますが,事件後1~3か月間程度が目安になりやすいでしょう。
呼び出した際には,被疑者が認めるかどうか,認める場合にはどのような話をしてくれるか,という点を確認し,その後の捜査方針を決定することが見込まれます。呼び出しは,警察担当者から携帯電話等への電話連絡が行われることが一般的でしょう。
②現場の実況見分のため
自転車窃盗事件の捜査としては,事件現場の位置関係を具体的に把握することが必要です。事件現場を直接確認する捜査を「実況見分」と言いますが,実況見分に際しては被疑者を同席させ,被疑者に説明をさせながら確認を進めることが多く行われます。
そのため,事件の発生現場で実況見分を行う際には,呼び出しを受けることが見込まれやすいでしょう。
実況見分のための呼び出しは,取調べで一通りの話を聞いた後になされることが通常です。取調べの内容を踏まえて実況見分を行い,その結果を実況見分調書の形で証拠化することが目的であるためです。
具体的な呼び出しの時期は,捜査機関のスケジュールにも影響を受けますが,必要な取調べの後1週間~1か月ほどの時期が目安になりやすいでしょう。
③盗品の提出を求めるため
自転車窃盗の事件で最も重要な証拠は,実際に窃盗の対象となった自転車です。そのため,盗品である自転車が確保できるのであれば,捜査機関としては必ず一度手にし,写真撮影等して証拠化をすることになります。
また,盗難自転車は所有者の手元に返す必要があるところ,被疑者から直接被害者に返させるわけにはいかないため,一度警察で預かり,警察から被害者に手渡すのが通常です。
そのため,窃盗された自転車を被疑者が所持している場合には,その提出を求めるために呼び出されることが想定されます。
呼び出しの時期は,所持していることが分かってから間もないタイミングであることが通常です。日程の都合がつけられない等の事情がない限り,基本的には自転車の提出を優先して進めることになるでしょう。
呼び出しに関する基礎知識
警察が呼び出す主な目的
警察から呼び出しを受ける場合,その目的には主に以下のようなケースが考えられます。
①参考人である場合
参考人とは,特定の事件について捜査の参考とすべき情報を持っているであろう人を言います。具体例としては,事件の目撃者や,被疑者の同僚・友人といった近しい人物,会社で犯罪が起きた場合の従業員などが挙げられます。
参考人の呼び出しは,犯罪捜査のために必要な情報を参考人から教えてもらうために行われるものです。参考人は捜査や処罰の対象となることが想定されていないため,逮捕をされたり前科が付いたりすることは通常ありません。
②身元引受人である場合
身元引受人とは,文字通り被疑者の身元を引き受ける人を言います。身柄を拘束しない事件(=在宅事件)の場合,捜査機関は被疑者の任意の出頭を求めることになりますが,出頭をより確かに見込めるように,適任者を警察署に呼び出し,身元引受人となることを求める取り扱いが広く行われています。
身元引受人は,同居家族(配偶者や親など)であることが一般的です。同居家族に適任者がいない場合は,勤務先の上司や被疑者の依頼した弁護士が身元引受人になることもあります。
身元引受人に対する呼び出しは,通常,被疑者の初回の取り調べが終了した後に行われます。捜査機関から身元引受人に電話連絡がなされ,被疑者を連れて帰ることと身元引受人になることが依頼される,という流れが一般的です。
身元引受人は,被疑者の監督者というのみの立場であるため,呼び出しに応じても逮捕されたり前科が付いたりすることはありません。また,呼び出しに応じなかったとしても特に問題が生じることはありません。
③被疑者である場合
被疑者とは,犯罪の嫌疑をかけられている者をいいます。ニュースなどでは「容疑者」と呼ばれますが,法律的には「被疑者」が正しい呼び方となります。
被疑者を呼び出す目的は,犯人候補として取調べを行うことに尽きます。犯罪の疑いを認めるかどうか,認める場合には具体的に何をしたか,などを確認し,記録化するために,被疑者を警察署へ呼び出します。
被疑者として呼び出される場合,事件の内容や状況によっては逮捕される可能性も否定できません。また,犯罪事実が明らかになれば,刑事処罰を受けて前科が付く可能性もあり得ます。
| 参考人 | 身元引受人 | 被疑者 | |
| 呼び出しの理由 | 事件の情報獲得 | 被疑者の出頭確保 | 犯人候補の取り調べ |
| 逮捕の可能性 | 通常なし | なし | あり |
| 前科の可能性 | 通常なし | なし | あり |
警察の呼び出しを拒むことは可能か
警察の呼び出しには強制力がありません。そのため,呼び出しを拒んだとしても法的にペナルティを科せられることはなく,その意味では呼び出しを拒むことはどのような場合でも可能,ということになるでしょう。
もっとも,立場によって呼び出しを拒むことにリスクや問題の生じる可能性はあり得ます。
①参考人の場合
参考人は,捜査への協力を依頼されている立場に過ぎないため,呼び出しに応じなかったとしてもリスクを抱えたり問題が生じたりすることは通常ありません。
ただし,「現在は参考人にとどまる取り扱いだが,犯罪への関与が疑われる可能性がある」という状況の場合には,呼び出しに応じないことのリスクが生じ得ます。呼び出しに対して積極的な協力や情報提供を尽くす場合に比べると,呼び出しを拒んで捜査協力を一切しない場合の方が,より強く犯罪の関与を疑われやすい傾向にあるためです。
そして,具体的な犯罪への関与を疑われた場合,今度は参考人でなく被疑者として,呼び出しを受けるなどの捜査が行われる可能性も否定はできません。
そのため,呼び出しを拒むことで犯罪への関与を疑われかねない場合には,拒むリスクが生じ得ると言えるでしょう。
②身元引受人の場合
身元引受人は,犯罪への関与が想定されていない立場の人物であるため,呼び出しを拒むことで犯罪の疑いをかけられるものではありません。
もっとも,同居している被疑者の身元引受人となるよう求められ,これを拒んだ場合,被疑者に不利益が生じる可能性は考えられます。身元引受人が拒んだから逮捕をする,ということはあまりありませんが,所在確認のために警察が自宅に訪れることは珍しくありません。そうすると,周囲の人々に警察と関わっている事実が分かってしまい,私生活に影響を及ぼす恐れがあり得ます。
被疑者が同居の家族であって今後も同居を予定している,という場合には,可能な限り身元引受人としての呼び出しに応じる方が無難なケースが多いでしょう。
③被疑者の場合
被疑者に対する呼び出しは,取り調べを行うための方法の一つとして行われるものです。この点,捜査機関が被疑者の取り調べを行う方法は,逮捕して強制的に行うか,呼び出しをして任意の出頭を求めるかの二択であることが通常です。
被疑者を取り調べる方法
1.逮捕をして強制的に行う
2.呼び出して任意の出頭を求める
この点,呼び出しても任意に出頭してくれないとなると,取り調べをするためには逮捕をするほかない,という判断になる可能性もあり得ます。二択のうち一方がダメであった以上,もう一方の方法が取られるのは自然なことであるためです。
そのため,被疑者として呼び出しを受けた場合,可能な限り応じることが適切になりやすいでしょう。もちろん,あまりに回数が多かったり,あまりに時間が長かったりという場合には,その点の配慮を求めることは全く問題ありませんが,呼び出しを徹頭徹尾拒む,というスタンスを取って被疑者自身が得をすることはあまりないと考えるのが適切です。
ポイント 呼び出しを拒む行動の注意点
参考人の場合,拒むことで事件への関与を疑われないように注意
身元引受人の場合,同居する被疑者への不利益に注意
被疑者の場合,拒んだことで逮捕を誘発する可能性に注意
呼び出された場合に弁護士へ依頼するメリット
被疑者として警察に呼び出された場合には,弁護士に依頼をすることが有益になりやすいです。具体的には,以下のようなメリットが生じます。
①逮捕を回避できる
呼び出しがなされた場合,そのまま逮捕されるというケースも否定できないところです。呼び出しに応じた流れで逮捕されると,その後に弁護士への相談や依頼をすることは困難となり,一定期間の身柄拘束を強いられてしまいます。
この点,呼び出された段階で弁護士に依頼し,弁護士を通じて適切な対応を取ることで,逮捕を回避できる場合があります。具体的に逮捕を回避するための手段は,ケースによっても異なりやすいため,弁護士と十分に相談するようにしましょう。
②不適切な取り調べを防げる
警察に呼び出された際の取り調べは,捜査担当者のやり方によっては違法・不適切なものになる場合もあり得ます。強く恫喝されたり,侮辱的な発言を受けたりと,取り調べがヒートアップするほど精神的苦痛を伴うケースが珍しくありません。
この点,弁護士に依頼をしている場合,捜査担当者による不適切な取り調べは多くの場合で防ぐことが可能です。これは,捜査担当者が,弁護士の目があることに配慮するためです。
不適切な取り調べを行えば,後から弁護士を通じて問題視される可能性があるため,不用意な取り調べは行えない,というわけです。
弁護士の目を光らせる意味でも,呼び出しに際して弁護士に依頼することは有力な手段でしょう。
③前科を防げる
被疑者として呼び出される場合,その後に起訴されて前科が付く可能性を想定する必要があります。被疑者として呼び出されるということは,自分に対して捜査が行われていることが明らかであるため,その先に控える処分に無関心でいるわけにはいきません。
この点,呼び出しという早期の段階で弁護士に依頼することで,適切な弁護活動を尽くしてもらい,前科を防げる可能性が高くなります。被害者のいる事件であれば被害者との示談を目指す,否認事件であれば自分が犯人でないことを主張するなど,個別のケースに応じた適切な弁護活動を通じて,前科を防ぐ試みができるのは大きなメリットになるでしょう。
自転車窃盗事件の自首
自転車窃盗事件で自首をするべき場合
①現行犯で発覚している場合
自転車窃盗事件は,現行犯で被害者や目撃者に発覚している場合,速やかな捜査で被疑者の特定に結びつく可能性が高くなりやすい傾向にあります。自転車窃盗の捜査が難航したり長期化したりするのは,主に事件の発覚が遅れてしまい,客観的な証拠が残っていない場合が挙げられますが,現行犯で発覚している場合には,証拠が散逸している可能性が低く,被疑者の特定が実現しやすいのです。
自首は,捜査がなされれば自分が被疑者と特定される,という場合に,先手を打って行うことで特に高い効果を発揮する動きです。自首をしなくても自分が被疑者と特定されてしまうのであれば,それに先立って自首をすることで,刑事処分の軽減が図れることになります。
そのため,自転車窃盗事件が現行犯で発覚したものの,その場を逃れてきたという場合には,後になって自分が被疑者と特定される可能性を踏まえ,自首をするメリットが大きくなりやすいでしょう。
ポイント
現行犯で発覚した自転車窃盗は,被疑者の特定に至りやすい
②反省・後悔の意思を表明したい場合
自転車窃盗事件の刑事処分は,反省や後悔といった情状面の事情が大きく影響することもあります。特に,被害の規模が小さいケースや,盗品の自転車が被害者の手元に戻ったため実質的な損害がないケースなどでは,反省の深さを考慮して不起訴処分を検討する余地も生じ得ます。
この点,反省や後悔を行動として表明する際の有力な手段が自首です。自首は,自らの犯罪行為を捜査機関に申告するものであって,刑事処罰を受けるリスクを背負った行為であるため,大きなリスクを背負ってでも反省の意思を表明したい,という気持ちがあると理解してもらうことが可能な動きです。自転車窃盗事件では,自首を行うほど反省を深めた被疑者である,ということを理由に不起訴処分とされることも少なくはありません。
反省の気持ちを具体的な行動に移したい場合には,自首をするメリットが非常に大きくなるでしょう。
ポイント
自転車窃盗の場合,自首が不起訴処分の理由となるケースもある
③周囲への発覚を防ぎたい場合
自首は,自ら捜査機関へ出頭する代わりに,事件の捜査をできるだけ穏やかな方法で行ってもらうことを期待する動きでもあります。自首をしない場合には家宅捜索などが必要と考えられるケースでも,自首をしているのであれば任意の提出に委ねてよい,と判断される可能性が高くなります。
自首をしている以上,証拠隠滅の恐れは想定しづらく,強制的な証拠収集の捜査を行う必要はないと判断してもらいやすいのです。
捜査方法が穏やかなものになれば,捜査を受けていることや事件の存在・内容などが周囲に発覚する可能性は非常に低くなります。一般的に,事件が周囲に発覚するのは,逮捕された場合や警察が自宅に来た場合などが代表例ですが,それらが行われず,周囲に発覚するきっかけが生じなければ,家族や職場などへの影響を防ぎながら解決を目指すことができるでしょう。
ポイント
自首をした場合,強制的な捜査は行われにくくなる
自転車窃盗事件で自首をする場合の注意点
①捜査を誘発する可能性
自首は,自ら捜査機関に捜査を求める行為であるため,メリットが大きい反面リスクも小さくはありません。この点,自首の代表的なリスクは,自首をしたばかりに捜査を誘発する結果になり得る,という点です。
自分の中では,自首しなくても捜査が行われ,やがて自分の犯罪が明らかになってしまうという流れを思い描いていたとしても,実際が異なる場合はあり得ます。被疑者の特定に必要な証拠が不足していたり,そもそも捜査が開始されていなかったりすれば,自首が捜査のきっかけとなる可能性は否定できません。
自首を試みる場合には,自首が捜査を誘発する結果になってもやむを得ない,という発想で行うことが望ましいでしょう。
②捜査のスタートライン
自首は,あくまで捜査のスタートラインであって,その後に行われる捜査の方がむしろ刑事手続のメインになります。自首は心理的負担も大きいため,「無事に自首ができたから一段落」と感じてしまいがちですが,適切ではありません。自首が成立したことに満足し,その後の捜査対応をおろそかにしては本末転倒と言わざるを得ないため,十分に注意しましょう。
③自首先の判断
自首を行う場合には,どの警察署に対して行うべきか,警察署のどの課に対して行うべきか,という点に注意するとより円滑な手続が見込まれやすくなります。
自首を行う警察署の場所としては,基本的に事件発生地を管轄する警察であることが望ましいでしょう。具体的に事件の捜査を行う場合,事件発生地を管轄する警察が担当することになりやすいためです。
もっとも,住居地と事件発生地が遠く離れている場合には,事件発生地への自首が困難であるため,自宅の最寄りにある警察署でも問題はありません。
また,自首先に関しては,窃盗事件であるため刑事課(盗犯係)にするべきとも思えますが,逮捕勾留のない事件では,地域課の管轄とされていることが少なくありません。個別のケースに際しては,警察に問い合わせて直接確認するのが端的でしょう。
自転車窃盗事件の自首は弁護士に依頼すべきか
自転車窃盗事件の場合,自首をするかどうか検討をしている状況であれば,弁護士に相談・依頼をして専門的な判断を仰ぐことが有益でしょう。また,実際に自首を試みる場合には,弁護士に委任をして,警察とのやり取りを可能な限り弁護士に進めてもらうことが非常に有効です。
自転車窃盗事件の自首に関して,弁護士に依頼する具体的なメリットとしては,以下のような点が挙げられます。
①事件の法的な整理ができる
自転車窃盗事件は,事件の具体的な内容によって窃盗罪や占有離脱物横領罪など,該当する罪名が異なる可能性があります。また,自転車を乗り捨てる行為が犯罪に該当しないケースもあり得るため,自分の行為のうちどの点がどの犯罪に該当し得るか,という整理は意外に難しいものでもあります。
自首の検討をするためには,前提として自分のどの行為がどの犯罪に当たるのかを理解していなければなりません。自首は自分の犯罪事実を申告するものである以上,犯罪事実が分からないというわけにはいかないためです。
この点,弁護士に依頼をすることで,その点の法的な整理は全面的に弁護士へ委ねることが可能になるでしょう。あわせて,犯罪事実の内容を踏まえた自首のメリットデメリットを正確に理解することも容易になります。
②適切な手順で自首ができる
自首を行うとなった場合,では具体的に何をするのか,ということが明確にイメージできる人は少ないでしょう。自首という言葉やその意味は何となく分かるものの,実際に自首をするにはまずどうすべきか,と問われるとよく分からないことが多いはずです。
自首は,捜査機関に捜査を求める動きであって,対応する捜査機関にはやむを得ず負担が生じるものであるため,捜査機関に配慮した手順や流れで行うことが適切です。自首に際して,捜査機関への適切な配慮ができていれば,逮捕回避や処分軽減といった自首のメリットは受けやすくなるでしょう。
この点,弁護士に依頼をし,弁護士が主導する形で自首を進めることによって,捜査機関への配慮と円滑な自首を両立することが可能です。弁護士が必要なやり取りを代わりに行ってくれるため,負担の軽減につながる効果も大きいでしょう。
③示談の試みができる
自転車窃盗の事件では,示談の成否が最終的な処分結果を左右しやすい傾向にあります。そのため,刑事処分の軽減を目指して自首を行うのであれば,続けて示談の試みに移行することが適切でしょう。自首のみをして示談を試みないというのは,合理的な動きとは言い難いところです。
この点,示談の試みは,弁護士に依頼し,弁護士を窓口にして行う必要があります。裏を返せば,自首の段階で弁護士に依頼している場合,既に窓口となる弁護士がいるため,速やかに示談の試みを進めることが可能になります。
速やかに示談ができれば,それだけ速やかな事件解決にもつながるため,そのメリットは非常に大きくなるでしょう。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
特設サイト:藤垣法律事務所