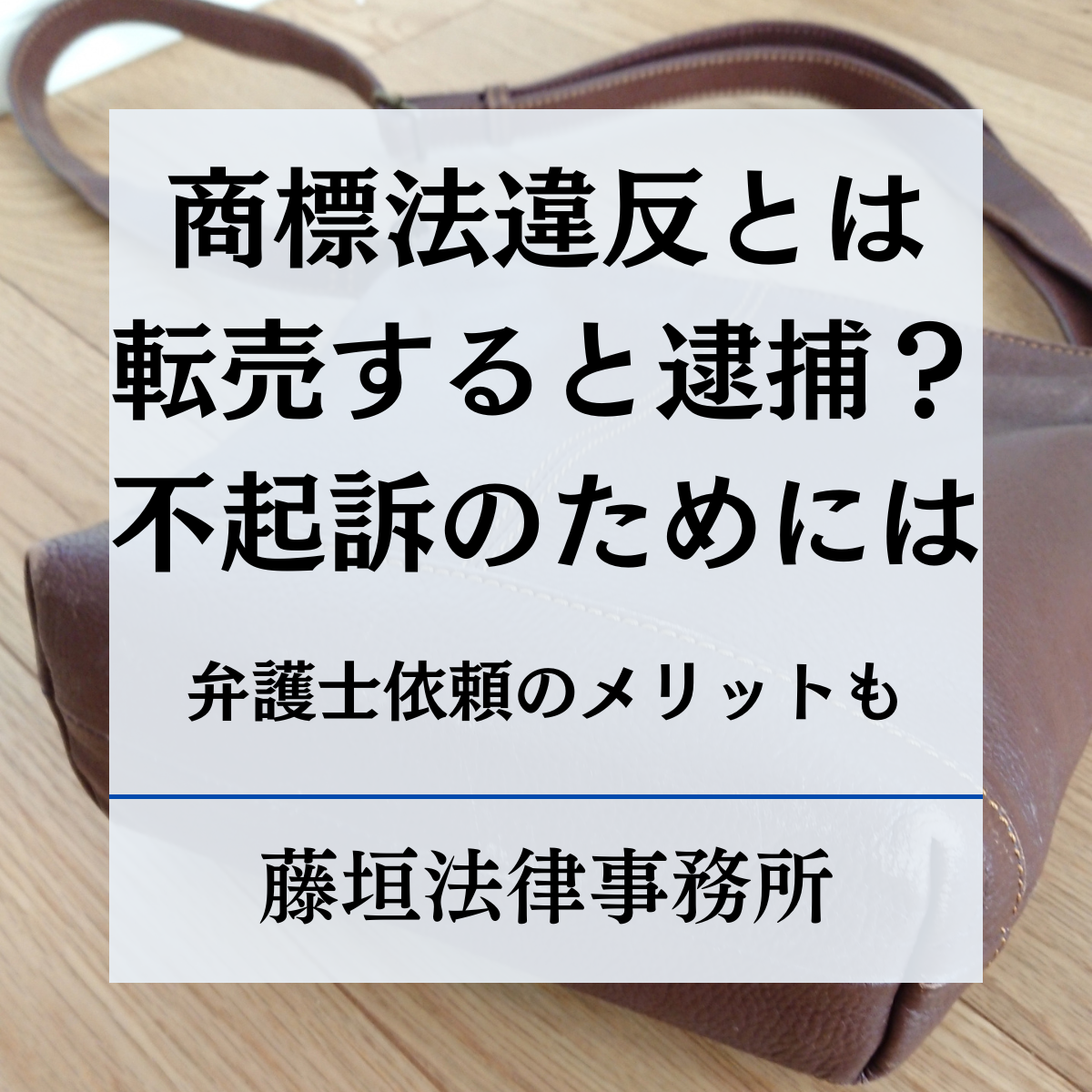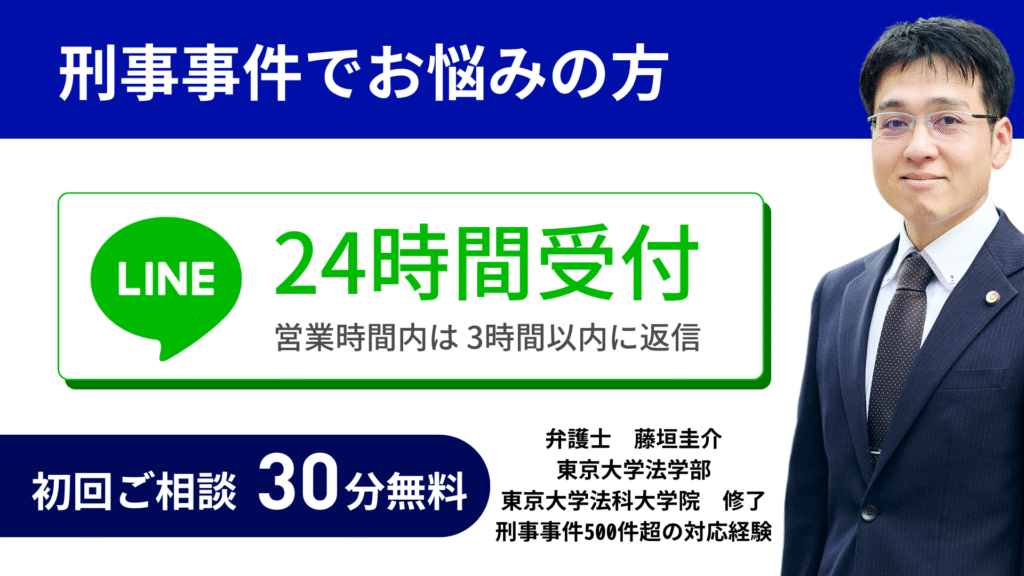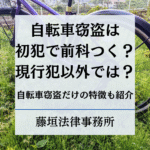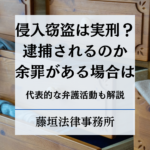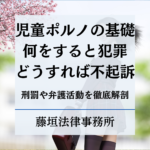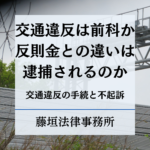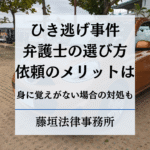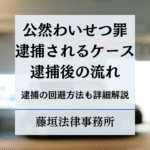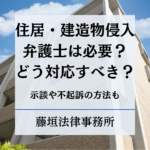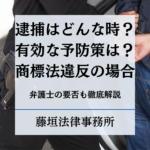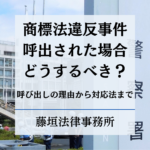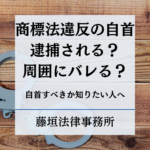「自分のビジネス名が他社と被っているかもしれない」
「商標法違反ってどこからがアウトなの?知らずに使ってたらどうなるの?」
そんな不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
商標法違反は、たとえ悪意がなくても、他者の登録商標を無断で使用していれば違反と判断される可能性があります。
最悪の場合、民事上の損害賠償だけでなく刑事罰を受けるケースもあるため、早めの確認と対策が必要です。
本記事では、商標法違反の定義や商標法違反で刑事事件になるとどうなるのか、刑事事件化する流れなどを詳しく解説します。
この記事の監修者

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
商標法違反とは
①商標法違反の意味
商標法違反は、他人の商標権を侵害した場合に成立する犯罪です。
商標というのは、事業者が、自身の取り扱う商品やサービスを他社のものと区別するために用いる目印となるものです。簡単に言うと、企業ロゴのことを指すのがほとんどでしょう。
商標は、その企業の商品が持つブランドイメージの象徴であり、商品を見た人は、商品中の商標を基準に商品への信頼を持つでしょう。ブランド品のバッグや財布などはその代表例です。
商標は、特許庁に申請して商標登録をすることで、排他的に(他人に用いられることなく)使用することができます。商標登録によって、自分たちの築き上げたブランドイメージにタダ乗りされないよう予防しているわけですね。
商標法違反というのは、そのように他人がブランドイメージを作った企業ロゴを、勝手に自分のものとして利用する行為を指します。なお、厳密には、ロゴなどの文字列のみでなく、図形や模様、記号、色彩やパッケージの形状なども商標登録することが可能です。
②商標法違反の具体的行為
商標法違反となる具体的な行為には、以下のようなものが挙げられます。
| 偽造品の作成・販売 | 企業ロゴを模倣したニセ物を作成・販売する行為 |
| 類似商標の使用 | 他の商標に似せて作成した商標を使用する行為 |
| 同一商標の無断使用 | 商標権者の許諾を得ることなく、その商標を使用する行為 |
近年では、ネット上で広く物品の販売ができるようになった影響もあり、商標を無断使用した商品や類似商標を使用した商品をネット上で販売する事件が増加傾向にあります。
また、海外で類似商標を使用した安価な商品を購入し、それを国内で転売する行為が問題になるケースも少なくありません。
ポイント
商標法違反は,他人の商標(ロゴなど)を無断利用する行為
商標法違反で科される刑事処罰
商標法違反の罰則
商標法違反の基本的な罰則は、「10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金又はその併科」とされています。
罰金額の上限が非常に高額であること、罰金刑と拘禁刑の併科が可能であることが大きな特徴です。
また、商標権行為の準備行為に対しては、「5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はその併科」の罰則が科せられます。
加えて、商標法違反が法人の業務として行われた場合には、行為をした個人に科される刑罰のほか、法人にも3億円以下の罰金が科せられる可能性もあります。
なお、個人と法人の両方を処罰することのできる定めを、両罰規定といいます。
商標法違反の刑罰は、罰金刑の高い上限額や両罰規定などによって、大きな金銭的負担を内容とするものになっています。
商標法違反の一般的な刑事処分
商標法違反は、規模の限定的な個人の事件であれば、罰金刑の対象となることが多く見られます。他から購入した偽造品や類似商標の商品を販売した、という一般的な商標法違反事件であれば、30~50万円ほどの罰金刑が一つの目安になるでしょう。
もっとも、余罪が多い場合、共犯者が多く計画性の高い場合、犯罪による収益の規模が大きな場合など、より刑罰が重くなるケースも少なくありません。特に、法人を設立し、事業として行っているような場合だと、代表者や実行した者個人への処罰に加え、法人にも多額の罰金が科せられることにより、トータルの金銭制裁が非常に大きな金額となることも考えられます。
商標法違反で刑事事件になるとどうなる?

商標法違反は民事上の損害賠償請求だけにとどまらず、悪質な場合には刑事事件として扱われる可能性があります。刑事事件になる流れは、主に以下の通りです。
- 家宅捜索が行われる
- 逮捕される
- 警察で取り調べされる
- 執行猶予がつくか実刑判決が下される
詳しく解説します。
家宅捜索が行われる
商標法違反が疑われると、捜査機関は証拠収集のために家宅捜索を行うことがあります。
これは刑事事件における初期段階の重要な措置であり、裁判所の発行する捜索差押許可状に基づいて行われます。
捜索対象となるのは、自宅、会社の事務所、倉庫、パソコンやスマートフォンなど、違反行為に関係する可能性があるあらゆる場所です。
捜索の際には、違法な商標を使用した製品や契約書類、メールの履歴などが押収されることが多く、ここで集められた証拠が後の取り調べや裁判に大きく影響します。
また、捜索が行われるタイミングは早朝であることも多く、精神的な動揺や社会的信用への打撃は計り知れません。
捜査対象となった時点で、既に重大な疑いがかけられていると認識する必要があります。
逮捕される
商標法違反が悪質かつ継続的であると判断された場合、刑事事件として被疑者が逮捕されることがあります。
逮捕の要件としては、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると捜査機関が判断した場合です。
逮捕された場合、最大で72時間は警察に拘束され、その後、検察官による勾留請求が通れば、さらに10日から最大20日間拘束が続きます。
この期間、被疑者は外部との連絡が制限されることがあり、企業経営者や事業主であれば、業務への支障が出ることは避けられません。
さらに、報道等により社会的信用が失われ、取引先や顧客からの信頼を失うリスクも高まります。
商標法違反が刑事罰の対象であるという認識が甘い場合、こうした深刻な展開に至ることがあるのです。
商標法違反の場合、決して逮捕されるケースの方が多いとは思われませんが、体感的には2~3割程度のケースで逮捕される印象です。
警察で取り調べされる
逮捕後、もしくは任意の事情聴取として、警察による取り調べが行われます。
取り調べでは、なぜその商標を使用したのか、相手企業の存在を認識していたのか、類似性についてどう認識していたのかなど、詳細な経緯が追及されます。
特に重要なのは、違反行為に対して「故意」があったかどうかであり、商標法における刑事責任を問う際の判断基準です。
捜査官は、取り調べを通じて自白を得ることを重視しますが、ここでの供述内容は後の裁判にも大きな影響を与えます。
不適切な発言や曖昧な説明は不利な判断材料となり得るため、弁護士を通じた適切な対応が求められます。
取り調べの過程で否認を続ける場合でも、押収された証拠と照合されることで矛盾点が浮き彫りになることもあるため、対応には慎重さが必要です。
執行猶予がつくか実刑判決が下される
商標法違反で刑事裁判にかけられた場合、有罪が確定すれば「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」、もしくはその両方が科される可能性があります。
初犯で悪質性が低いと判断された場合には、執行猶予付きの判決が下されることが多いですが、組織的な犯行や再犯、被害金額が大きい場合などは、実刑判決となる可能性も十分にあります。
執行猶予がついたとしても前科は残り、社会的信用の回復は容易ではありません。
また、法人が関与していた場合には、法人自体にも罰金刑が科され、企業活動に甚大な影響を及ぼします。
商標法違反は「知らなかった」では済まされず、たとえ善意であっても厳しい責任が問われる可能性があるため、事前のリスク管理が必要です。
前科がない初犯のケースであれば、多くは執行猶予判決になりやすいでしょう。適切な対応を尽くすことで、経験的には8割程度のケースで執行猶予判決になる印象です。
商標法違反が刑事事件化する流れ

商標法違反が刑事事件化するケース
商標法違反が刑事事件となる場合には、以下のようなケースがあります。
①商品の購入者が警察に通報する
購入した商品が商標を模倣した偽造品であった場合、その購入者が警察に通報する方法で捜査が始まるケースです。
このケースでは、販売者が正規品として販売していることが大多数であるため、正規品であるか模倣品であるか、正規品でなかった場合にその認識が販売者にあったかなどが問題になりやすいです。
②侵害行為を知った商標権者が警察に捜査を求める
侵害行為が生じている事実を知った商標権者が、自らの被害を警察に申告した場合です。
権利者地震の被害深刻であるため、犯罪事実が明らかに存在しない場合でない限りは被疑者に対する十分な捜査が行われやすい傾向にあります。、
③サイバーパトロール
警察によるサイバーパトロール中に、商標法違反の事実を発見したケースです。
いわゆるネットフリマ等で偽造品や類似商標が確認された場合、これをきっかけに捜査が開始され、刑事事件化する場合があります。
④内部告発
主に法人として商標法違反の行為がなされている場合に、その内部事情を把握する人が警察等の捜査機関に告発するケースです。
ポイント
商標法違反の刑罰は両罰規定の存在が特徴
捜査の主なきっかけは購入者の通報,商標権者の通報,サイバーパトロール,内部告発
商標法違反の捜査
商標法違反における捜査の方法としては、捜索が先に行われる場合が多く見られます。電話連絡や呼び出しなどされることなく、自宅や事業所などに立ち入り、保管されている商品などを強制的に差し押さえる捜査手法です。
商標法違反の事件は、偽造品や類似商標の用いられた商品などが被疑者の管理下にある場合、捜索によってその存在を証拠かすることが極めて強力な犯罪の証拠となります。また、捜査の当初段階で把握できる違反行為には限りがあり、その全体像を把握することは容易でないため、実際の商品や取引履歴・内容を網羅的に確認することで、証拠隠滅の防止や余罪の発見を可能にする意味もあります。
このような捜索・差し押さえは、事前に被疑者へ通知していたのでは証拠隠滅の機会を与えることになりかねないため、被疑者側への通知を行うことなく、証拠隠滅の猶予を与えない方法で強制的に行うのが一般的です。
商標法違反事件で弁護士に依頼するメリット
①適切な取り調べ対応のため
刑事事件の捜査では取調べが不可欠です。特に,被疑者への取調べは捜査の中核であって,被疑者からどのような話が引き出せるかによってその後の捜査が決定づけられる事件も少なくありません。
逆に,被疑者の立場にある場合,取調べにどのような対応を取るのが最も有益であるのかを把握していることは非常に重要です。自分が何を話すか,どのように話すかによって,その後の捜査や処分が決定づけられる可能性もあるため,取調べ対応の方法・内容は十分に検討する必要があるでしょう。
特に,商標法違反の場合には,犯罪の故意の有無が問題になるケース,余罪の捜査が生じるケースなど,取り調べへの対応が結果を左右する局面は類型的に多くなりやすいところです。
商標法違反事件に対応する場合には,取調べ対応への重要性を踏まえ,弁護士から適切なサポートを受けるようにしましょう。
②早期釈放のため
商標法違反の事件で逮捕された場合,早期釈放を目指すことは有力な選択肢です。短い拘束期間のみで釈放されることができれば,日常生活への悪影響は最小限に抑えることが可能になります。
もっとも,その具体的な動きは,弁護士以外には困難なものです。接見で必要な話し合いを行ったり,ご家族と連絡を取り合ったり,捜査機関や裁判所に必要なアクションを尽くしたりと,早期釈放に向けて弁護士でしかできないことは多岐に渡ります。
また,商標法違反の事件では,そもそも早期釈放が困難な事件も少なくないため,弁護士に判断を仰ぐなどして,釈放に関する見通しを正しく持つことも不可欠です。
③刑事処分の軽減のため
商標法違反の場合,認め事件であれば,刑事処分を少しでも軽減するための試みを行うことが適切です。漫然と対応していては刑罰を防ぐことが難しい事件類型であり,場合によっては重大な刑罰の対象ともなりかねないため,処分の軽減に向けた弁護活動を依頼することは非常に重要となるでしょう。
この点,刑事処分の軽減のため,具体的にどのような試みを行うのかは,個別の事件を踏まえた専門的な判断が必要となります。また,弁護活動によってどのような刑事処分が見込まれるのか,という見通しを持つことも不可欠です。
これらの判断や見通しは,弁護士に委ねることが最も適切であるため,処分軽減を目指す場合には弁護士選びが必要と言えます。
④家族や周囲との連携のため
身柄事件の場合,逮捕勾留されたご本人は,自分で外部と連絡を取ることができません。電話を携帯することも認められないため,連絡を取るための手段は以下のような方法に限られます。
逮捕勾留中に外部と連絡を取る手段
1.手紙の送受
→数日~1週間ほどのタイムラグが避けられない
2.(一般)面会
→時間制限が厳しい。接見禁止の場合は面会自体ができない
3.弁護士の接見
→時間的制限なくコミュニケーションが可能
手紙の送受は現実的でなく,面会の時間制限の中で必要な連絡をすべて取ることも難しいため,ご本人と周囲との連絡には弁護士の接見を活用することが不可欠になりやすいでしょう。
身柄事件で必要な連絡を取り合うためには,弁護士への依頼が適切です。
弁護士に依頼するタイミング

①自首を試みるとき
自首とは,罪を犯した者が,捜査機関に対してその罪を自ら申告し,自身に対する処分を求めることをいいます。犯罪事実や犯人が捜査機関に知られる前に,自分の犯罪行為を自発的に捜査機関へ申告することが必要とされます。
そのため,自首は,事件の発覚や犯人の特定に時間を要しやすいケースで,特にその時間的な猶予が生じやすいものです。
この点,商標法違反の事件は,違反行為が発覚するまでに時間がかかりやすい,という点に大きな特徴があります。多くの場合,商標法違反に当たる商品の販売などがきっかけになりやすいですが,商品が販売されたからと言って,直ちに違反行為が発覚するわけではないためです。
その意味では,商標法違反の事件は自首の検討が有力になりやすい事件類型と言えます。
もっとも,本当に自首をすべきかどうか,自首をする場合にどのような手順・方法で行うか,という点は,当事者自身での判断が困難なポイントです。自首を試みようと考えるときには,適切な弁護士選びの上で,弁護士とともに検討・行動をするのが適切でしょう。
そのため,自首を試みたいと考えるときは,弁護士選びのタイミングということができます。
ポイント
商標法違反の事件は,自首が有力になりやすい
自首すべきかの判断,自首する場合の方法は,弁護士に委ねることが適切
②捜索を受けたとき
商標法違反の場合,被疑者に対する捜査は捜索から始まることが非常に多く見られます。商標法違反の証拠となる商品が保管されている可能性が高いため,家宅や事業所の捜索を行い,商品の差押えを行うことが優先されやすいのです。
そして,捜索を受けて商品の差し押さえがなされた後,取り調べなどの本格的な捜査が始まることとなります。
そのため,商標法違反の事件で捜索を受けた際には,その後の捜査に対する備えを検討したり,刑事処分を少しでも軽減するための行動に着手したりすることが望ましいと言えます。これらの動きは,弁護士なしでは現実的に困難であるため,弁護士選びを行うべきタイミングということができるでしょう。
ポイント
商標法違反に対する捜査は,捜索から始まるケースが多い
捜索後の捜査に対応するため,弁護士選びを行うべきタイミング
③呼び出しを受けたとき
商標法違反の事件で取り調べを行う場合には,逮捕せず呼び出す方法が用いられるケースも多数見られます。特に,あらかじめ捜索差押えをしている,証拠となる商品が確保できているなど,今後に証拠隠滅される可能性が低いと言える状況であれば,逮捕せず呼び出す形になりやすいでしょう。
そのため,呼び出しを受けたときには,その後に行われる取調べへの対応を事前に検討しておく必要があります。商標法違反の場合には,対象となる行為や証拠が一つしかないというケースはほとんどないため,複数の出来事について,それぞれどのような対応をすべきかを想定することが非常に重要です。
しかしながら,出頭後の取り調べに対してどのように対応するのが適切かを自分の力で整理するのは容易でありません。取り調べを受けた経験のある人でなければ,取り調べがどのように行われるかを想像することも困難でしょう。
そこで,呼び出しを受けて取り調べの予定が明らかになったタイミングで,弁護士を選ぶことが有力な選択肢になります。適切な弁護士選びができれば,出頭時の対応が万全になるほか,その後の弁護活動も充実したものになるでしょう。
ポイント
逮捕せず取調べ目的で呼び出す方法が用いられる場合も多数ある
取り調べに備えるためには,取調べに精通した弁護士選びが適切
④逮捕されたとき
商標法違反事件は,逮捕をされる可能性も十分に考えられる事件類型です。特に,違反行為の数や期間が際立っている場合,違反行為による損害が非常に大きい場合,組織的,計画的な事件である場合など,捜査に慎重を期す必要が大きい事情があるケースでは,被疑者を逮捕勾留の上で捜査することが多くなります。
そのため,逮捕された商標法違反事件では,その後に捜査される内容が多くなりやすく,対応を要するポイントも多くなるのが通常です。そのすべてに適切な判断をすることは非常に難しく,弁護士の助言やサポートを受けながら対応することが望ましいでしょう。
逮捕されてしまったケースでは,家族をはじめとする周囲の人ができるだけ早期に弁護士選びを進め,その後の不利益を最小限に抑えることを目指すのが適切です。
ポイント
逮捕された場合は,特に対応を要する点が多くなりやすい
適切な対応を判断するため,弁護士選びが望ましいタイミング
商標法違反事件の弁護士を選ぶ基準
①商標法違反の弁護に精通しているか
商標法違反の事件は,弁護活動に他の事件類型とは異なる特徴が複数あります。刑事事件の代表的な弁護活動である示談一つを取っても,示談の相手は誰なのか,誰との間であれば示談が可能か,誰と示談をすると処分結果にどのような影響があるか,といった点を検討しなければなりませんが,これは商標法違反の特徴と言えるでしょう。
商標法違反の弁護士を選ぶ際には,商標法違反事件の弁護活動について十分な知識を持っているか,事件類型の特色に精通しているか,といった点を重要な判断基準とすることをお勧めします。
②詳細な聴き取りを円滑に行ってくれるか
商標法違反とされる具体的な事件としては,商標権を侵害した商品を入手し,販売したというケースが非常に多く見られますが,商品の入手方法,販売方法は人により様々です。また,商品の数や取引の回数,得られた利益の大きさなど,事件の全体像を把握しなければ,適切な見通しを持つことも困難です。
そのため,商標法違反事件の弁護活動を行う場合には,事件の詳細な内容をはじめ,経緯などの周辺事情を適切に聴き取ることが不可欠です。
弁護士選びに際しては,弁護士が事件の把握に必要な情報を,円滑に聴き取ってくれるかという点を基準の一つとするのが適切でしょう。聴き取りの円滑さは,商標法違反の事件への経験値を推し量る判断材料にもなります。
③具体的な対応方針を説明してくれるか
商標法違反の場合,弁護活動の方針にいくつかの選択肢があるケースも少なくありません。特に,余罪を含めた複数の事件が問題になりやすいことから,一つの事件だけでなく複数の事件それぞれについて方針を検討する必要があり,それだけに選択肢も多くなりやすい傾向にあります。
もっとも,どの選択肢が客観的に正しいかは不明確であって,結果が出た後でも正しい選択だったかは分からない,というケースは多く見られます。その中で,どのような理由でどのような方針を取っていくのか,という判断が,商標法違反の事件を弁護する弁護士の大きな役割と言えるでしょう。
そのため,商標法違反の弁護士選びに際しては,弁護士が今後の対応方針を詳細に判断してくれるか,その方針を取る理由やメリットは何か,といった点について,十分な説明を受けるようにしましょう。その説明内容を踏まえて,弁護士選びを行うことが有力です。
④弁護士費用の見通しは明確か
商標法違反の事件は,逮捕などの身柄拘束を受けるかどうか,捜査にどの程度の期間を要するか,どのような動きを要するか,といった点を事前に判断することが容易でありません。そして,期間が長く,必要な活動が多くなれば,事前の想定よりも弁護士費用が高くなる可能性はあり得ます。
もっとも,想定される弁護士費用が分からない,という状態で弁護士選びをするわけにはいきません。そのため,弁護士費用については,どのような場合にどの程度の費用となりやすいか,といった形で見通しを把握できることが望ましいでしょう。
裏を返せば,依頼者目線を踏まえてできる限り費用の見通しを明確にしてくれるかどうか,という点は,弁護士選びの重要な判断基準の一つと言えます。
刑事事件に強い弁護士をお探しの方へ
商標法違反の事件は,その内容や捜査に至った経緯などによって,有効な対応策が変わってくることのある事件類型です。
そのため,商標法違反に精通した弁護士への相談や依頼ができなかった場合,有益な対処をする機会を逃してしまう可能性も高いと言えます。
商標法違反の事件でお困りの場合は,弁護士へのご相談をお勧めします。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
早期対応が重要となりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
特設サイト:藤垣法律事務所