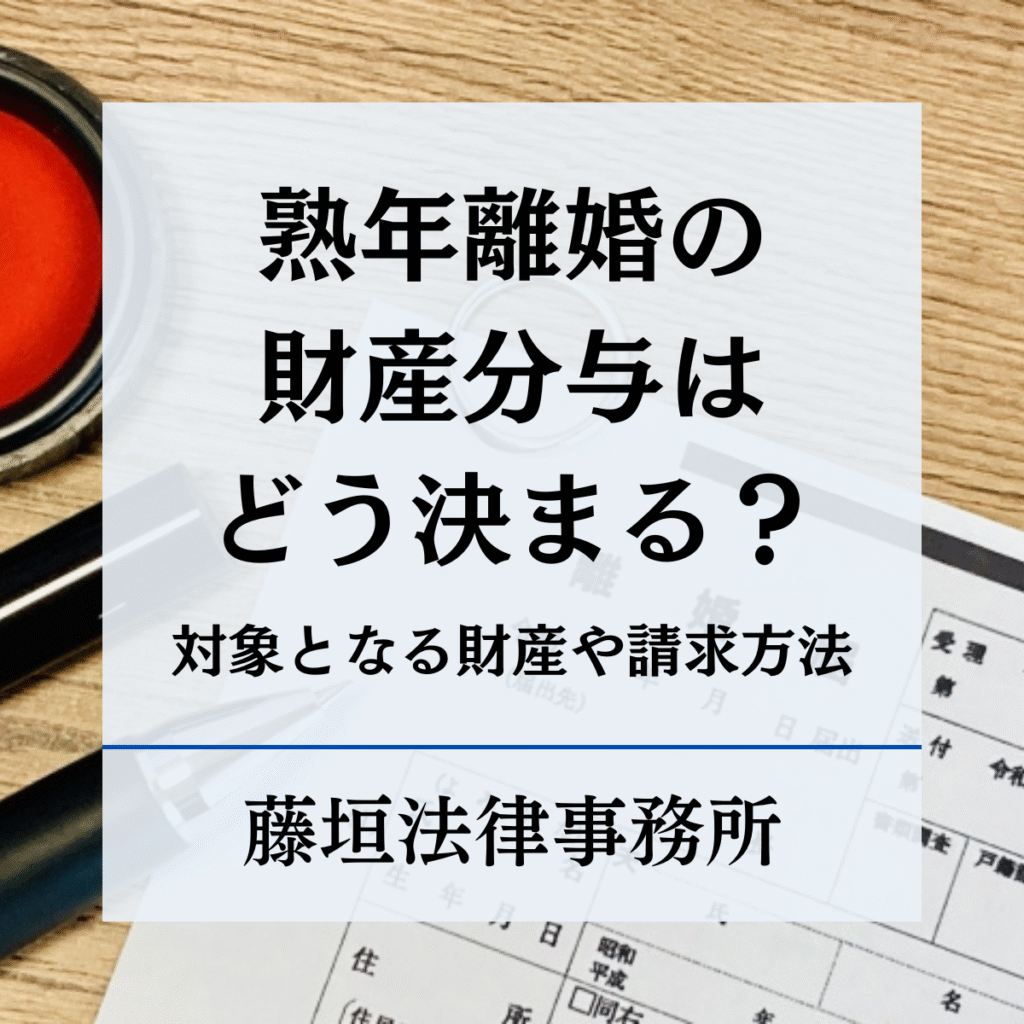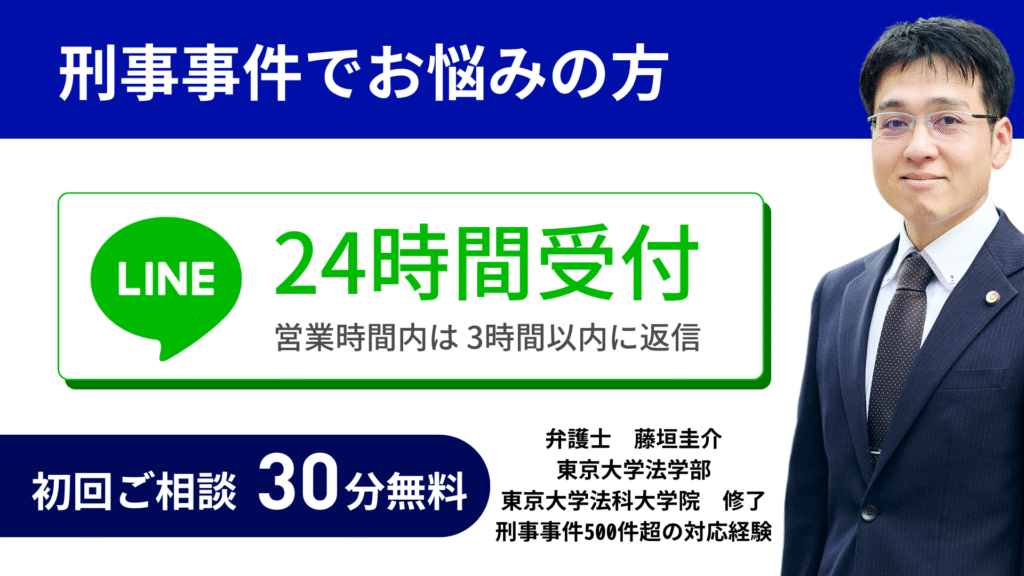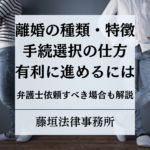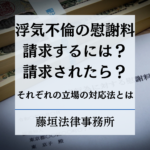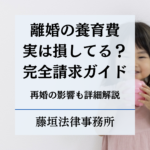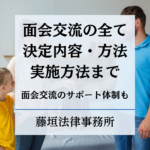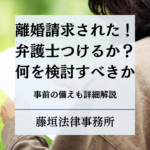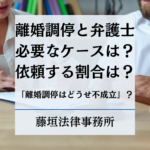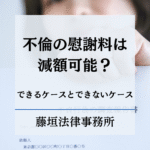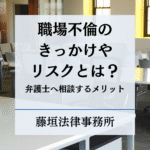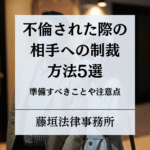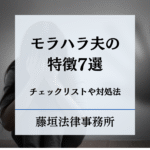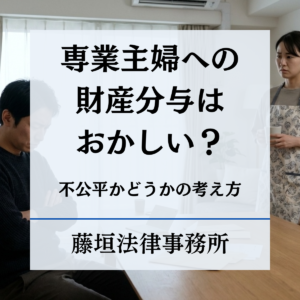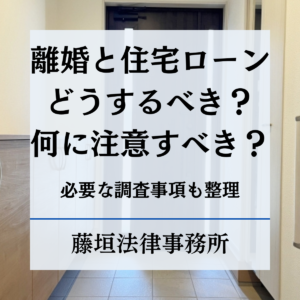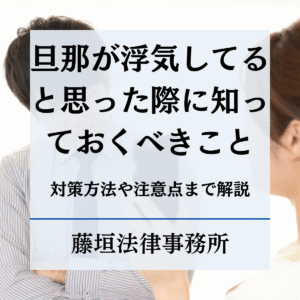「熟年離婚を考えているけれど、財産分与ってどうなるの?」
「退職金や年金も分けるの?」
このような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。
熟年離婚における財産分与は、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を原則として半分ずつ分け合うことになります。
ただし、退職金や年金など将来に関わる資産も対象となるため、正しい知識を持つことが重要です。
そこで本記事では、熟年離婚における財産分与の基本的な仕組み、割合や種類、対象となる財産の範囲について詳しく解説します。
藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。
この記事の監修者

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
熟年離婚すると財産分与はどうなる?

熟年離婚では、長年にわたる共同生活で形成された財産を公平に分けることが求められます。
ここからは、熟年離婚の財産分与について詳しく解説します。
財産分与の割合
熟年離婚における財産分与の割合は、原則として「2分の1ずつ」が基本とされています。
これは夫婦が共に築いた財産は、収入を得た側だけでなく、家事や育児、介護など無償労働を担った側の貢献も等しく評価されるという考え方に基づいています。
たとえば、夫が長年会社で働き給与を得ていたとしても、その背景には妻の家事や子育ての支えがあったと認められるため、財産は折半が妥当と判断されるのです。
ただし、例外的に一方が特別な資産形成に大きく貢献した場合や、極端に短期間の婚姻であった場合には、裁判所が5対5ではなく6対4や7対3などと判断するケースもあります。
形式的に2分の1ずつ分けることがかえって不公平である場合には、財産分与の割合が変更されることもあり得ます。夫婦の一方が特に浪費をしていた場合や、逆に一方が特に財産形成に貢献した場合などが一例です。
財産分与の種類
財産分与には大きく分けて3つの種類があります。
| 目的 | 内容 | |
| 清算的財産分与 | 婚姻中に築いた財産を公平に分ける | 不動産、預貯金、車、証券などを原則2分の1ずつ分配 |
| 扶養的財産分与 | 離婚後の生活を支えるため | 経済的に弱い側に生活費や補助金を分与 |
| 慰謝料的財産分与 | 精神的損害の補償 | 不貞行為や暴力などが原因の際に上乗せされる |
表で整理したように、財産分与と一口に言っても、単に財産を折半する清算的財産分与だけで完結するわけではありません。
熟年離婚における財産分与は「公平な精算」「生活保障」「精神的損害の補填」という三つの側面を持ち合わせているのです。
どの観点が自分のケースに当てはまるのかを理解しておくことで、相手との協議や調停に臨む際に主張すべきポイントが明確になるでしょう。
熟年離婚に伴う財産分与の対象となるもの

熟年離婚において財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産です。
ここからは、財産分与の対象となるものを詳しく解説します。
家や土地
熟年離婚において大きな財産となりやすいのが家や土地といった不動産です。
婚姻中に住宅ローンを組んで購入した場合、その返済に夫婦双方が協力してきたと評価され、原則として財産分与の対象となります。名
名義が夫や妻のどちらか一方にあっても、生活基盤として共に維持してきたことから、分配対象とみなされます。
不動産の分与方法は、売却して現金を分ける「換価分割」、一方が住み続けて他方に代償金を支払う「代償分割」、共有名義のまま持ち続ける「共有分割」といった方法があります。
熟年離婚では子どもの独立に伴い住宅を手放すケースが多いですが、高齢期の住まいは生活の安心に直結するため、単にお金に換えるのではなく、どちらが住み続けるかを慎重に判断する必要があります。
また、ローンが残っている場合は債務の処理も重要な検討課題となるでしょう。
預貯金
預貯金は現金化が容易で分割しやすいため、財産分与の代表的な対象です。
夫婦いずれかの名義であっても、婚姻中の収入から積み立てられたものであれば公平に分けることになります。
熟年離婚では数十年にわたる生活費の余剰や退職金の一部が預金として蓄えられている場合が多く、その金額は生活設計に大きく影響します。
注意すべきは、離婚を見越して一方が預金を隠したり引き出したりするケースがあることです。
この場合、過去の通帳記録や金融機関の取引履歴から調査が行われるため、財産開示を求める準備が欠かせません。
生活の基盤となる資金だからこそ、正確に把握し、公平に分けることが重要です。
自動車
自動車も婚姻中に取得したものであれば財産分与の対象になります。とくに地方に居住している場合は生活に欠かせない資産であり、その価値は無視できません。
評価の方法は、中古車市場の相場や査定額を参考にするのが一般的です。配分方法としては、使用頻度が高い側が引き取り、もう一方に代償金を支払う形が多く見られます。
熟年離婚では生活拠点が変わることが多いため、車が本当に必要かどうかを再考する機会にもなります。
維持費や今後の生活動線を踏まえ、所有を続けるか処分するかを冷静に検討することが望まれます。
家電や家具
家電や家具といった生活用品も原則として財産分与の対象になりますが、実務上は中古価値が低いため大きな争点にはなりにくいのが特徴です。
冷蔵庫や洗濯機、テレビなどは購入時は高額でも、数年経つと価値が大幅に下がるため、分与対象に含めても実際の評価額はわずかです。
ただし、生活に不可欠なものが多いため、誰がどの品を引き継ぐかを協議で決める必要があります。
熟年離婚では新たな生活拠点を整える必要があるため、家電や家具をどう分けるかは生活の立ち上げに直結します。
金銭的価値よりも実用性を重視して分配を決めることが現実的です。
貴金属
貴金属や高級時計、美術品などは換金性が高く、財産分与の対象として重要な位置を占めます。
とくに熟年夫婦の場合、長年の結婚生活で指輪や宝飾品を購入してきたケースが多く、価値が高額になる場合もあります。
注意点は、これらが「個人の装飾品」として扱われるか「財産」として扱われるかの線引きです。
一般的に高額な貴金属は資産として扱われ、分与対象となります。売却して現金を分けるか、一方が所有し代償金を支払う形で処理することが多いでしょう。
評価には専門の鑑定が必要になることもあり、正しい価値を知ったうえで分与方法を検討することが大切です。
証券や債券
株式や投資信託、国債や社債などの有価証券も婚姻中に取得したものであれば財産分与の対象です。
証券類は市場価格の変動があるため、分与時点の評価額で計算されます。
熟年離婚では長期的に投資を続けてきた資産が多額になっている場合があり、その扱いは慎重に行う必要があります。
売却して現金化する方法のほか、一方が証券口座を引き継ぎ、他方に代償金を支払う方法も1つの手段です。
証券会社の取引履歴や残高証明を取り寄せ、資産状況を明確にすることが重要です。資産分配に不透明さを残さないことが、後のトラブル回避につながります。
退職金
退職金は熟年離婚で特に大きな争点となる財産です。将来の生活費や老後資金として位置づけられるため、分与の対象とすべきかどうかが議論されやすい部分です。
判例では、退職金がすでに支給済みであれば当然に財産分与の対象となり、まだ受け取っていない場合でも退職が近いと予測されるときには対象とされることがあります。
分与割合は他の財産と同様、原則は2分の1ずつです。老後の生活を左右する重要な資産であるため、請求の有無によって将来の安心度が大きく変わります。
正確に算定し、必要に応じて専門家に相談することが欠かせません。
おすすめの記事:不動産を生前贈与するメリット・デメリットは?税金や手続きを分かりやすく解説
熟年離婚に伴う財産分与の対象外のもの

熟年離婚といえども、すべての財産が分与の対象になるわけではありません。
対象外となる財産も存在し、その範囲を理解しておくことがトラブル防止につながります。ここでは代表的な3つの財産について解説します。
婚姻前に保有していた財産
婚姻前から個人が保有していた財産は、原則として分与の対象外です。
たとえば、結婚前に購入した不動産や預貯金、車、株式などは夫婦の共同生活によって形成されたものではないため、相手が請求することはできません。
熟年離婚では婚姻期間が長いため、この区分が曖昧になりがちですが、購入時期や名義を明確に示す資料を準備することが大切です。
遺産相続した財産
親からの相続によって取得した不動産や預貯金、株式などは、原則として個人の特有財産とされ、財産分与の対象になりません。
ただし、相続財産を生活費や住宅ローン返済に充てた場合には、その一部が実質的に共有財産とみなされるケースもあります。相続財産の性質を正確に区別することが重要です。
別居してからそれぞれで保有した財産
夫婦が別居を開始してからそれぞれが得た収入や資産は、財産分与の対象外です。
別居は婚姻関係が実質的に破綻したとみなされるため、その後の収入や購入した財産は個人のものとして扱われます。
熟年離婚の場合、別居期間が長期に及ぶこともあるため、別居開始時点を明確にすることが重要です。
熟年離婚に伴う財産分与の請求方法

財産分与は単に対象財産を明確にするだけでなく、その分け方をどう決めるかが重要です。ここからは、熟年離婚に伴う財産分与の請求方法を詳しく解説します。
夫婦間で協議する
一般的な方法は、夫婦間の協議によって分与内容を決めることです。財産の範囲や分配方法について冷静に話し合い、合意が得られれば比較的スムーズに解決できます。
協議書を作成し、公正証書化しておくと、後々のトラブルを防ぐ効果があります。
熟年離婚では財産が多岐にわたるため、協議の際にはリスト化して一つずつ確認することが有効です。
離婚調停や離婚裁判で決める
協議が難航した場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるのが流れです。調停では中立の立場にある調停委員が間に入り、合意の有無をサポートします。
それでも合意できなければ裁判に移行し、裁判所が分与方法を決定します。熟年離婚は財産規模が大きいため、調停・裁判に発展するケースも少なくありません。
法的手続きに進む場合は、弁護士への依頼が必要となるでしょう。
熟年離婚に伴う財産分与の期限は離婚成立から2年まで
財産分与には請求期限があり、離婚成立から2年以内に行わなければなりません。この期間を過ぎると、法律上は請求できなくなるため注意が必要です。
熟年離婚の場合、財産の種類や範囲が広いため、調査や協議に時間がかかる傾向があります。したがって、離婚手続きと並行して財産分与の準備を進めることが求められます。
とくに退職金や年金分割など老後生活に直結する資産は早めの手続きが必要です。期限を軽視せず、早い段階から行動を起こすことが将来の安心につながります。
まとめ:熟年離婚の財産分与は早めの準備が安心
熟年離婚における財産分与は、不動産や預貯金といった基本的な資産から、退職金や年金といった老後に直結する資産まで幅広く含まれます。
割合は原則2分の1とされますが、婚姻期間や貢献度によって変動する場合もあります。
重要なのは、離婚成立から2年以内という期限を守り、早期に財産調査と証拠整理を行うことです。
老後の生活設計に直結する問題だからこそ、準備を怠らず専門家の助言を得ながら進めることが、安心して新しい生活を始めるための鍵となるでしょう。
藤垣法律事務所では、離婚・男女問題に精通した弁護士が在籍しており、迅速対応により最適な解決方法をご提案いたします。下記からぜひご相談ください。