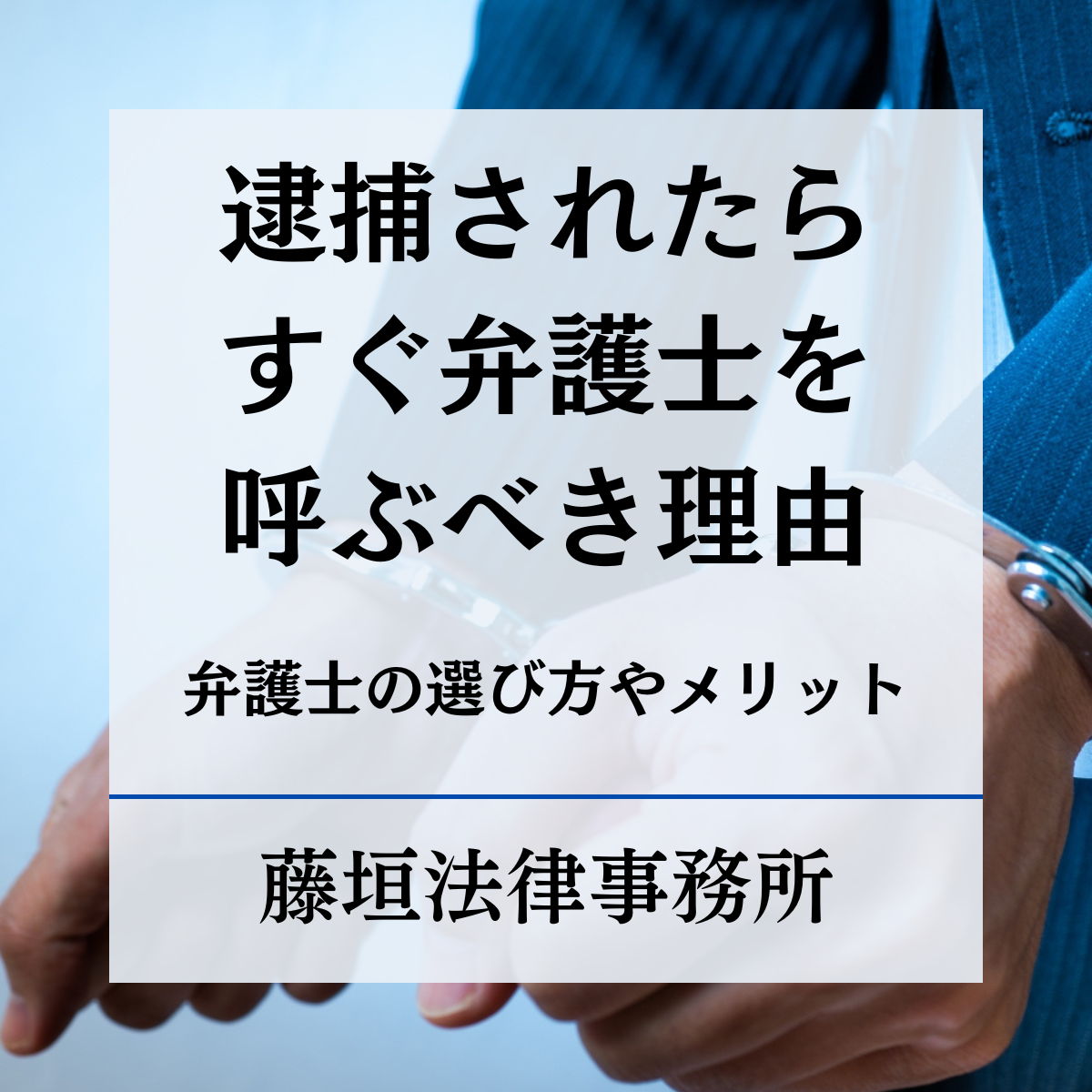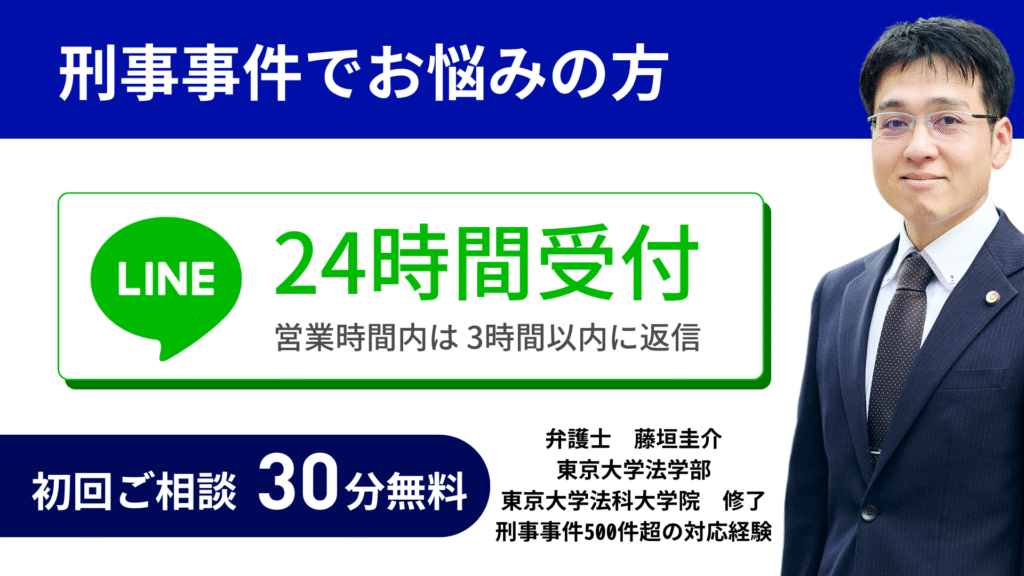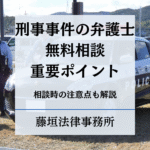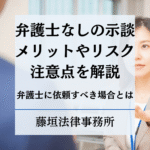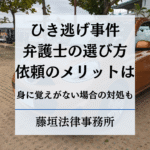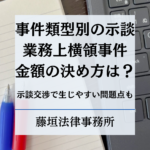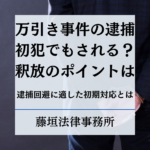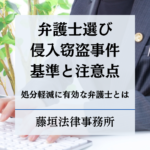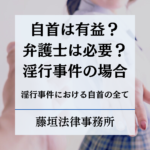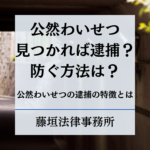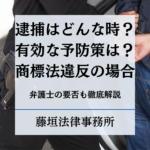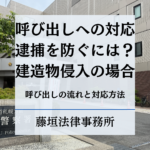突然の逮捕は、本人だけでなく家族にも大きな衝撃と不安をもたらします。警察の取調べが進む中で、誤った対応をしてしまうと不利な状況に陥ることもあります。こうしたときに最も重要なのが、できるだけ早く弁護士を呼ぶことです。弁護士は逮捕後の手続きや取調べへの対応、早期釈放や不起訴のための交渉などを行い、あなたの権利を守ります。本記事では、逮捕されたときになぜ弁護士をすぐ呼ぶべきなのか、逮捕後に弁護士を呼ぶべき理由や具体的な呼び方、相談の流れを詳しく解説します。
この記事の監修者

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
逮捕後に弁護士を呼ぶメリット

① 早期釈放を目指すため
逮捕後に弁護士を呼ぶ最大の理由は、早期釈放を実現するためです。
逮捕されると最大72時間の身柄拘束が始まりますが、この期間中に適切な対応を取れば釈放される可能性があります。
弁護士は逮捕直後から警察や検察との交渉を開始し、勾留請求の阻止に向けて動きます。
弁護士が早期に介入した場合、早期釈放目指すための具体的な対応としては、以下のような動きが可能です。
・身元引受人の手配と身元引受書の作成
・証拠隠滅や逃亡の恐れがないことの立証
・検察官に対する勾留請求回避の意見書提出
・被害者との示談交渉の開始
特に初犯や軽微な事件では、弁護士の適切な対応により勾留を回避できるケースが多くあります。
逮捕から最大72時間以内に検察官が勾留請求を行うかを判断するため、この期間が勝負となるでしょう。
早期釈放が実現すれば、社会復帰への影響を最小限に抑えることができます。
勾留に関する判断を行う検察や裁判所に対して、彼らが把握していない重要な情報を提供していくことができれば、早期釈放の可能性が飛躍的に高まるケースも少なくありません。その他、同居家族が身元引受を行う具体的な方法を示していくことも、釈放してよいとの判断を促す有益な試みになり得ます。
② 学校や職場への発覚を防ぐため
逮捕されると、学校や会社に知られてしまう可能性が高まります。
弁護士を呼ぶことで、周囲への発覚を最小限に抑えられる可能性があります。
弁護士の具体的な対応としては、以下の内容が挙げられます。
・警察との交渉により不必要な連絡を防ぐ
・早期釈放を目指し身柄拘束の期間を短縮する
・報道機関への情報漏洩を防ぐための依頼や要望を行う
・職場や学校への適切な説明方法をアドバイスする
弁護士には守秘義務があるため、弁護士への相談内容が外部に漏れることはありません。
また、家族を通じて職場への連絡調整も可能です。
逮捕が長期化すれば、無断欠勤や無断欠席として扱われ、解雇や退学のリスクが高まります。
弁護士の迅速な対応により、社会復帰への道筋を確保することが重要です。
逮捕があった場合に学校や職場へ情報共有すべきかどうかは判断の難しい問題です。個別の内容や状況、ご本人のお立場などを踏まえた弁護士の意見を仰ぐことが望ましいでしょう。
③ 不利な供述調書の作成を防ぐため
逮捕後の取り調べでは、供述調書という重要な書類が作成されます。
この調書は裁判で証拠として使われるため、内容によっては有罪判決に大きく影響する可能性があります。
弁護士がいない状況では「早く帰りたい…」という気持ちから、捜査官の誘導に応じて事実と異なる内容に署名してしまうケースが少なくありません。
供述調書は一度作成されると後から撤回することが極めて困難で、不利な内容が記載されれば裁判で不利な立場に追い込まれてしまう恐れがあります。
弁護士は取り調べ前に以下のアドバイスを提供できます。
・事実と異なる内容には署名しない方法
・捜査官の誘導的な質問への適切な対応
・黙秘権の行使タイミング
・調書の内容確認時のチェックポイント
また、弁護士は接見を通じて取り調べの状況を把握し、不当な圧力がかかっていないか監視する役割も果たします。
適切な法的助言により、事実に基づいた正確な供述調書の作成が可能となり、後の裁判で有利な展開を期待できるでしょう。
④ 示談を行うため
逮捕後に示談を成立させることは、起訴を回避し前科を避けるために極めて重要です。
示談とは、被害者との間で損害賠償などの条件を取り決め、事件を民事的に解決することを指します。
特に窃盗や傷害などの被害者がいる事件では、示談の成立が検察官の起訴判断に大きく影響するでしょう。
示談の中に被害者が加害者を許す(宥恕する)旨を盛り込めれば、不起訴処分を決定づける要素になることも珍しくありません。
弁護士が示談交渉を行うメリットは以下の通りです。
・被害者との直接交渉を避けられる
・適正な示談金額を判断できる
・法的に有効な示談書を作成できる
・被害者の感情に配慮した交渉が可能
逮捕から起訴までの期間は最大23日間と限られているため、早期の示談成立が重要になります。
弁護士に依頼することで、迅速かつ適切な示談交渉が期待できるでしょう。
刑事事件の示談は、ほとんどの場合、当事者間で直接行うことが困難です。そのため、加害者側の窓口として弁護士が入り、弁護士を窓口に被害者側と示談交渉を行う必要があります。
⑤ 逮捕された本人と家族の連絡役になれる
逮捕された本人は警察署内で身柄を拘束されており、外部との連絡が大幅に制限されます。
この状況で弁護士は、本人と家族をつなぐ重要な連絡役として機能するでしょう。
弁護士は接見を通じて本人の状況や意向を確認し、家族に正確な情報を伝えることができます。
逆に家族からの心配や励ましの言葉、必要な連絡事項も本人に届けられるのです。
「家族に心配をかけているのではないか…」と不安を抱える本人にとって、弁護士を通じた家族との連絡は精神的な支えとなります。
特に長期間の身柄拘束が予想される場合、弁護士による連絡調整は欠かせません。
家族も弁護士から定期的に状況報告を受けることで、適切な対応を取ることが可能になるでしょう。
特に禁じられていない限り、ご本人から家族に文書を発送することもできますが、到着まで長い時間がかかるため迅速な連絡は非常に困難です。また、面会の時間や回数にも限りがあるため、連絡役としての弁護士の役割は大きくなりやすいでしょう。
逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぶべき理由

① 手続の期間制限が厳しい
逮捕後の手続きには厳格な期間制限が設けられており、時間との勝負になります。
警察による逮捕から検察官への送致まで48時間以内、検察官による勾留請求の判断まで24時間以内という短い制限時間が法律で定められています。
この72時間以内に適切な対応を取らなければ、勾留が決定してしまう可能性が高くなるケースも多いです。
勾留が決定されると最大20日間の身体拘束が続き、社会復帰が困難になりかねません。
「もう少し様子を見てから弁護士に相談しよう」と考えていると、あっという間に貴重な時間が過ぎ去ってしまうことも少なくないでしょう。
弁護士は逮捕直後から以下の活動を開始できます。
・勾留阻止のための意見書作成
・検察官との面談による釈放交渉
・被害者との示談交渉の試み
・家族への状況説明と今後の方針相談
特に勾留阻止は逮捕から72時間以内の限られた時間での勝負となるため、一刻も早い弁護士への依頼が成功の鍵を握っています。
時間制限の厳しさを理解し、迷わず専門家のサポートを求めることが重要です。
逮捕から勾留決定までの期間は、都道府県や事件の内容、状況によっても異なることがありますが、早いケースでは逮捕翌日に勾留が決定される場合も数多くあります。逆に、釈放の判断となる場合は逮捕翌日の午前に釈放されるケースもあり、手続は非常にスピーディーです。
② 周囲に発覚した後では取り返しがつかない
逮捕の事実が周囲に知られてしまうと、その後の人生に深刻な影響を与える可能性があります。
逮捕情報は一度広まると完全に消去することは困難でしょう。
職場では懲戒処分や解雇の対象となり、学校では退学処分を受ける恐れもあります。
家族や友人からの信頼失墜、近隣住民からの偏見など、社会復帰への道のりは険しくなってしまいます。
逮捕直後に周囲への発覚を防ぐための弁護活動としては、以下の対応が挙げられます。
・早期釈放に向けた弁護活動により、長期勾留を回避する
・勤務先や学校への連絡を適切にコントロールする
・報道機関への情報提供を最小限に抑制するよう求める
・家族への状況説明と対応策のアドバイス
会社員や学生の場合、逮捕が長引くほど無断欠勤、欠席扱いとなり、発覚リスクが高まります。
弁護士による早期の身柄解放が実現すれば、周囲に気づかれることなく日常生活に戻れる可能性が大幅に向上するでしょう。
周囲に発覚しやすい傾向にある立場や事件もあります。立場としては公務員や著名人、事件としては重大性や社会的影響のある事件が、報道を通じた発覚リスクの高いケースの代表例です。
③ 供述調書を作成すると撤回できない
供述調書は一度作成されると後から撤回することが極めて困難になります。
逮捕後の取調べで警察官や検察官が作成する供述調書は、裁判で重要な証拠として扱われるためです。
「つい認めてしまったけれど、やっぱり違う…」と後悔しても、供述調書に署名・押印した内容を覆すのは非常に困難になりやすいでしょう。
刑事裁判において、裁判官は供述調書の記載内容を重視して判断を下すのが通常です。
特に注意すべき点は以下の通りです。
・取調官の誘導により事実と異なる内容で作成される危険性
・一度署名すると「自分の意思で認めた」とみなされること
・後から「強制された」と主張しても証明が困難なこと
・供述調書の内容が起訴・不起訴の判断材料になること
弁護士がいれば、供述調書の作成前に適切なアドバイスを受けられます。
取調べでの発言内容や署名の可否について専門的な判断を仰げるため、不利な供述調書の作成を防げるでしょう。
供述調書は刑事手続きの根幹を成す重要書類であり、慎重な対応が求められます。
供述調書への署名押印は、調書の内容に誤りがないとお墨付きを与える意味のものです。
内容にお墨付きを与えられない場合や、お墨付きを与えてよいか判断できない場合は、安易に署名押印せず弁護士と協議することも重要な対応です。
④ 示談が手遅れになってしまう恐れ
逮捕後に示談交渉を行うには、限られた時間内での迅速な対応が不可欠です。
逮捕から起訴までの期間は最大23日間しかなく、この短期間で被害者との示談を成立させなければなりません。
示談が成立すれば、検察官が起訴を見送る可能性が高まります。
しかし、時間が経過するほど被害者の処罰感情が強くなり、示談交渉が困難になることも少なくありません。
示談を試みるべき場合は、早期の弁護士依頼が重要です。
刑事事件に精通した弁護士は、被害者との交渉ノウハウを持ち、適切な示談金額の提示や交渉戦略を立てられます。
特に以下のケースでは示談の重要性が増します。
・被害者がいる事件(傷害、窃盗、詐欺など)
・初犯で反省の意思を示したい場合
・前科をつけたくない場合
逮捕後すぐに弁護士に依頼することで、示談交渉の成功率を大幅に向上させることができるでしょう。
示談が成立した、という理由で早期釈放の判断を促せるケースは珍しくありません。示談が成立した場合、その後の被害者への接触が想定されない上、刑事手続は不起訴処分が見込まれやすくなるためです。
⑤ 必要な連絡ができず不利益の生じる可能性
逮捕された本人は、警察署内での身柄拘束により外部との連絡が大幅に制限されます。
この状況下で弁護士がいなければ、重要な連絡を取ることができず、深刻な不利益を被る恐れが高まります。
まず、勤務先への連絡が困難になります。
無断欠勤が続けば懲戒処分や解雇のリスクが生じ、経済的基盤を失うことになりかねません。
学生の場合も同様で、長期間の無断欠席により進級や卒業に影響が出る恐れがあります。
また、家族への状況説明も重要な課題です。
周囲が心配を募らせる中、適切な説明がなければ家庭内の混乱や信頼関係の悪化を招きます。
さらに、被害者との示談交渉の機会を逸する可能性も深刻です。
早期の示談成立は起訴回避や刑の軽減に大きく影響するため、連絡の遅れは致命的な結果をもたらします。
弁護士は本人に代わってこれらの必要な連絡を行い、職場や学校への適切な説明、家族への状況報告、示談交渉の開始など、本人の利益を守るための行動を迅速に実行できます。
連絡の遅れによる二次的被害を防ぐためにも、弁護士の早期依頼が不可欠でしょう。
逮捕後に連絡できる弁護士の種類
① 当番弁護士
当番弁護士は、弁護士会から派遣された弁護士であり、逮捕・勾留中に1回接見を行うことが可能です。
当番弁護士の最大のメリットは、逮捕直後から無料で接見してもらえる点です。逮捕後の初動を誤らないための手段として、有力な選択肢の一つでしょう。
ただし、当番弁護士として派遣される弁護士が、刑事事件の対応に長けているとは限らない点には注意が必要です。弁護士会に登録をしているかどうかが派遣の条件であり、得意分野や専門性が異なる可能性がある点には注意するのが望ましいでしょう。
当番弁護士によるサポートは、初回の接見のみです。引き続き弁護活動を依頼したい場合には、その弁護士と契約をし、私選弁護人になってもらう必要があります。その際の弁護士費用は自己負担となります。
② 国選弁護人
国選弁護人は、経済的に私選弁護人を雇うことが困難な被疑者・被告人のために、国が費用を負担して選任する弁護士です。
国選弁護人制度は、経済状況に関係なく弁護を受ける権利を保障する重要な制度といえます。
逮捕された段階で国選弁護人を利用した場合、以下の2つの条件を満たす必要があります。
・勾留されていること
・資産が50万円未満であること
なお、国選弁護人も当番弁護士と同様、刑事事件に精通しているとは限らない点に注意が必要です。国選弁護人の名簿に登録していれば、最低限の研修を受けるのみで経験を問わず国選弁護人になることが可能です。
国選弁護人は、勾留された後に初めて選任されるため、勾留を防ぐ弁護活動を行う余地がない点には注意が必要です。また、勾留が途中で終了し釈放された場合には国選弁護人の役割も終了することになります。
③ 私選弁護人
私選弁護人は、被疑者やその家族が自由に選択できる弁護士です。
当番弁護士や国選弁護人とは異なり、費用は全額自己負担となりますが、その分多くのメリットがあります。
私選弁護人の最大の特徴は、弁護士を自由に選べることでしょう。
刑事事件に詳しい弁護士や、過去に同種事件で実績のある弁護士を指名できます。
また、費用を支払う分、より手厚いサポートを受けられる可能性が高いです。
「費用が心配だけど、しっかりとした弁護を受けたい」と考える方には、私選弁護人がおすすめです。
初回相談を無料で行っている事務所も多く、まずは相談してから依頼を検討できます。
私選弁護人は、逮捕直後から迅速に対応してもらえるため、早期釈放や示談交渉において有利に働くことが期待できるでしょう。
逮捕直後の段階で釈放に向けた弁護活動を行ってもらう場合には、私選弁護人への依頼が唯一の選択肢となります。できるだけ迅速に信頼できる私選弁護人を見つけられるかどうかは、その後の進行に大きく影響するでしょう。
逮捕後に弁護士を呼ぶ方法
① 当番弁護士
当番弁護士を呼ぶ方法には、以下の2つがあります。
・逮捕された本人が呼ぶ方法
・ご家族や友人が呼ぶ方法
逮捕された本人は、留置場で警察官に希望を伝えれば当番弁護士を呼ぶことが可能です。要望を受けた警察は弁護士会に連絡をし、弁護士会が担当になる弁護士を留置場へ派遣する形を取ります。
ご家族が当番弁護士を呼ぶ場合、ご本人が留置されている警察署がある都道府県の弁護士会に電話をし、本人の氏名や警察署を伝えるとともに、当番弁護士の派遣を依頼します。
依頼後、弁護士会から担当となる当番弁護士が派遣され、接見が行われます。
② 国選弁護人
国選弁護人を呼ぶ場合、被疑者勾留が決定された後、被疑者本人がその希望を表明することが必要です。
多くのケースでは、裁判所での勾留質問やその後の勾留決定の際に、弁護人が付いていなければ国選弁護人の選任希望が問われるため、希望する旨回答すれば足りるでしょう。
なお、その後でも、勾留中であればいつでも希望することができます。
国選弁護人については、本人以外のご家族等が呼ぶ手段はありません。また、国選弁護人の有無や氏名について、ご家族が問い合わせや照会を行っても回答を得ることは難しいでしょう。国選弁護人からの連絡を受けるか、本人と面会して国選弁護人の情報を聞き出すか、という方法が現実的な接触手段になりやすいところです。
③ 私選弁護人
私選弁護人とは、被疑者や家族が自分で選んで依頼する弁護士のことです。
逮捕後に最も柔軟で手厚いサポートを受けられる選択肢でしょう。
私選弁護人を呼ぶ方法は、家族が直接弁護士事務所に連絡を取って依頼するのが一般的です。
被疑者本人が逮捕されている場合、家族が代わりに弁護士を探して契約を結びます。
弁護士会の紹介サービスを利用したり、インターネットで刑事事件に強い弁護士を検索したりして選ぶことが可能です。
逮捕後は、本人がインターネット等を利用して私選弁護人を探すことはできないため、ご家族のサポートが非常に重要となります。
法律事務所によっては、正式な依頼の前に接見だけを行ってもらうサービスを提供している場合も相当数あります。まず接見を依頼し、事件の内容や弁護士の見解を確認した上で依頼を検討することも一案でしょう。

逮捕後にどの弁護士を呼ぶべきか
① 当番弁護士のメリット・デメリット
当番弁護士のメリット
・費用が無料
→経済的負担なく弁護士に相談できます。
・逮捕直後から利用できる
→取調べ開始段階から、適切な対応が可能になります。
当番弁護士のデメリット
・1回限りである
→初回の接見しか依頼することができません。
・弁護士を選べない
→専門性のある弁護士が派遣されるとは限りません。
・弁護活動の依頼には契約が必要
→弁護活動を行ってもらうには、別途私選弁護人の契約を要します。
② 国選弁護人のメリット・デメリット
国選弁護人のメリット
・費用負担の軽さ
→基本的に費用の負担が発生しません。
・全般的な弁護活動を行ってもらえる
→接見のみでなく一通りの弁護活動を担当してもらうことができます。
国選弁護人のデメリット
・弁護士を選べない
→希望した弁護士についてもらうことはできません。
・活動内容が弁護士次第になる
→弁護士の意欲によって希望に沿った弁護活動をしてもらえない可能性があります。
・勾留後にしか利用できない
→釈放された場合には利用できず、勾留を防ぐ弁護活動を依頼することもできません。
③ 私選弁護人のメリット・デメリット
私選弁護人のメリット
・弁護士を選ぶことができる
→信頼でき、刑事事件に長けた弁護士へ依頼することができます。
・いつでも依頼ができる
→勾留前の逮捕段階から依頼できるため、勾留を防ぐための弁護活動も期待できます。
・サポートが充実しやすい
→依頼者の意向に沿った弁護活動を期待することができます。
私選弁護人のデメリット
・弁護士費用の負担が発生する
→相当額の経済的負担を想定する必要があります。
私選弁護人は、依頼者や被疑者の希望、利益を実現する観点では最も適した弁護士と言えます。費用負担が不可能である場合を除き、逮捕されたときは基本的に私選弁護人を選ぶことをお勧めします。
④ 私選弁護人を選ぶときのポイント
私選弁護人を選ぶ際は、刑事事件の経験豊富な弁護士を選ぶことが最も重要です。
刑事事件は民事事件とは全く異なる専門性が求められるため、「どの弁護士でも同じだろう」と考えるのは危険が伴います。
弁護士選びで重視すべきポイントは以下の通りです。
・刑事事件の取り扱い実績が豊富であること
・同種事件での弁護経験があること
・迅速な対応が可能であること
・費用体系が明確で納得できること
・説明が分かりやすく信頼できること
また、弁護士との相性も重要な要素です。
初回相談で質問に対する回答が的確で、今後の見通しを具体的に説明してくれる弁護士なら安心して任せられるでしょう。
適切な弁護士選びが、事件の結果を大きく左右します。
特に、対応の迅速さは法律事務所や個々の弁護士によって大きく差が生じやすい傾向にあります。刑事事件の時間制限や依頼者への誠意に配慮した弁護士であるかどうかは、動きのスピードで判断することも有力でしょう。
逮捕後の弁護士費用
① 当番弁護士の弁護士費用
当番弁護士の利用は基本的に無料です。
逮捕された方やその家族が費用を心配する必要はありません。
当番弁護士制度は、経済的な理由で弁護士に依頼できない方でも法的支援を受けられるものです。
この制度により、逮捕直後の重要な時期に専門的なアドバイスを受けることが可能になります。
ただし、当番弁護士が対応できるのは初回の接見のみという制限があります。
継続的な弁護活動を希望する場合は、以下のいずれかを選択する必要があります。
・国選弁護人への移行を申請する
・私選弁護人として正式に契約する
当番弁護士の接見で事件の概要や今後の見通しを把握することは、経済的に不安のある方にとって貴重な機会になるでしょう。今後の検討にとって重要な判断材料を得らることが可能です。
② 国選弁護人の弁護士費用
国選弁護人の弁護士費用は、原則として国が負担するため被告人の経済的負担は大幅に軽減されます。
ただし、完全に無料というわけではなく、本人に費用負担ができるだけの財力がある、と判断された場合には、一定程度の支払を裁判所から命じられる可能性もあります。
もっとも、国選弁護人の報酬は、国で定める基準に従った金額になるため、私選弁護人と比較すると非常に安価です。
国選弁護人制度は、経済的理由で適切な弁護を受けられない、という人の救済を目的とした制度です。経済的に苦しい方が必要最低限の弁護活動を受けるためのサポートと言えるでしょう。
③ 私選弁護人の弁護士費用
私選弁護人の費用は、弁護士事務所によって大きく異なりますが、一般的な相場を知っておくことが重要です。
着手金は事件の内容により20万円から100万円程度が相場となっています。
軽微な事件では30万円前後、重大事件では100万円を超えることもあるでしょう。
成功報酬は着手金と同額程度に設定されることが多く、不起訴や執行猶予を獲得した場合に支払います。
日当や交通費も別途必要となります。遠方でなければ、裁判所への出廷1回につき3万円から5万円程度が一般的です。
また、示談交渉が必要な事件では、示談成立時に別途10万円から30万円の報酬が必要になることもあります。
費用が高額に思われる場合は、早期釈放や不起訴処分の獲得により得られる利益と比較して慎重に検討するのも有力でしょう。
私選弁護人の弁護士費用は、法律事務所によって大きく異なります。特に理由なく着手金や成功報酬に2倍程度の差が生じることも見受けられます。
可能であれば、複数の法律事務所へ相談を行い、それぞれの費用感を把握することが望ましいでしょう。
刑事事件の逮捕勾留に強い弁護士をお探しの方へ
釈放されるどうか,いつ釈放されるかは,弁護士による活動やそのスピードによって大きく変わります。
逮捕勾留からの釈放に向けた弁護活動に強い弁護士に依頼することで,速やかな釈放を目指すことが非常に重要となります。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,500件を超える様々な刑事事件に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内することができます。
刑事事件は少しでも早い対応が大事になりますので,お困りごとがある方はお早めにお問い合わせください。
特設サイト:藤垣法律事務所