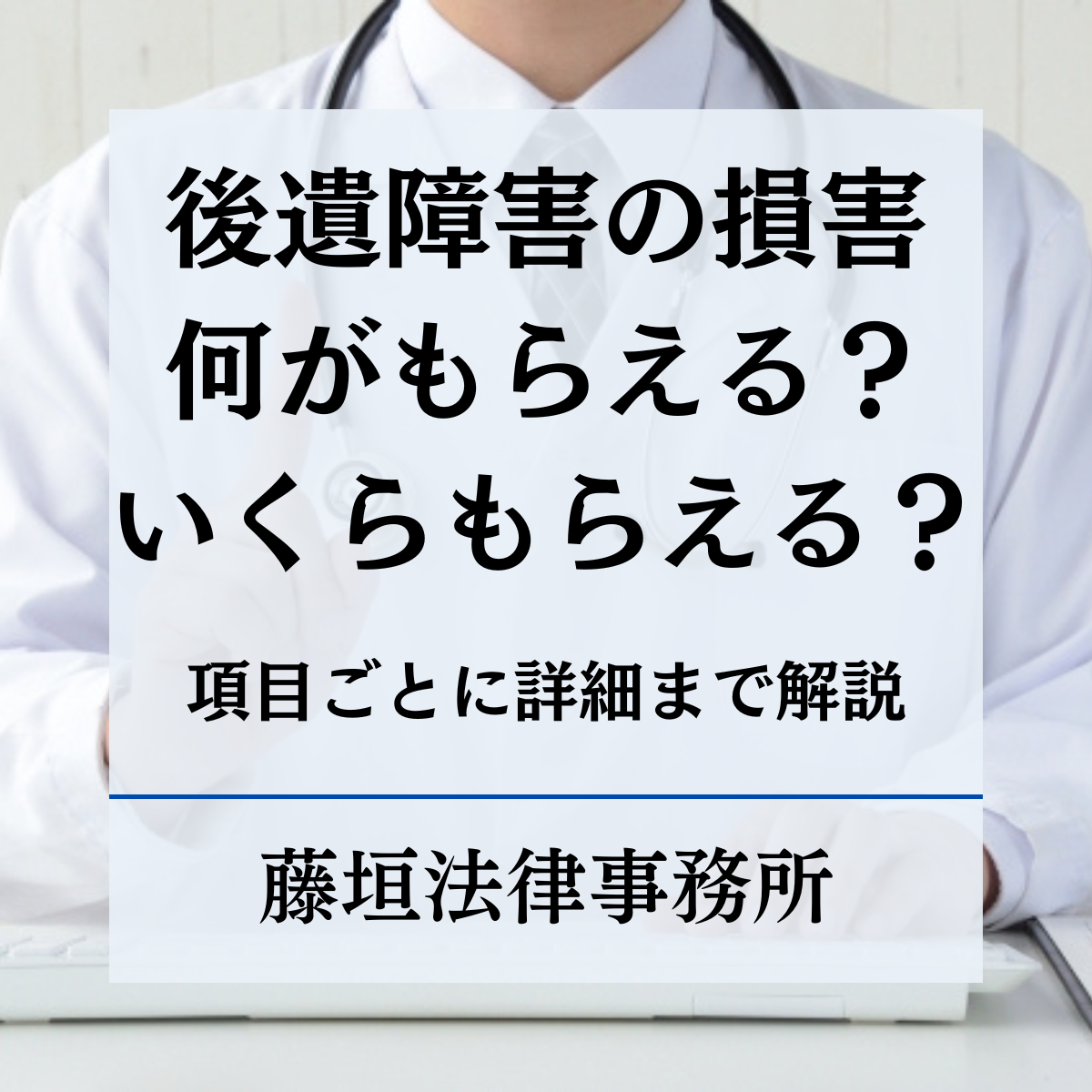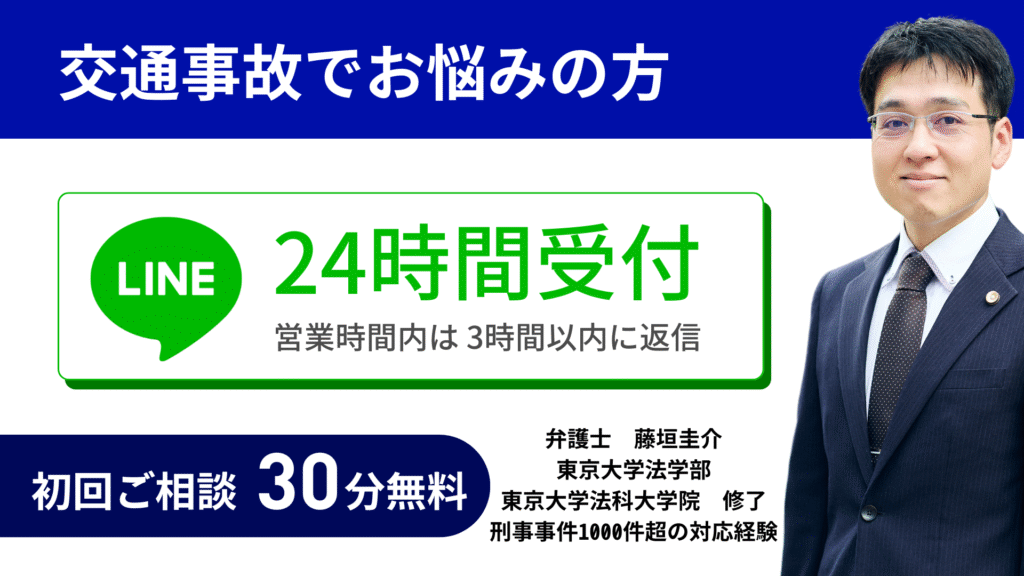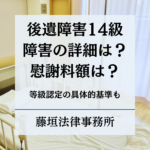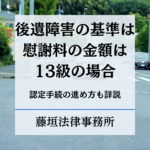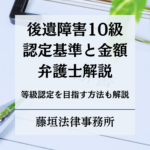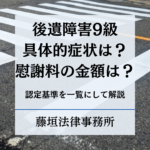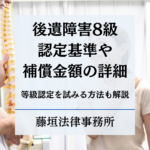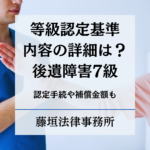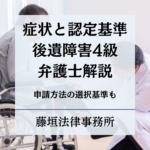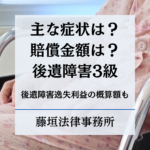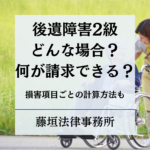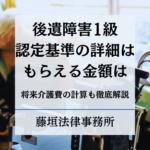後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残った精神的苦痛に対する賠償金です。
金額は、後遺障害等級ごとに定められた基準に基づいて計算され、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算出方法によって大きく変わります。
あらかじめ計算方法を理解しておくことで、不当に低い金額での示談を避け、正当な賠償を受けやすくなるでしょう。
そこで本記事では、後遺障害慰謝料の計算方法や算出基準、弁護士依頼のメリットなどを詳しく解説します。
この記事の監修者

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
この記事の監修者

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は,後遺障害等級ごとにその金額が定められています。
後遺障害慰謝料の計算基準には,大きく分けて自賠責基準と裁判基準があり,自賠責基準よりも裁判基準の方が高い金額が定められています。等級ごとの具体的な金額は以下の通りです。
| 後遺障害等級 | 【自賠責基準】 | 【裁判基準】 |
| 1級 | 1150万円 | 2800万円 |
| 2級 | 998万円 | 2370万円 |
| 3級 | 861万円 | 1990万円 |
| 4級 | 737万円 | 1670万円 |
| 5級 | 618万円 | 1400万円 |
| 6級 | 512万円 | 1180万円 |
| 7級 | 419万円 | 1000万円 |
| 8級 | 331万円 | 830万円 |
| 9級 | 249万円 | 690万円 |
| 10級 | 190万円 | 550万円 |
| 11級 | 136万円 | 420万円 |
| 12級 | 94万円 | 290万円 |
| 13級 | 57万円 | 180万円 |
| 14級 | 32万円 | 110万円 |
後遺障害慰謝料の算出基準
後遺障害慰謝料は基準によって金額が大きく変わります。主な算出基準は、以下の通りです。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準)
詳しく解説します。
自賠責基準
自賠責基準は、自動車損害賠償保障法に基づく公的な最低補償ラインで、後遺障害等級ごとに定められた定額表を用いて算定されます。
被害者がまず受けられる金額としての役割があり、迅速な支払いや最低限の補償を目的とするため、他の基準に比べて最も低く抑えられることが普通です。
また、認定や請求には所定の手続きや書類(後遺障害診断書や画像等の提出)が必要で、等級認定が得られなければ支給されない点にも注意が必要です。
任意保険基準
任意保険基準は各保険会社が内部で定める基準で、自賠責基準より高い水準を想定するものの、弁護士基準には及ばないことが多いです。
示談交渉の段階では保険会社側がこの基準を基に提示額を決めるため、被害者が専門家を介さず交渉すると任意保険基準での妥結に留まるケースが多く見られます。
また、各社の社内運用や担当者の裁量によって算定額が変わるため、具体的な金額は一律ではありません。
弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準は、裁判例や損害賠償算定の実務基準に基づき算出される水準で、三つの基準の中で最も高額になることが一般的です。
実際の裁判で認められた判例や、弁護士が交渉で用いる判例表を参考に等級や症状の程度を詳細に評価し、被害者の実損や精神的苦痛を広く反映させます。
結果として、弁護士に依頼して弁護士基準で交渉することが、金額面で有利になるケースが多いです。
後遺障害等級の認定を得るためのポイント
後遺障害等級の認定は慰謝料額を左右する重要な要素です。後遺障害等級の認定を得るためには、主に以下4つのことが必要です。
- 後遺症の症状を客観的に記録・保存する
- 適切な医師に診断書を作成してもらう
- 画像検査や検査結果などの医学的証拠を揃える
- 後遺症が自賠責の等級基準に当てはまる
詳しく解説します。
後遺症の症状を客観的に記録・保存する
後遺症の主張を裏付けるためには、症状の発生時刻や頻度、日常生活での具体的な制限などを継続的に記録することが重要です。
診察時には症状の詳細を口頭だけで済ませず、メモやスマホ動画、写真、痛みの程度を示すスケール(VASなど)を用いて客観的に残すと説得力が増します。
さらに、通院履歴や処方履歴、リハビリの記録など医療機関の記録と照合できる形で保存しておくと、自賠責や審査機関への提出書類としても有効です。
適切な医師に診断書を作成してもらう
後遺障害認定に用いる診断書は形式や記載内容が認定結果に直結するため、後遺障害の実態を正確に把握している専門医に作成してもらうことが望ましいです。
可能であれば事故直後から同じ医師に継続して診てもらい、症状の推移や治療結果を一貫して記載してもらうと診断書の信頼性が高まります。
また、診断書には主観的訴えだけでなく具体的な所見、検査数値、日常生活の制限などを詳細に記載してもらうよう依頼することが重要です。
画像検査や検査結果などの医学的証拠を揃える
MRI、CT、X線、神経伝導検査、筋電図、血液検査など、症状に応じた客観的検査を適宜実施し、その結果を保存しておくことが後遺障害認定の要です。
特に器質的変化が認められる場合は画像所見が強い証拠となり、神経・筋の障害では機能検査の数値が評価に直結します。
検査は事故前後の比較や専門医による報告書があるとより有利で、検査結果の報告書や画像データそのものを提出できるようにしておきましょう。
後遺症が自賠責の等級基準に当てはまる
自賠責による等級認定は具体的な基準表(症状の種類と程度)に照らして判断されるため、自分の後遺症がどの等級に該当しうるかをあらかじめ把握しておくことが重要です。
単に「痛みが残った」だけでは等級に該当しないことがあり、機能障害や可動域制限、感覚障害の程度を客観的に示すデータが必要です。
等級表の要件に合わせて診断書や検査結果を整えることで、認定可能性を高められます。
後遺障害の損害について弁護士に依頼すべき場合
後遺障害等級が認定された場合には,そうでない場合に比べて損害額が大きく増加するため,基本的に弁護士への相談が適切でしょう。中でも,特に弁護士委任が有力になりやすい場合としては,以下のようなケースが挙げられます。
①後遺障害等級がより上位の場合
後遺障害等級が上位であるほど,その損害額も大きくなります。損害額の大きさは,弁護士に依頼した場合の増額幅の大きさに直結するため,後遺障害等級が上位であるほど弁護士への依頼が有力になりやすいでしょう。
②過失がない又は小さい場合
過失がないか,あったとしても10%程度など小さい場合には,弁護士への依頼によって増額した分が過失相殺によって差し引かれないため,弁護士依頼の利益が大きくなりやすいところです。そのため,過失が小さければ小さいほど弁護士への依頼が有力になるでしょう。
③弁護士費用特約が利用できる場合
弁護士費用特約が利用できれば,弁護士への依頼に必要な費用の負担が大きく軽減されます。法律事務所によっては弁護士費用の負担がゼロになることも珍しくないため,そのような弁護士への依頼ができれば,費用倒れのリスクなく弁護士に依頼ができるでしょう。

交通事故の後遺障害に強い弁護士をお探しの方へ
後遺障害の損害は,金額が非常に大きくなりやすいため,適切な対応ができた場合とできなかった場合の金額面への影響もまた大きくなる傾向にあります。
加えて,他の損害項目にはない独自の争点もあり,解決を図るためには後遺障害に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
さいたま市大宮区の藤垣法律事務所では,1000件を超える数々の交通事故解決に携わった実績ある弁護士が,最良の解決をご案内いたします。
ご相談やお困りごとのある方は,お気軽にお問い合わせください。
特設サイト:藤垣法律事務所