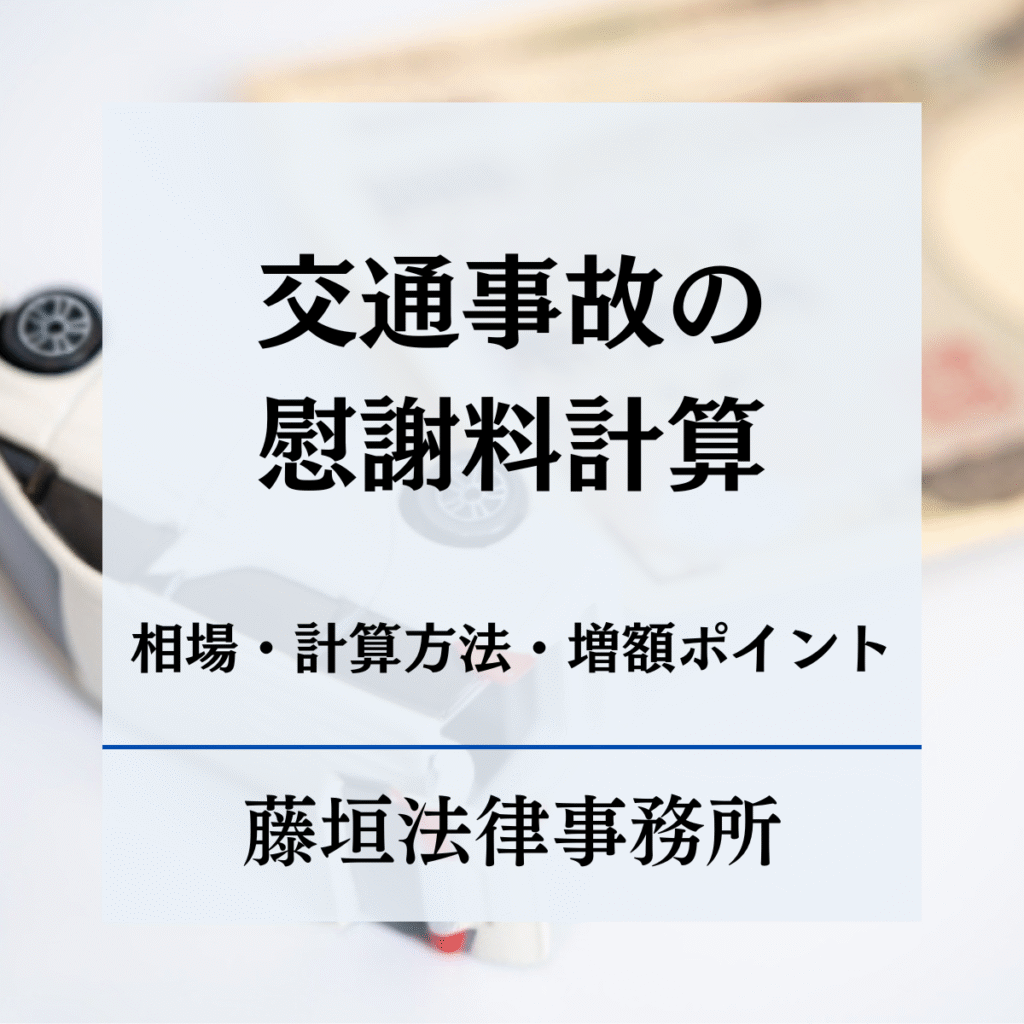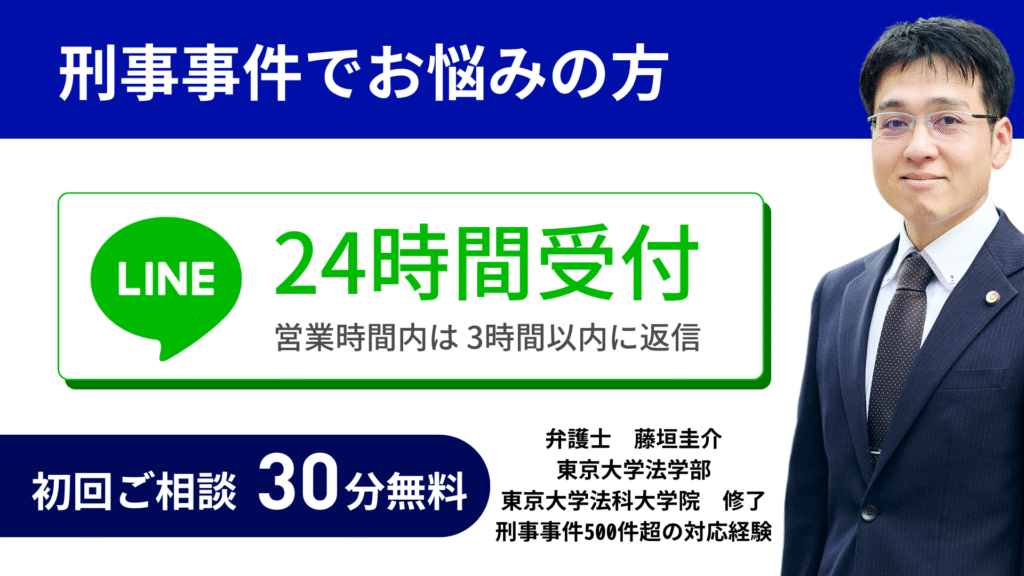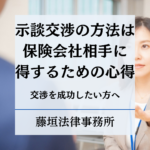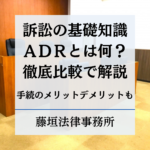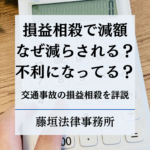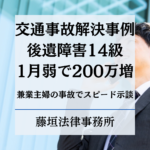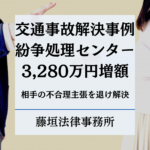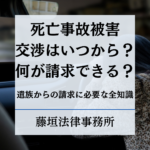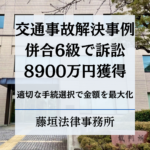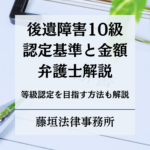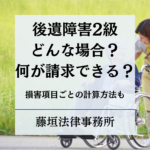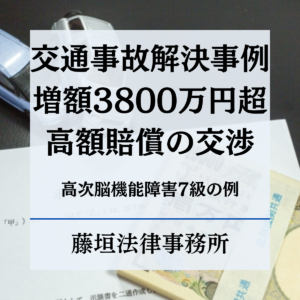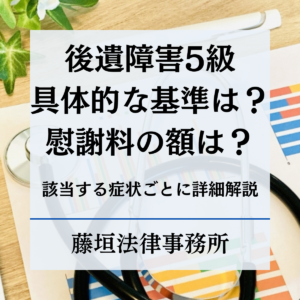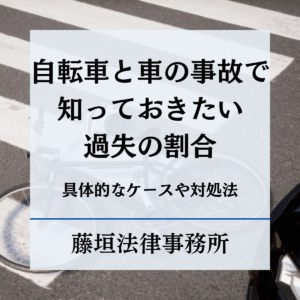「交通事故に遭ったけど慰謝料ってどうやって計算されるの?」
「示談で提示された金額が妥当なのか知りたい」
このような疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。
交通事故の慰謝料は、入通院日数や後遺障害の有無、被害者の年齢や収入などによって金額が大きく変わります。
計算方法を理解しておくことで、適正な補償を受けられ、不利益を被るリスクの軽減が可能です。
本記事では、交通事故慰謝料の計算方法や慰謝料を増額・減額させる要因についてわかりやすく解説していきます。
この記事の監修者

藤垣法律事務所
代表 藤垣 圭介
全国に支店を展開する弁護士法人で埼玉支部長を務めた後、2024年7月に独立開業。
これまでに刑事事件500件以上、交通事故案件1,000件以上に携わり、豊富な経験と実績を持つ。
トラブルに巻き込まれて不安を抱える方に対し、迅速かつ的確な対応で、安心と信頼を届けることを信条としている。
交通事故の慰謝料相場
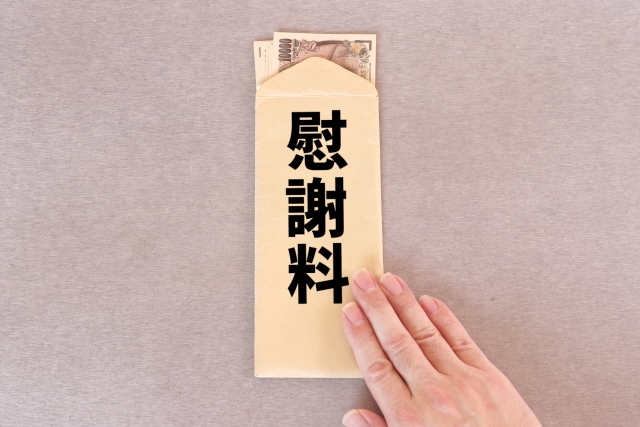
交通事故の慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛や生活への影響を金銭で補償するものであり、金額は一律ではなく状況により大きく変わります。
入通院期間が短い軽傷の場合には十数万円程度で済むこともありますが、数か月の長期通院や入院を要する場合には50万円から100万円前後になることも少なくありません。
さらに、後遺障害が残るケースでは、等級によって大きな差があり、最も軽い14級ではおよそ110万円、最も重い1級では2,800万円程度にまで達することもあります。
死亡事故の場合には、被害者の立場や家族構成によって算定される基準が異なりますが、概ね2,000万円から2,800万円の範囲に収まるのが一般的です。
また慰謝料を計算する際には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の三種類が用いられ、適用される基準によって金額が大きく異なるため注意が必要です。
打撲や捻挫などの場合、弁護士に依頼したケースの慰謝料相場は、通院期間3か月で40~50万円ほど、通院期間6か月で80万円前後というのが一例です。
交通事故慰謝料の計算方法

交通事故慰謝料を計算する際には、まず「どの基準で算定するか」が大きなポイントです。
ここからは、交通事故慰謝料の計算方法を詳しく解説します。
入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料は、むち打ちなどの軽症のケースと骨折などの重症のケースによって慰謝料額が異なり、治療やリハビリのために入通院した日数や期間を基準に算出されます。
| 通院期間 | むち打ちなどの軽症のケースの慰謝料 | 骨折などの重症のケースの慰謝料 |
| 1ヶ月 | 19万円 | 28万円 |
| 2ヶ月 | 36万円 | 52万円 |
| 3ヶ月 | 54万円 | 73万円 |
| 4ヶ月 | 67万円 | 90万円 |
| 5ヶ月 | 79万円 | 105万円 |
| 6ヶ月 | 89万円 | 116万円 |
| 7ヶ月 | 97万円 | 124万円 |
| 8ヶ月 | 103万円 | 132万円 |
| 9ヶ月 | 109万円 | 139万円 |
| 10ヶ月 | 113万円 | 145万円 |
例
打撲などの軽傷・事故発生から900日間通院したケース
54万円
| 入院期間 | むち打ちなどの軽症のケースの慰謝料 | 骨折などの重症のケースの慰謝料 |
| 1ヶ月 | 35万円 | 53万円 |
| 2ヶ月 | 66万円 | 101万円 |
| 3ヶ月 | 92万円 | 145万円 |
| 4ヶ月 | 116万円 | 184万円 |
| 5ヶ月 | 135万円 | 217万円 |
| 6ヶ月 | 152万円 | 244万円 |
例
打撲などの軽傷・事故発生から900日間通院したケース
54万円
このように、入通院慰謝料は計算方法によって大きく異なるため、提示された金額が妥当かどうかを判断するためには、必ず複数の基準を照らし合わせることが大切です。
後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は、治療を続けても完治せず、後遺症が残ってしまった場合に支払われる慰謝料です。その金額は「後遺障害等級」という基準によって大きく変動します。
| 等級 | 弁護士基準での慰謝料 |
| 1級 | 2800万円 |
| 2級 | 2370万円 |
| 3級 | 1990万円 |
| 4級 | 1670万円 |
| 5級 | 1400万円 |
| 6級 | 1180万円 |
| 7級 | 1000万円 |
| 8級 | 830万円 |
| 9級 | 690万円 |
| 10級 | 550万円 |
| 11級 | 420万円 |
| 12級 | 290万円 |
| 13級 | 180万円 |
| 14級 | 110万円 |
例えば、打撲で12級の場合、290万円が後遺障害の慰謝料となります。
自賠責基準や任意保険基準ではこれより低い金額が提示されることが多く、被害者が知らないまま示談してしまうと大きな不利益を被る可能性があります。
そのため、後遺障害が認定された場合には、必ず弁護士基準での算定を意識し、適正な金額を受け取れるよう交渉を進めることが重要です。
死亡慰謝料の計算方法
死亡慰謝料は、交通事故で被害者が亡くなった場合に、遺族へ支払われる慰謝料です。
死亡慰謝料の具体的な金額の目安は、以下の通りです。
| 慰謝料 | |
| 一家の支柱 | 2800万円 |
| 母親、配偶者 | 2500万円 |
| その他 | 2000万円 ~ 2500万円 |
一家の支柱を失った場合は2,800万円程度、母親や配偶者であれば2,500万円前後、独身で扶養家族がいない場合でも2,000万円程度が目安とされています。
交通事故慰謝料が増額するケース

交通事故慰謝料が増額するケースは、主に以下の通りです。
- 通院期間・治療内容が長期化した場合
- 後遺障害が認定された場合
- 弁護士に依頼して「弁護士基準」で交渉した場合
詳しく解説します。
通院期間・治療内容が長期化した場合
交通事故のケガは、症状によっては長期間の治療やリハビリを要することがあります。
通院期間が長引けば、それに伴って精神的負担や生活への影響も大きくなるため、慰謝料の金額も増額される傾向があります。
とくに医師の判断で継続的な治療が必要と認められたり専門的なリハビリを受け続けたりする場合は、裁判や弁護士基準に基づいた算定において高額の慰謝料が認められることもあるのです。
後遺障害が認定された場合
後遺障害が残ってしまった場合には、その程度に応じて慰謝料の金額が大きく増額されます。
後遺障害は専門的な審査によって等級が認定され、14級から1級までの段階に分類されます。
認定を受けることで、例えば14級で110万円、7級で1,000万円を超える金額、1級では2,800万円といった高額な慰謝料が認められるのです。
後遺障害の認定を受けるには医師の診断書や後遺障害診断書が不可欠であり、手続きの仕方によって認定結果が変わる場合もあります。
そのため、専門家のサポートを受けながら正しく申請することが非常に重要です。
弁護士に依頼して「弁護士基準」で交渉した場合
慰謝料を大幅に増額できる最も有効な手段は、弁護士に依頼して弁護士基準で交渉を行うことです。
保険会社が提示する金額は自賠責基準や任意保険基準をもとに算定されることが多く、被害者にとっては最低限の水準にとどまります。
しかし弁護士が介入すると、裁判例を根拠とした弁護士基準が適用され、示談金額が数倍に跳ね上がるケースもあります。
また、交渉を専門家に任せることで被害者自身の精神的負担も軽減でき、より適正な解決を図れる点も大きなメリットです。
交通事故慰謝料が減額するケース

一方、交通事故慰謝料が減額するケースは主に以下の通りです。
- 通院頻度が少ない・治療を中断した場合
- 軽傷の場合
- 事故前からの持病や既往症が影響している場合
詳しく解説します。
通院頻度が少ない・治療を中断した場合
交通事故の被害を受けた後、医師に通院を勧められたにもかかわらず通院頻度が少なかったり、途中で治療を自己判断でやめてしまうと、慰謝料が減額されるリスクが高まります。
これは、通院を怠ったとみなされると「症状が軽いのではないか」と判断されてしまい、精神的苦痛の程度が低く評価されるためです。
そのため、適正な慰謝料を受け取るためには、医師の指示に従って治療や通院を続けることが重要です。
軽傷の場合
交通事故のケガが軽傷にとどまり、治療期間も短期間で済むようなケースでは、慰謝料が低く算定されるのが一般的です。
たとえば、打撲や軽いむち打ちで1〜2週間程度の通院しか必要なかった場合、数万円から十数万円の範囲に収まることも珍しくありません。
もちろん、軽傷であっても被害者にとっては大きな精神的苦痛であることに変わりはありませんが、基準に基づいた計算上は金額が大きくならない点は理解しておく必要があります。
事故前からの持病や既往症が影響している場合
被害者に事故前から持病や既往症があり、その影響で症状が悪化したと判断される場合には、慰謝料が減額されるケースがあります。
これは、交通事故による影響と既往症の影響を区別する必要があるためで、事故が主な原因と認められなければ、全額が補償されないのです。
このようなケースでは、事故と症状悪化との因果関係を証明することが重要になり、医師の診断書や専門的な意見が交渉のカギを握ります。
交通事故慰謝料の請求を弁護士へ依頼するメリット
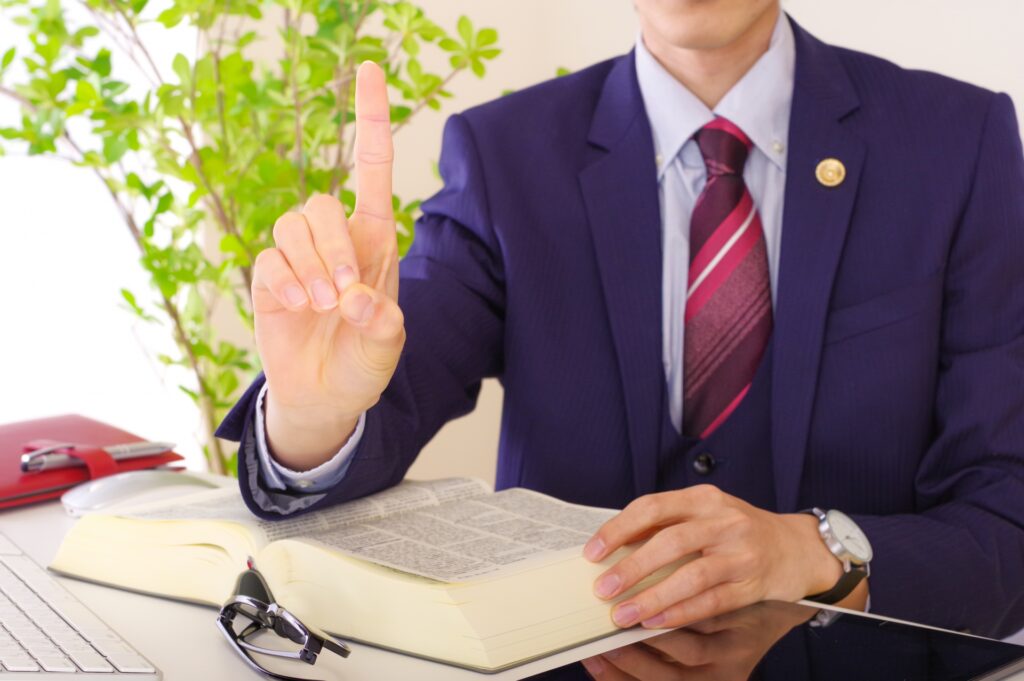
交通事故慰謝料を請求する際、被害者自身で交渉することも可能ですが、弁護士への依頼がおすすめです。弁護士へ依頼するメリットは、主に以下の通りです。
- 慰謝料の増額が期待できる
- 弁護士費用特約の利用が期待できる
詳しく解説します。
慰謝料の増額が期待できる
弁護士に依頼するメリットは、慰謝料が大幅に増額される可能性があることです。
保険会社の提示額は任意保険基準に基づくため低額になりがちですが、弁護士が介入すると弁護士基準が適用され、裁判例に基づいた高水準の金額で交渉できます。
そのため、提示額に不満がある場合や後遺障害が残ったケースでは、弁護士に相談することで本来受け取るべき補償を獲得できる可能性が高まるのです。
後遺障害のない事故では10~30万円程度、後遺障害を伴う事故では100万円単位で、深刻な後遺障害や死亡結果のある事故では1000万円単位で、それぞれ増額することは珍しくありません。
弁護士費用特約の利用が期待できる
交通事故に備えて自動車保険に加入している場合、多くの契約には「弁護士費用特約」が付帯されています。
この特約を利用すれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、自己負担をほとんどかけずに専門家へ依頼できます。
利用限度額は一般的に300万円程度とされており、通常の示談交渉であれば十分にカバー可能です。
費用面の不安が解消されれば、被害者は安心して弁護士に相談でき、適正な慰謝料を獲得するための強力なサポートを受けられるのです。
まとめ
交通事故の慰謝料は、入通院の期間、後遺障害の有無、死亡事故のケースによって大きく変動し、算定基準によっても最終的な金額に差が出ます。
保険会社の提示額だけを鵜呑みにしてしまうと本来受け取れる補償を逃す恐れがあるため、相場や計算方法を理解し、必要に応じて弁護士へ相談することが重要です。
とくに弁護士基準での交渉は増額の可能性が高いため、適正な慰謝料を獲得するうえで大きな助けとなります。
【おすすめ】
アール・アンド・アイ|交通事故鑑定:交通事故の原因と現場の検証、解析調査と事故鑑定、交通事故鑑定書作成など、個々のご要望に合わせたサービスを提供
アール・アンド・アイ|指紋鑑定:指紋採取や照合、指紋鑑定書作成、指紋証明書の発行など、個々のご要望に合わせたサービスを提供